障害者手帳は「就職に不利」ではなく「働きやすくするための武器」。正しい活用法を知ろう
「障害者手帳を持っていると、転職に不利になるのでは」と不安を抱く方は少なくありません。しかし実際には、障害者手帳は自分に合った働き方を実現するための“支援の入り口”であり、適切に活用すれば、働くうえでの大きな味方になります。特に精神障害者保健福祉手帳は、就職活動や職場での配慮を求める際の正当な根拠となり、障害者雇用枠での応募や、就労支援サービスの利用にもつながります。
現在、精神障害に理解のある企業や特例子会社、支援機関も増えつつあり、「障害者手帳を使う=不利になる」という認識は過去のものになりつつあります。大切なのは、「どのタイミングで」「どのように」使うかを正しく理解することです。障害者手帳は、自分を守りながら働くための“交渉ツール”であり、キャリアの可能性を広げる鍵でもあります。今回は、転職活動における障害者手帳の使い方と、具体的な活用法について詳しく解説していきます。
そもそも障害者手帳って転職活動でどう使えるの?
障害者手帳を使うことで、転職活動における選択肢や支援体制が大きく広がります。たとえば、障害者雇用枠に応募できるようになり、応募先企業には合理的配慮を求めやすくなるという利点があります。また、ハローワークの障害者専門窓口や、就労移行支援事業所の利用も可能となり、履歴書や面接準備、職場体験といった幅広い支援を受けられます。民間のエージェント(dodaチャレンジ、atGPなど)を利用する場合も、手帳があることで専門のキャリアアドバイザーによる丁寧な支援が受けられることが多くなります。
一方で、手帳を提示するタイミングや伝え方によって、印象や採用条件に影響を及ぼすこともあるため、自分の希望する働き方や職場環境に応じた活用の仕方をあらかじめ整理しておくことが重要です。
応募時に使う?入社後?タイミングで変わる使い方
障害者手帳を転職活動で活用する際は、「応募時に提示するか」「入社後に伝えるか」によって、使い方や得られる支援の内容が変わってきます。それぞれのタイミングでのメリット・デメリットを把握し、自分に合った選択をすることがポイントです。
障害者手帳を使うタイミングによる活用法の違い
まず、**応募時に障害者手帳を提示する**場合は、いわゆる「障害者雇用枠」での応募となり、企業は法定雇用率を満たす目的で障害者を積極的に採用する傾向があります。この枠での応募では、合理的配慮を受けられる前提での選考が行われるため、「通院配慮がある」「体調に波がある」「静かな環境で働きたい」といった要望を伝えやすく、入社後も支援体制が整っていることが多いです。また、支援機関の同席やフォローが入りやすいため、就職後の不安を減らす効果もあります。
一方で、**入社後に障害者手帳を提示する**方法もあります。このケースでは、当初は一般枠で入社し、働きながら必要性を感じた段階で配慮を求めるという流れになります。メリットとしては、職歴上の印象を気にする必要がないことや、応募の選択肢が広がることが挙げられますが、その反面、配慮の交渉が難しくなったり、企業側に制度への理解が乏しいと対応してもらえない場合もあります。
どちらの方法にも一長一短がありますが、大切なのは「自分がどのような働き方をしたいのか」「どの程度の配慮が必要か」を明確にし、必要に応じて就労移行支援やエージェントなどの専門機関と相談しながら、戦略的に活用することです。障害者手帳は“見せることが目的”ではなく、“安心して働くためのツール”であるという視点を持ち、自分にとって最善のタイミングと方法で活用していきましょう。
| タイミング | メリット | デメリット | 向いている人 | 注意点 |
| 応募時 | 障害者枠求人が選べる/配慮の提示がしやすい | 応募段階で障害が開示される | 継続的な配慮が必要な人 | 面接での説明準備が必須 |
| 内定後(入社前) | 条件交渉や配慮の確認がしやすい | 企業によっては理解が浅い場合も | 環境次第で伝えたい人 | 書面での合意を取りたい |
| 入社後 | 自分のペースで様子を見ながら開示できる | 配慮が受けられない期間が発生 | 徐々に慣れたい人/体調安定後に開示 | 職場との信頼構築が前提 |
書類提出の有無/求人選定の基準としての役割
障害者手帳を活用して転職活動を行う際には、「どの段階でどの書類を提出するのか」「どんな求人を選ぶのか」といった点が、手帳の活用と深く関係してきます。まず、書類提出の有無についてですが、障害者雇用枠で応募する場合、多くの企業では「障害者手帳のコピー」や「障害の状況・配慮事項を記載した自己申告書」などの提出を求められることがあります。これは企業側が、採用後にどのような配慮が必要かを事前に把握し、適切な配置や対応を行うためです。
一方で、一般枠で応募する場合には、手帳の提出は原則不要です。そのため、配慮を求める場合には、口頭での説明や医師の意見書、就労移行支援事業所からのサポートが必要になることがあります。いずれにしても、「書類の提出=不利になる」ということはなく、むしろ自分に合った職場を見極めるための一助と考えることが大切です。
また、障害者手帳は求人選定の基準としても大きな意味を持ちます。たとえば、dodaチャレンジやatGPでは、手帳所持者向けの求人を数多く取り扱っており、その多くが「通院配慮あり」「残業なし」「静かな職場環境」など、精神・発達障害に対する配慮が前提となっています。これは、手帳を持っていることで、あらかじめ配慮のある環境に応募できるというメリットを意味します。
就労移行支援事業所を通じた就職活動でも、手帳があることで企業実習や職場見学を受けやすくなり、支援員が企業に直接配慮事項を説明する際の根拠にもなります。つまり、手帳を持っていることで、自分に合った求人を選びやすくなり、かつ企業とのミスマッチも防ぎやすくなるのです。
障害者手帳は「ただ持っている」だけではなく、どの求人に応募し、どんな職場環境を希望するのかを選択する際の“指針”にもなります。求人を見極める際には、手帳の提出有無だけでなく、「その求人が自分の特性に合っているかどうか」を見極める目を養うことが大切です。そしてその判断には、就労支援機関の力を借りることも有効です。書類や制度をうまく活用しながら、無理のない働き方を選び取っていきましょう。
「使わないと損」な求人・制度・支援一覧
| 活用対象 | 内容 | 対象者 | 得られるメリット | 見落としがちなポイント |
| 障害者枠求人 | 配慮前提の求人/勤務形態に柔軟性あり | 手帳所持者 | 面接段階から配慮あり/負担軽減 | 求人内容に具体性があるかを確認 |
| 就労移行支援 | 転職準備・訓練・就労後のサポート | 就労に不安のある人 | 継続就労の可能性が高まる | 相談→体験→通所と段階的に進む |
| 障害者職業センター | 職業評価・アセスメント提供 | 自分の特性が言語化しづらい人 | 面接での自己説明がしやすくなる | 利用には申請が必要な場合も |
| 助成金制度 | 雇用開始時に企業側に支給 | 手帳所持者を雇う企業 | 採用しやすくなる要因に | 制度の存在を企業側が知らないことも |
障害者枠求人/通院配慮/助成金対象などの利点あり
障害者手帳を活用することで得られる利点は数多くあります。まず大きなメリットの一つが、「障害者雇用枠」での応募が可能になることです。この枠では、法律に基づいて企業に配慮義務があるため、通院配慮や勤務時間の調整、業務内容の見直しといったサポートを受けやすい傾向があります。特に精神障害をもつ方にとっては、体調の波や感覚の過敏さに理解を示してくれる環境で働くことが、長期的な安定就労につながりやすくなります。
また、企業にとっても障害者手帳を持つ方を採用することで、国や自治体からの「雇用助成金」を受け取れる場合があるため、積極的に採用し、定着支援に力を入れている企業も増えています。たとえば、特定求職者雇用開発助成金などは、精神障害者を一定期間継続して雇用することで企業に給付される仕組みがあり、制度に詳しい人事担当者であれば、支援の必要性にも理解が深いことが多いです。
さらに、就労移行支援やハローワークの専門窓口でも、手帳を持っていることで利用できるサービスの幅が広がります。たとえば、職場実習や模擬面接、職業準備訓練など、就職前のサポートが手厚くなり、「自分に合った職場かどうか」を見極めるための機会を得ることができます。dodaチャレンジやatGPといった転職エージェントも、障害者手帳を前提とした求人紹介や面接調整、入社後のフォローアップに強みがあります。
こうした制度や支援をうまく使うことで、手帳の提示は不利どころか「安心して働き続けるための武器」となり、自分にとって無理のない転職を実現する鍵になります。
手帳を活用して“働きやすくなる”3つの転職術
障害者手帳を持っていることは、単なる「証明書」にとどまらず、自分にとって必要な配慮や働き方を企業と共有するための大切な手段です。ここでは、精神障害や発達障害を持つ方が「自分らしく働く」ために意識したい3つの転職術についてご紹介します。いずれも、「制度を使いこなす」視点が求められるものであり、就職・転職活動を安心して進めるうえでの基本になります。
① 自分の「得意・不得意」を伝えて職場を選ぶ
まず最初の転職術は、「自分の特性を正確に伝え、それを受け入れてくれる職場を選ぶ」ことです。精神障害や発達障害のある方にとって、自分の「得意」と「不得意」を把握することは、職場環境とのミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。たとえば、対人コミュニケーションが苦手な方が営業職に就くとストレスが強くなってしまう一方、データ入力や事務作業など静かな環境では力を発揮できることもあります。
そのため、就職活動ではまず「自己理解」を深め、どのような配慮が必要なのか、どのような環境で力を発揮できるのかを明確にしたうえで、求人を選ぶようにしましょう。就労移行支援事業所では、自分の特性を整理するプログラムや職場体験を通じて「自分に合った働き方」のヒントを得ることができます。たとえば、manabyでは在宅型支援を活用しながら自分のペースで訓練を進めることが可能で、自分の強みや課題を冷静に見つめ直す時間を持つことができます。
また、支援員と一緒に「配慮が必要な場面」と「工夫できる方法」を整理することで、面接の場でも自信を持って伝えられるようになります。「苦手」を避けるのではなく、「どうすればうまく対応できるか」を含めて伝えることが、企業側の理解を得る大きな一歩になります。自分の特性を前向きに捉え、それに合った職場を選ぶことが、長く安定して働ける未来への土台となります。
得意・不得意」を伝えて職場選びを成功させる整理シート
| 自分の特性 | 得意なこと | 苦手なこと | 配慮してほしい点 | 合いそうな職場 |
| 感覚過敏あり | 一人作業に集中 | 大きな音/光に敏感 | 静かな環境/明るさ調整 | 在宅ワーク/特例子会社 |
| 書くことが得意/話すのが苦手 | 文章によるやり取り | 電話・雑談対応 | メール中心の業務 | 事務/データ入力職 |
| 状況判断に時間がかかる | ルーチン作業が得意 | 即判断・即返答が苦手 | ゆっくり進められる業務 | 事務補助/軽作業 |
障害内容を軸に業務内容や環境を整理
転職活動で自分に合った職場を見つけるためには、まず「自分の障害特性が、業務や職場環境とどう関係しているか」を整理しておくことが重要です。精神障害や発達障害を持つ方の多くは、「どのような作業でストレスが生じるか」「どういった環境なら集中しやすいか」「体調に影響を与える要因は何か」といったことが、日々の業務に大きく影響します。こうした情報を事前に言語化しておくことで、自分に合わない職場を避けたり、企業に具体的な配慮を求めたりすることが可能になります。
たとえば、「マルチタスクが苦手である」という特性を持つ方であれば、「一度に複数の指示を受けると混乱するため、業務は一つずつ整理して渡してもらえると助かる」といった形で、必要な配慮を具体化できます。逆に、強みとして「コツコツとした作業は得意」と把握していれば、その特性を活かせる求人を優先して探すこともできます。
このように障害内容を中心に、自分に合った業務内容や環境の条件をリストアップしておくことで、求人選定時の指針になります。支援事業所では、障害特性の整理シートやジョブマッチングツールを使って、自分と職場との相性を可視化する取り組みも進んでいます。たとえばLITALICOワークスやキズキビジネスカレッジでは、模擬職場体験や面談の中で、自分にとっての「働きやすい条件」を洗い出すサポートが受けられます。
「障害内容を伝える=マイナス要素」と捉える必要はなく、自分がどうすればより安定して働けるかを明確にし、職場と共有していくことが、結果的に双方にとって安心できる雇用関係を築くことにつながります。
② 配慮してもらいたいポイントを明文化しておく
転職活動で障害者手帳を活用する場合に欠かせないのが、「自分に必要な配慮を明文化しておくこと」です。配慮とは漠然としたものでなく、「具体的に何をどうしてほしいか」が伝わるものでなければ、企業側も対応が難しくなります。たとえば「ストレスに弱い」「疲れやすい」といった抽象的な表現ではなく、「30分に一度は小休憩を入れてもらえると集中しやすい」「体調が不安定な日は在宅勤務への切り替えが可能だと助かる」など、具体的な希望として記載することが重要です。
このような配慮の希望は、履歴書や職務経歴書に添付する「配慮事項シート」としてまとめておくと、面接時にも説明しやすく、誤解も少なくなります。また、入社後のトラブルを防ぐためにも、雇用契約書に反映してもらうように交渉することが理想的です。「あとから困った時に伝える」よりも、「最初から明記しておく」ことで、働き始めてからも安心して業務に集中できます。
就労移行支援やエージェント型サービスでは、こうした配慮内容の整理や書類作成のサポートも行っており、dodaチャレンジやatGPなどでは専門のキャリアアドバイザーが実務的な観点からアドバイスを提供しています。また、manabyではオンライン上で配慮事項の相談ができ、自宅にいながら準備を進めることが可能です。
「配慮をお願いする=わがまま」と誤解されがちですが、それは決して間違ったことではありません。むしろ、自分にとって働きやすい環境を作るための前向きな自己開示であり、企業にとっても長く安心して働いてもらうための情報となります。配慮を明文化することで、自分自身も働き方の軸を持つことができ、より納得のいく転職活動へとつながっていきます。
配慮希望を“伝わる形”に整えるチェック表
| 配慮項目 | 状況の具体例 | 伝える理由 | 調整してほしい内容 | 一言で伝える例 |
| 通院頻度 | 週1で午前に病院通いあり | 継続治療のため勤務調整が必要 | その日は午後出勤 or 休み希望 | 「週1で午前中に通院があります」 |
| 体調変動 | 月数回、集中力が落ちる日あり | 無理せず勤務継続したい | 業務量や時間の一時調整 | 「体調に波があり、調整いただけると助かります」 |
| 環境配慮 | 音に敏感で集中しづらい | 職場環境によって作業効率が変わる | 静かなスペース/席配置の調整 | 「静かな場所で作業できると集中しやすいです」 |
「言いづらい」ではなく「伝える」がカギ
精神障害や発達障害がある方の多くが、「配慮をお願いしたいけれど、面接で伝えるのは気が引ける」と感じてしまいがちです。しかし、就職後に長く働き続けるためには、最初に正直に伝えることが非常に大切です。「言いづらい」と感じるのは当然ですが、「伝えなかった結果、働けなくなる」ほうが本人にとって大きな不利益になる場合もあります。
配慮は、遠慮するものでも、申し訳なく思うものでもありません。職場に必要な環境調整を依頼することは「合理的配慮」という法的に保障された権利であり、企業側も対応の努力義務を負っています。むしろ、最初から配慮が必要だと伝えておくことで、企業側も対応方法を考えやすくなり、結果的にお互いの信頼関係を築きやすくなるのです。
たとえば、ココルポートやatGPジョブトレでは、配慮事項をどのように言葉にするかを実践的に学べる支援があります。模擬面接やロールプレイを通じて、「伝える訓練」を積んだ結果、「伝えたことで気持ちが楽になった」「面接官が前向きに受け止めてくれた」という声も多く聞かれます。
「言いづらい」から「伝えてよかった」に変えるためには、準備と練習がカギです。一人で悩まず、支援員やエージェントと一緒に、自分にとっての働きやすさを言葉にしていきましょう。
③ 面接で“配慮されたい理由”を伝える方法
面接で配慮をお願いするとき、ただ「これをしてほしい」と伝えるだけでは、企業側にとって納得しにくい場合があります。大切なのは、配慮を求める理由を“自分の特性”と“仕事への意欲”の両方から伝えることです。面接官にとっても、「なぜこの配慮が必要なのか」「配慮があることでどんな効果があるのか」が具体的に理解できると、前向きに検討してもらいやすくなります。
面接で“配慮されたい理由”を納得感をもって伝える構成
面接時に配慮を伝えるときは、以下のような3つのステップで話すと、納得感のある伝え方ができます。
①【特性の説明】:自分にどのような特性があるのかを、簡潔かつ客観的に説明します。たとえば、「私は聴覚過敏の傾向があり、騒音の多い環境では集中力が低下しやすい傾向があります」など。
②【配慮の具体例】:どのような配慮が必要かを具体的に伝えます。「そのため、なるべく静かなスペースやイヤーマフの使用などを許可いただけると、業務に集中できます」といった形です。
③【配慮による効果・意欲】:配慮を受けることでどのようにパフォーマンスが上がるか、自分の意欲や責任感も含めて伝えます。「このような環境であれば、自分のスキルを十分に活かし、長く安定して働けると考えています」と締めると、前向きな印象を与えられます。
このような伝え方は、manabyやキズキビジネスカレッジなどの支援事業所で実践的に学ぶことができ、自信を持って面接に臨むことができます。
配慮をお願いすることは、「仕事をするうえでの必要な準備」であり、「信頼関係を築く最初のステップ」です。伝えることを怖がらず、自分の力を最大限に発揮するための一歩として、自信をもって取り組んでいきましょう。
| 構成パーツ | 内容例 | ポイント |
| ①自己理解の説明 | 「私は音や人の声に敏感で、集中が途切れやすい特性があります」 | 単に「苦手」ではなく、“特性”として説明 |
| ②働く意欲の提示 | 「ただし、一人で集中する作業は得意で、書類作成などで力を発揮できます」 | 苦手の裏にある強みをセットで話す |
| ③具体的な配慮希望 | 「そのため、作業環境における静かなスペースの配慮をお願いしたいです」 | 配慮内容は具体的に&現実的に |
単なるお願いでなく「働くために必要な工夫」として伝える
配慮を求めるとき、「これは自分のわがままなのでは」と感じてしまう方も少なくありません。しかし大切なのは、それを“お願い”としてではなく、「安定して働くために必要な工夫」として、前向きな姿勢で伝えることです。たとえば「音に敏感なので静かな場所で作業したい」という希望は、「集中力を保つための環境づくり」として企業側に説明することができます。このように伝え方を工夫することで、配慮を求めること自体が、働く意欲や責任感の表れとして受け取られる可能性が高くなります。
実際にdodaチャレンジやatGPなどのエージェントを通じて就職した方の中には、配慮の理由を前向きに説明することで、企業側の理解が得られたというケースが多数あります。また、就労移行支援事業所では、伝え方の練習やアピール方法の整理を支援員と一緒に進められるため、自信を持って配慮希望を伝えられるようになります。
重要なのは「できないこと」を並べるのではなく、「こうすれば働ける」という解決策を提示することです。「苦手な電話対応の代わりに、チャットを活用して業務連絡に対応します」「通院のため週に1日午後を休むことで、週4日は安定して勤務可能です」といったように、具体的な“工夫”として示すことが、配慮を「協力すべき前提」として伝えるポイントになります。
履歴書・職務経歴書にも一工夫|手帳を活かす書類作成のコツ
就職活動で必要となる履歴書や職務経歴書も、障害者手帳を活かす転職においては、伝え方に少し工夫が必要です。障害を理由にした不安や空白期間をそのままにしておくのではなく、「これまでの経験から何を得たのか」「今はどのような環境なら働けるのか」を具体的に記すことで、採用担当者の理解を深めることができます。特に職務経歴書は、自分の強みや働き方の工夫を伝える重要な書類です。適切な配慮を求めつつ、自分の能力をしっかりとアピールできる内容に整えておくことが、選考通過の鍵となります。
職務経歴書には「できること」「配慮希望」を両立させて書く
職務経歴書では、「どのような経験・スキルがあるか」を伝えると同時に、「どのような配慮があれば力を発揮できるか」も明記することで、働く姿勢や準備が伝わりやすくなります。たとえば「前職では一般事務としてExcelによるデータ入力や請求書作成を担当し、月末処理を正確に納期内に仕上げていました」という実績と並行して、「集中力が必要な作業では静かな環境があることで、より成果が出せることがわかりました」といった補足を加えることで、自分の強みと配慮内容を同時に伝えることができます。
また、「体調管理のため週1回の通院が必要ですが、事前に申請すれば業務に支障をきたしません」といった記載を入れることで、「配慮があっても勤務に問題がない」という安心感を与えることができます。これは企業側にとっても、採用後の業務設計をしやすくする手助けになります。
manabyやキズキビジネスカレッジなどの支援機関では、実際の職務経歴書の作成サポートも行っており、「どう書けばよいかわからない」「障害のことをどこまで書いていいか悩んでいる」といった方でも、安心して準備を進めることができます。
履歴書や職務経歴書は「自分を売り込むツール」であると同時に、「自分が働く上での条件を共有するツール」でもあります。できることと必要な配慮の両方をバランスよく記載することが、就職後の安定につながります。事実を丁寧に、前向きな姿勢で伝える書類作成を心がけましょう。
| セクション | 記載内容のポイント | 実例 | 印象を高めるコツ |
| 業務実績 | 数値・結果で強みを見せる | 「事務職として月100件の処理をミスなく対応」 | 定量化で信頼性UP |
| 得意分野 | 強みと特性を絡める | 「マルチタスクより、コツコツ型作業に集中力を発揮」 | 特性が“強み”になる表現を |
| 配慮希望 | 働き続けるための必要条件を明記 | 「静かな作業環境、定期的な面談があると安定しやすい」 | “職場に貢献したい”意図を添える |
履歴書での記載例と、書かない場合の配慮ポイント
| 状況 | 記載する場合 | 記載しない場合 | 補足・工夫ポイント |
| メリット | 配慮の必要性を事前に伝えられる | 書類選考で“中立的”な判断を受けられる | 両方のメリットを理解して選択を |
| 書き方 | 「精神障害者保健福祉手帳(3級)所持、通院中」 | 特に記載せず、口頭で説明予定 | 備考欄 or 別紙メモとして添える方法も可 |
| 注意点 | 書く内容の具体性が大切(通院頻度・症状の安定性など) | 面接時に突然伝えると混乱を招く場合あり | 職務経歴書で補足する方法も有効 |
就職活動中に利用できる制度や支援と連携する方法
精神障害や発達障害のある方にとって、就職活動は「体調管理」と「将来の不安」が重なりやすい時期です。無理に急いで就職を決めてしまうと、再び働けなくなるリスクも高まりがちです。だからこそ、「今の自分に必要な支援は何か」を見極め、制度やサポートを上手に活用しながら、落ち着いて就職活動を進めていくことが大切です。
就労移行支援事業所やハローワーク、民間の転職エージェントなどでは、それぞれの状況に合わせたサポートが受けられます。たとえば、働く準備を整えるためのリハビリ的な支援が必要な場合は就労移行支援を活用し、すぐに就職を目指す段階であればエージェントとの連携が有効です。また、生活の安定を保ちながら就職活動を続けるには、金銭面での支援を得ることも重要です。ここで注目したいのが「傷病手当金」です。
傷病手当金を活用して、焦らず転職を考える時間を確保
精神的な不調や発達障害の二次障害で退職を余儀なくされた場合、生活の不安が先立ってしまい、「早く働かなければ」と焦ってしまう方も多いかもしれません。しかし、次の職場で長く安定して働くためには、しっかりと体調を整え、自分に合った仕事や職場環境を見極める時間が必要です。そんなときに活用できる制度が、「傷病手当金」です。
傷病手当金を受け取りながら、安心して転職活動を整える流れ
傷病手当金は、健康保険に加入していた人が、病気やケガで働けなくなったときに生活を支えるための所得補償制度です。一定の要件を満たしていれば、最長で1年6か月間、給与の約3分の2が支給されます。たとえば精神疾患により退職した場合でも、在職中に連続した3日以上の休職があり、その後も就労困難な状態が続いていると医師が判断すれば、退職後も受給が可能です。
この制度を活用することで、生活費の不安を抱えずに療養やリカバリーに専念でき、落ち着いた気持ちで「次はどんな働き方をしたいか」「どんな配慮があれば働けるか」を考える余裕が生まれます。また、傷病手当金を受給中でも就労移行支援事業所の利用は可能であり、体調に合わせて少しずつ社会復帰の準備を進めることもできます。manabyのように在宅型の支援に対応している事業所であれば、外出が難しい時期でも無理なくステップを踏むことができます。
転職活動は、自分に合った働き方を見つけるための大切な時間です。だからこそ、「すぐに働くこと」だけに目を向けるのではなく、制度を活用して「働ける状態を整えること」にも意識を向けましょう。傷病手当金を使いながら支援機関と連携し、一歩ずつ準備を進めていくことで、自分らしく働ける未来を築くことができます。
| ステップ | やること | ポイント | メリット |
| 1.医師に相談 | 診断書を取得 | 働けない状態であることの証明 | 支給対象かどうかの判断材料 |
| 2.申請書提出 | 健保組合に必要書類を郵送 | 会社への報告と並行して行う | 最長1年6ヶ月の金銭的サポート |
| 3.療養と転職準備 | 支給を受けながら休養・支援相談 | 焦らず次の職場選びに向き合える | 心身のリカバリーに集中できる |
障害年金を受け取りながら、働き方を再設計するケースも
精神障害や発達障害を抱える方の中には、安定した就労が難しい時期に「障害年金」を活用しながら、自分に合った働き方を模索する方も増えています。障害年金は、働けない状態を経済的に支えるための制度ですが、「働いてはいけない制度」ではありません。むしろ、自分の体調や生活に合ったペースで少しずつ働きながら、生活の自立を目指す“足場”として捉えることが重要です。
障害年金を受給しながらの就職活動は、「すぐにフルタイムで働く」ことを前提とせず、自分の体調や得意・不得意に合わせた働き方を再構築する貴重な時間になります。たとえば、「週3日からスタート」「在宅勤務で業務負担を減らす」「職場実習を通じて合う環境を試す」といった柔軟なアプローチが可能です。これにより、無理に働いて再び体調を崩すという悪循環を防ぎ、自分のペースで社会との接点を回復していくことができます。
支援機関の中には、障害年金と就労の両立を前提としたサポートを提供しているところもあります。manabyやLITALICOワークスなどでは、週数日の通所や在宅支援、通院とのバランスを考慮したプログラムが用意されており、年金受給中の方でも無理なく利用できる仕組みが整っています。
障害年金と就労の両立を考えた“再設計のステップ”
障害年金と働くことを両立させるには、いくつかのステップを意識して進めることが大切です。第一に「自己理解を深めること」です。現在の体調やストレス耐性、生活リズムを把握したうえで、「どのような働き方なら継続できるのか」を明確にする必要があります。これは就労移行支援などの訓練で得られる大きなメリットでもあります。
次に「段階的なステップアップ」を意識します。いきなり正社員を目指すのではなく、短時間勤務や職場実習、アルバイトから始めてみることが、社会復帰の大きな一歩となります。このような働き方は障害年金と調整が取りやすく、体調への負担も抑えられます。
さらに重要なのが「収入と年金のバランス管理」です。障害年金は一定の収入を超えると停止または減額される可能性があるため、年金制度の基準や手続きについても理解を深めておくことが求められます。多くの支援機関では、社会保険労務士など専門家との連携を通じて、こうした制度面の相談にも対応しています。
障害年金を受けながら働き方を整えていくことは、「長期的に安定して働く」ための土台づくりでもあります。焦らず、しかし確実に。支援と制度を味方につけて、今の自分に合ったペースで未来を描いていくことが可能です。制度は「制限」ではなく、「可能性」を広げるための仕組みであるという視点を持ち、安心して次のステップへと進んでいきましょう。
| ステップ | 状況 | 活用できる制度 | 工夫したこと | 結果 |
| 休職中 | 働けないが生活費が不安 | 障害年金(精神2級) | 医師に等級の妥当性を相談 | 申請通過で安心感が得られた |
| 再始動前 | 働きたいが体調に不安あり | 年金+短時間勤務 | 通勤日数を減らす/在宅勤務併用 | 継続就労が可能に |
| 転職時 | 手帳活用し障害者雇用枠へ | 障害者枠+年金継続 | 勤務収入と年金のバランス調整 | 安定収入と働きやすさを両立 |
就労支援事業所や支援員と連携して「伝え方」を整える
精神障害や発達障害のある方が就職を目指す際、スキルや経験だけでなく「自分の特性や配慮事項をどう伝えるか」が非常に重要になります。多くの方が「どこまで話していいのか」「どう伝えればマイナスに見えないか」と悩みを抱えていますが、そんなときこそ頼りにしたいのが、就労移行支援事業所の支援員です。支援員は、障害のある方の特性や背景に理解があり、就職活動の場面で必要な伝え方や書類の準備、企業との調整などをサポートしてくれます。
たとえば、ココルポートやキズキビジネスカレッジでは、利用者一人ひとりの状況に応じて、「自分に合った伝え方」を一緒に考える面接練習や書類添削、模擬面談などが行われています。こうした支援を受けることで、「配慮事項をどのタイミングで、どんな表現で伝えればいいのか」といった不安を軽減し、自信をもって企業と向き合えるようになります。
また、面接に同席するケースや、就職後の職場定着支援を通じて企業との橋渡しをしてくれることも多く、「一人で伝えなければならない」というプレッシャーを和らげてくれます。自分の想いや希望を言語化し、それを支援員と共有しておくことで、適切なフォローやアドバイスも受けやすくなります。
支援員と連携して“伝え方”を整える場面別チェック表
就職活動では、「伝えるべき場面」がいくつもあります。それぞれの場面で支援員と連携し、どう伝えるかを整理しておくことが、安心して活動を進めるための鍵となります。以下のようなチェックリストをもとに、支援員と事前に確認しておくと良いでしょう。
| 場面 | よくある不安 | 支援員ができること | 利用者がやること | 伝えるときのコツ |
| 面接準備 | 配慮の伝え方が不安 | 面接練習で想定質問を確認 | 回答の型をメモして繰り返す | 「必要理由+協力意志」のセットで話す |
| 履歴書記載 | 何を書けばいいかわからない | 記載例や言葉選びをサポート | 自分の言葉で表現し直す | 書きすぎず、整理して一言で伝える |
| 配属面談 | 何を伝えるか迷う | 事前に配慮内容を一緒に整理 | 優先順位をつけて話す | 配慮だけでなく、できることも伝える |
働きずらさを感じている人におすすめの転職サービス
dodaチャレンジ|ストレスを減らせる環境を一緒に考えてくれる
→dodaチャレンジ アフィリリンクを貼る
関連ページはこちら:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
LITALICOワークス|働く前に心の準備ができる就労支援
→LITALICOワークス アフィリリンクを貼る
ランスタッド|大手だから安心して相談できる環境がある
→ランスタッド アフィリリンクを貼る
atGP|理解ある職場紹介で再出発を後押ししてくれる
→atGP アフィリリンクを貼る
ミラトレ|小さな練習から始められる就労移行支援サービス
→ミラトレ アフィリリンクを貼る
【まとめ】障害者手帳 転職 活用 方法|“使う”ことで働き方は変えられる
障害者手帳は、単なる証明書ではありません。それは「自分に合った働き方を実現するためのツール」であり、「働きやすさを企業と共有するための橋渡し役」として活用することができます。精神障害や発達障害を抱える方にとって、「就職=不安」のイメージを持ちやすいものですが、手帳を正しく活用することで、その不安を「準備」と「選択」に変えていくことが可能です。
配慮が得られる障害者雇用枠の求人に応募することで、通院や勤務時間、作業環境といった働き方に柔軟性を持たせることができ、自分のペースで仕事に慣れていくことができます。また、就労移行支援事業所や専門エージェントを通じて、自己理解を深め、配慮事項を言語化する訓練を重ねることで、面接でも安心して自分を伝えられるようになります。こうした準備が、就職後の安定や定着につながっていきます。
さらに、傷病手当金や障害年金といった経済的支援を受けながら、自分のペースで就職活動を進めるという選択肢もあり、制度の活用によって「焦らず整える時間」を持つこともできます。支援員と連携し、書類の作成や面接の練習、就職後のフォローアップまで一貫してサポートを受けることで、一人では難しいと感じていたことも、少しずつ乗り越えていくことができるはずです。
障害者手帳は、“不利になるもの”ではなく、“働く力を引き出すための手段”です。その手帳をどう使うかは、あなた次第です。正しく知り、上手に使い、必要な配慮を得ながら、自分に合った働き方を手に入れていきましょう。働き方は、制度を「使う」ことで変えられるのです。
関連ページはこちら
転職前に金銭的な安心を確保したい方へ
傷病手当金の申請方法や条件についてわかりやすく解説しています。
→関連ページはこちら「傷病手当金 申請 方法」へ内部リンク
面接での配慮希望、どう伝えればいい?
成功した人が実際に話したこと、失敗から学んだ伝え方を紹介しています。
→関連ページはこちら「面接 対策 方法 成功例」へ内部リンク
履歴書の記載に迷っている方へ
障害の開示・配慮希望をどう記載するかの具体例をまとめています。
→関連ページはこちら「履歴書 書き方 ポイント」へ内部リンク
転職までの生活費に不安があるなら
障害年金の申請手続きや併用可能な制度について紹介しています。
→関連ページはこちら「障害年金 申請 手続き」へ内部リンク
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
生活とお金に関するおすすめ情報まとめ(ドメイントップページ)を見る
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
厚生労働省「こころの健康」ページも参考になります

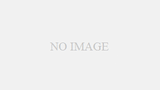
コメント