精神障害があっても安心して働ける時代。制度の仕組みを知ることが最初の一歩です
かつては「精神障害があると働くのは難しい」と考えられていた時代がありました。しかし今では、障害のある方が社会で安心して働けるように、国や自治体、民間企業が連携して支援する制度や環境が整いつつあります。特に精神障害に関しては、症状の波やストレス耐性など個人差が大きいため、配慮を前提とした就労支援が重要です。働きたいけれど不安がある、自信が持てない、どこから始めればよいかわからないという方も多いと思います。そのようなときにこそ、まずは「制度の仕組みを知る」ことが大切な第一歩です。制度を理解することで、自分に必要な支援が何なのか、どんな選択肢があるのかが見えてきます。そして、「特別ではない当たり前の働き方」を、自分のペースで目指していくことが可能になります。情報を知り、自分を理解し、支援とつながることで、誰もが働ける時代が始まっているのです。
精神障害がある人の就職は“特別”じゃない|知っておきたい制度の基本
精神障害のある方が就職を目指すとき、「特別なルート」や「限られた仕事しか選べない」と思われがちですが、実際にはそうではありません。制度上も、精神障害を持つ方が一般企業で安心して働けるように、多くの支援や仕組みが整えられています。大切なのは、「特別な就職」ではなく、「個人に合った働き方」を見つけること。そのためには、制度の基本を正しく知ることが欠かせません。
障害者雇用制度とは?誰のために、何のためにあるのか
障害者雇用制度は、障害のある方が社会の一員として対等に働く機会を保障するために設けられた仕組みです。企業には一定の割合で障害者を雇用する義務があり(障害者雇用率制度)、この中には身体障害、知的障害、精神障害を持つ方も含まれます。とくに精神障害については、2006年から法定雇用率の対象となり、以降、雇用促進の流れが加速しています。制度は「障害があるから支援される」ためのものではなく、「その人らしく働ける環境を整える」ことを目的としており、配慮を前提とした働き方が可能となるような工夫が求められます。
たとえば、atGPやdodaチャレンジのような転職エージェントでは、精神障害のある方に対して専門のキャリアアドバイザーが付き、個々の状況に応じた就職活動のサポートを行っています 。求人情報も「通院配慮あり」「残業なし」「在宅勤務可」など細かく記載されており、自分のペースや体調に合わせた職場選びがしやすくなっています。
この制度は「特別な道」ではなく、あくまで「誰もが働ける社会を実現するための土台」です。だからこそ、精神障害があっても就職は“特別なもの”ではなく、「制度を活用して、自分に合った働き方を選ぶ」という、当たり前の選択肢の一つとして捉えることができます。
| 観点 | 内容 | 働く側が得られること | 企業側が求められること |
| 法的背景 | 障害者雇用促進法 | 配慮のある就業環境の確保 | 雇用率の達成・合理的配慮の提供 |
| 制度の目的 | 「働ける」を社会に広げること | 安心して働ける土台 | 特性に応じた業務設計と配属 |
| 対象者 | 身体・知的・精神障害者(手帳あり) | 仕事を“あきらめない”選択肢 | 偏見・誤解なく対応できる環境構築 |
| 意義 | 継続的に働けることを支援 | 自己肯定感と生活安定 | 社会的信用の向上と企業価値の強化 |
配慮を前提に働ける環境づくりのための制度です
障害者雇用制度は、精神障害を含むさまざまな障害のある方が、無理なく安心して働けるよう「配慮」を前提とした環境を整えるために設けられた仕組みです。この制度の根底には、「障害があることを理由に働く機会を奪われないようにする」という考え方があります。たとえば、通院が必要な方には勤務時間の調整、過敏な感覚を持つ方には静かな作業環境の確保、対人不安がある方には業務範囲の明確化など、それぞれの特性に応じた柔軟な対応が求められます。
この制度を活かすことで、企業側も「どのような配慮が必要なのか」を理解しやすくなり、障害のある方が職場で孤立せずに働ける体制が築かれます。支援サービスでは、そうした「職場との橋渡し」も行っており、たとえばatGPジョブトレやミラトレなどの就労移行支援では、事前に配慮事項を整理し、企業に伝える練習を重ねたうえで就職を目指す支援が充実しています。
働くことは、「我慢して耐えること」ではありません。自分に合った環境で、自分の力を発揮するために必要な制度や配慮をきちんと活用すること。それこそが、長く働き続けるための鍵となるのです。
精神障害者保健福祉手帳があると受けられるサポート
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方が生活や就労の場面で適切な支援を受けやすくするための公的な証明書です。この手帳を所持していることで、障害者雇用枠での応募が可能となるほか、さまざまな福祉サービスを受けられるようになります。たとえば、就労移行支援事業所の利用や、公共交通機関の運賃割引、税制面での優遇措置など、生活や通勤を支える制度が多数用意されています。
また、dodaチャレンジやatGPといった転職支援サービスでは、手帳の有無によってマッチングできる求人が大きく変わるため、精神障害者保健福祉手帳を持っていることが、就職活動をスムーズに進めるための大きな助けになります 。企業に対しても「配慮が必要であること」が伝えやすくなるため、就職後の定着支援や業務調整といった対応も受けやすくなります。
もちろん、手帳を取得することには抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、「安心して働き続けるための道具」として前向きに捉えることが重要です。自身の特性に応じた支援や制度を最大限に活用することで、自分らしい働き方への一歩を確実に踏み出すことができるようになります。
| 支援内容 | 利用タイミング | 利用できる制度・場面 | 備考 |
| 就労支援サービス | 転職活動前〜活動中 | 就労移行支援/職場定着支援 | サービスによって受給条件あり |
| 求人の選択肢拡大 | 求人検索・応募時 | 障害者枠での応募が可能 | 一般枠と並行応募も可能 |
| 税・交通優遇 | 常時利用可 | 所得控除・通院時の割引など | 自治体により差異あり |
| 雇用後の配慮交渉 | 面接時/入社後 | 勤務時間・業務内容の調整 | 合理的配慮に繋がる材料として使える |
就職活動時・職場配属後に使える制度や支援の種類
精神障害がある方が就職活動や就労後に利用できる制度や支援は、想像以上に多岐にわたります。こうした支援を正しく活用することで、無理のない働き方や、長期的な職場定着を実現しやすくなります。たとえば就職活動中であれば、ハローワークの「専門援助部門」にて精神障害に特化した職業相談や求人紹介を受けることができます。また、就労移行支援事業所を利用することで、職業準備訓練、面接練習、履歴書作成支援、企業実習などを段階的に受けることが可能です。manabyやミラトレ、キズキビジネスカレッジといった事業所では、個別性の高い支援が行われており、自分のペースで「働く準備」ができる仕組みが整っています。
就職後には、「職場適応援助者(ジョブコーチ)」による職場訪問や、定着支援事業によって、働きながら継続的な支援を受けることが可能です。また、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、通勤費や医療費の助成、各種税制優遇などを受けられる自治体の制度を利用できることもあります。こうした制度は、自分が「安心して働き続けるための土台」であり、申請すれば自動的に効果が得られるものではなく、「どの場面で、何が必要か」を整理して使い分けることが大切です。制度と支援を正しく理解し、自分にとって必要なタイミングで活用することが、安定した就労への近道になります。
制度を“活かせる人”になるために必要な理解の仕方
制度は「ある」ことが重要なのではなく、「どう活かすか」が問われます。精神障害があっても安心して働くためには、自分にとって必要な支援を見極め、適切に利用することがカギとなります。しかし現実には、「制度があるのは知っているけれど、うまく使えない」「何を相談すればいいか分からない」という声も少なくありません。制度を“活かせる人”になるためには、自分の状況を客観的に理解し、必要な場面で適切な支援を求めるスキルが必要です。
制度を“申請するだけ”で終わらせない工夫
制度の多くは、申請すれば受けられる形式になっていますが、真に活用するためには「受け身で終わらせない」工夫が求められます。たとえば精神障害者保健福祉手帳を取得しても、それを就職活動や職場でどう使うかが明確でなければ、活用の効果は薄くなってしまいます。大切なのは、「この制度を使って、自分はどんな配慮を受けたいのか」「働く上でどこに困りごとがあるのか」といった視点を持つことです。
支援事業所では、こうした制度活用の“実践力”を身につけるための支援も行われています。たとえばatGPジョブトレやココルポートでは、面談やワークシートを通じて、自分が必要とする配慮を明確にし、それを職場でどう伝えるかを具体的に練習するプログラムがあります。また、キズキビジネスカレッジでは、「自己理解」と「自己表現」の力を養うトレーニングがあり、自分の状況を整理する力を支援してくれます。
制度を“活かす”ためには、まず自分が「どう働きたいか」「どんな支援があれば続けられるか」を言語化することが出発点になります。そして、それを制度に照らして「使える形」にしていくことで、支援ははじめて実効性を持ちます。申請して終わるのではなく、「活用して続ける」ことを意識することが、安定就労の大きな支えとなります。
| フェーズ | やること | ポイント | 成果が出る理由 |
| 申請前 | 制度の種類を調べておく | ハローワーク・支援機関で事前相談 | 自分に必要な支援が見えやすくなる |
| 申請時 | 目的を明確にして書類作成 | 通院・生活状況も具体的に伝える | 通過率と配慮内容がマッチしやすい |
| 申請後 | 支援を活かした就活設計 | 制度を活かした面接練習や求人選定 | 継続的な支援との連動で実効性が上がる |
| 雇用後 | 制度と職場のギャップを報告 | 支援員との情報共有で調整が可能 | 離職リスクを抑えて職場定着が図れる |
利用のタイミング・書類・面談時の伝え方がカギ
制度をうまく活用するためには、「いつ使うか」「どのように伝えるか」「どんな準備が必要か」といった具体的な行動が重要です。たとえば精神障害者保健福祉手帳を取得していても、就職活動のどのタイミングでそのことを開示するかは慎重に判断する必要があります。履歴書に記載する場合でも、事前にエージェントや支援員と相談し、自分が希望する配慮や支援の内容を整理しておくことが重要です。伝え方次第で、企業側の受け取り方や配慮の内容が大きく変わる可能性があるからです。
また、面接の際には「何ができて、どこに配慮が必要なのか」を具体的に説明できるよう、あらかじめワークシートにまとめておくとスムーズです。支援事業所ではこのような準備をサポートしてくれることが多く、atGPジョブトレやミラトレ、キズキビジネスカレッジなどでは、実際の面接を想定した模擬練習や書類の添削を通して、伝え方の練習を重ねることができます。
制度の効果を十分に引き出すには、形式的な申請だけでなく、自分の特性を正しく理解し、必要な支援を言葉で伝えられる準備がカギとなります。そのためには、自分一人で抱え込まず、支援員や専門家と連携しながら、タイミング・内容・方法を整えていくことがとても大切です。
企業側も「制度を理解している」とは限らない
障害者雇用制度が法律で定められているとはいえ、すべての企業がその内容を十分に理解し、実践できているわけではありません。特に精神障害に関する配慮については、企業側が具体的な知識や経験を持っていないケースも多く、「どんな配慮が必要なのか分からない」「どう接すればよいか不安」と感じている採用担当者も少なくありません。そのため、働く側から丁寧に説明したり、支援員と企業との間でコミュニケーションを取ることが、より良い雇用環境を築くうえで重要になります。
たとえば、dodaチャレンジやatGPのような障害者専門の転職支援サービスでは、企業への情報提供も含めたマッチングを行っており、利用者が安心して働けるよう、雇用前後にわたって調整をサポートしています。また、就労移行支援事業所では、企業訪問や三者面談を通じて、職場の理解促進を図ることが可能です。
企業との認識のズレを防ぐためには、「制度がある=理解してもらえる」ではなく、「制度を通じてどう配慮すべきかを一緒に考える姿勢」が求められます。働き手自身も、何をどう配慮してもらいたいかを言語化し、必要であれば支援員に橋渡しを依頼することで、職場との信頼関係が築かれやすくなります。制度はあくまで“枠組み”であり、その中で「人と人」としてどう協力できるかが、安心して働き続けるための土台となるのです。
| 状況 | 企業のリアクション | 対処の工夫 | 伝えると良いこと | 結果 |
| 面接時 | 「制度って何?」 | 資料や制度概要を簡単に持参 | 精神手帳の概要+配慮希望 | 相手の理解がスムーズに |
| 配慮相談時 | 「そんな制度知らないよ」 | 就労支援員に同席してもらう | 具体的な配慮例の提示 | 話が通りやすくなった |
| 契約書記載時 | 「記載まではちょっと…」 | 書面化の必要性を丁寧に説明 | 後々のトラブル回避になる旨を説明 | 双方の安心材料になる |
自分から伝える・交渉する力も身につけよう
障害者雇用制度や支援サービスを活用するうえで、自分の状況を「待ち」の姿勢ではなく、「伝える」「交渉する」姿勢で臨むことはとても大切です。精神障害や発達障害のある方にとって、体調の波やストレスの感じ方には個人差があります。だからこそ、自分にとってどのような配慮が必要かを、職場や支援者に対して明確に伝えられる力が、働き続けるうえでの支えになります。
たとえば「午前中は体調が安定しない」「定期的な通院がある」「マルチタスクは苦手」といった特性や状況も、工夫次第で働き方を調整できる可能性があります。しかし、それは相手に伝えなければ理解されません。就労移行支援事業所では、こうした交渉力を高める訓練として、自己理解を深めるワークや、模擬面接・ロールプレイなどのプログラムが行われています。atGPジョブトレやキズキビジネスカレッジなどでは、「どう伝えれば伝わるか」を支援員と一緒に考える時間が設けられ、実践的に練習できます。
「配慮を求めること」は決してわがままではなく、「自分が働き続けるための具体的な工夫を提案すること」です。その視点を持つことで、対等な立場で職場と向き合い、自分にとって安心できる環境を一緒につくっていくことが可能になります。
配慮を求める=わがままではない|働きやすさの交渉術
「こんなことをお願いしたら、面倒に思われるのではないか」「配慮を求めるなんて、わがままに思われるかも」——そんな不安を抱く方は少なくありません。しかし、働きやすさのための配慮は、決して“特別なわがまま”ではなく、長く安定して働いてもらうために企業側が受け入れるべき“必要な調整”です。むしろ適切な配慮を申し出ることは、職場との信頼関係を築くための大事なステップです。
通院配慮・体調変化への柔軟性など、どんなことが伝えられる?
精神障害や発達障害のある方が職場に伝えられる配慮事項には、さまざまなものがあります。たとえば、定期的な通院が必要な場合には「毎月◯日午前中は通院があるため、勤務時間をずらしたい」、体調に波がある方なら「体調が悪化する兆しがある場合は在宅勤務や時差出勤を検討したい」などが挙げられます。また、感覚過敏のある方であれば「蛍光灯の光がつらいため、間接照明や席の配置を相談したい」といった要望も、具体的に伝えることで現実的な対応につながります。
求人票には「通院配慮あり」「フレックスタイム可」などと記載されている場合もあり、dodaチャレンジやatGPといったエージェントでは、応募前に企業へ確認し、利用者に代わって調整をしてくれることもあります。
配慮として伝えられることと、伝え方の工夫
配慮を求める際に大切なのは、感情的に話すのではなく、「事実」と「希望」を分けて冷静に伝えることです。たとえば、「体調が不安定になることがある」だけで終わるのではなく、「その際は◯分程度休憩をとると回復しやすい」「報告はチャットで行う方がスムーズです」といったように、対応策まで添えると相手も受け入れやすくなります。
また、「伝えっぱなしにしない」ことも重要です。支援員と一緒に振り返ったり、企業と定期的にすり合わせを行うことで、働きやすさの調整が継続され、より良い職場環境につながります。ミラトレやココルポートでは、配慮内容を可視化した「配慮事項シート」を用いながら、実際の職場に共有するサポートも実施しています。
配慮を伝えることは、自分らしく働くための前向きな行動です。遠慮せず、自分に合った方法で伝える力を少しずつ身につけていきましょう。そうすることで、働く環境そのものを自分の味方に変えていくことができます。
| 配慮項目 | よくある要望例 | 面接・相談時の伝え方 | 伝える理由 | 伝えたことで起きた変化 |
| 通院配慮 | 「週1で午前通院あり」 | 「この曜日の午前は通院があるため、午後から勤務希望です」 | 就労継続に必要なため | 通院日を避けたシフトが組まれた |
| 体調変動への対応 | 「体調に波がある」 | 「月に数回、体調により勤務時間の調整が必要な日があります」 | 突発的な休みに備えるため | 欠勤のたびに説明せず済むようになった |
| 休憩の取り方 | 「一度に長時間働くのが難しい」 | 「1時間半ごとに短い休憩を取らせていただけると助かります」 | パフォーマンス維持のため | 集中力を保って作業できるように |
実際に交渉してよかった配慮の例を紹介
実際の就労現場では、配慮を求めることによって働きやすさが格段に改善された例が多くあります。たとえばある発達障害のある方は、朝の通勤ラッシュで強いストレスを感じていたため、勤務時間を10時始業にずらすよう交渉しました。その結果、心身の負担が軽減され、安定して出勤できるようになりました。また、感覚過敏の特性を持つ方が「電話応対が苦手」と伝えたところ、主な連絡をチャットで行うように変更してもらえたケースもあります。これにより業務効率が上がり、本人の自己肯定感も高まりました。
さらに、うつ病の既往がある方が「定期的な通院のため、月に1回の午後休を確保したい」と希望したところ、企業側が柔軟に応じてくれた事例もあります。このように、配慮を伝えることによって生まれるのは“甘え”ではなく、“双方が働きやすい環境を築くための対話”です。就労移行支援事業所の支援員が同席しながら交渉をサポートしてくれることで、本人も安心して希望を伝えることができたという声も多数あります。
キズキビジネスカレッジやatGPジョブトレ、ココルポートでは、これらの「配慮が実現した成功事例」をもとに、利用者一人ひとりに合った交渉の仕方を練習できる体制が整っており、「自分も伝えていいんだ」と思えるきっかけになっているようです。
雇用契約書に記載すべきポイントを確認
就職が決まり、いざ働き始める段階で重要になるのが「雇用契約書」の内容です。特に精神障害や発達障害のある方にとっては、口頭での約束だけでなく、文書に明記しておくことで後々のトラブルや誤解を防ぐことができます。配慮を受ける前提で就労する場合、その配慮内容を契約書にしっかりと反映させておくことが、自分を守ることにもつながります。
雇用契約書に記載しておくべき項目と理由
雇用契約書に記載しておくべき重要な項目には、以下のようなものがあります。まず「勤務時間・始業終業時刻・休憩時間・残業の有無と対応方針」。体調の波に応じた勤務時間の調整(例:通院日には午後出勤可)や、原則残業なしという条件がある場合は、あらかじめ明文化しておくことで企業とトラブルになりにくくなります。
次に、「業務内容の範囲と変更の可能性」。苦手な業務や避けたい作業がある場合、それをどう取り扱うかも明記しておくと安心です。さらに、「業務上の配慮内容(業務の指示方法・業務量の調整方法・定期的なフィードバック)」なども記載できれば理想的です。これらを明記することで、支援員やジョブコーチがサポートに入る際にも基準が共有され、配慮が形骸化しにくくなります。
たとえば、atGPやdodaチャレンジのようなエージェント型サービスを通じて就職した場合、契約内容の確認や交渉についてアドバイスをもらえることもあります。支援事業所を利用している場合は、支援員に同席してもらって確認をするのも有効です。
就労は長く続けてこそ意味があります。そのためにも、働き始める前に「言った・言わない」にならないよう、重要な条件は文書にしっかり残しておくことが、安心して働くための第一歩となります。
| 項目 | 記載例 | なぜ必要か | 記載してよかったこと |
| 通院配慮 | 「週1の通院により、勤務時間の調整を行うことがある」 | 後からトラブルを避けるため | 通院日変更時も柔軟に対応してもらえた |
| 業務内容の限定 | 「PC入力作業を主業務とする」 | 得意業務の明確化と苦手回避 | 不得意業務の依頼を減らせた |
| 勤務時間の柔軟性 | 「体調に応じて時短勤務への切り替えあり」 | 継続勤務を想定した設計 | 状況変化時も再交渉しやすくなった |
「あとから言えばいい」は危険!最初に明記しよう
働き始めた後に「やっぱりこの配慮もお願いしたい」と思う場面は決して少なくありません。しかし、こうした重要なことを「あとから言えばいい」と先送りにしてしまうと、職場との関係がこじれたり、誤解が生まれるリスクが高くなります。特に精神障害の場合は、体調の変化が急であることや、他人からは見えにくい困難を抱えていることが多いため、最初にしっかりと伝えておくことが肝心です。
配慮は、就職前の面談や雇用契約書の段階で明確にしておくことが最も効果的です。たとえば「週に1日は在宅勤務希望」「通院のため月に1回の午後休が必要」「指示は口頭よりもメモでほしい」など、実際に働き始めてから困る可能性のあることは、最初の段階で伝え、文書に残しておくことで、後々の誤解を防げます。
就労移行支援事業所では、配慮事項のリストアップや伝え方の練習、企業側への共有方法なども支援内容に含まれており、manabyやミラトレ、キズキビジネスカレッジでは「配慮事項シート」などのツールを活用して、本人と企業の双方が納得できる形で共有が進められています。信頼関係を築く第一歩として、最初に「自分に必要なこと」を誠実に明記することが、長く働くための基盤となります。
精神障害があっても“活かせる”制度と支援まとめ
精神障害があるからといって、働くことをあきらめる必要はありません。現代では、障害者雇用促進法をはじめとする制度が整備され、就労に不安を抱える人たちが安心して一歩を踏み出せる支援の仕組みが広がっています。就労移行支援事業所、エージェント型転職支援、職場定着支援など、段階ごとに必要なサポートを受けながら、自分のペースで「働き方」をつくっていける時代になっています。
精神障害者保健福祉手帳や就労移行支援の利用は、働きやすさを実現するための“手段”であり、わがままではなく、社会の中で共に働くための“選択肢”です。制度を知り、活かすことで、体調や特性に合った職場に出会う可能性が高まり、自分らしく働く未来へとつながります。
障害者雇用促進法の概要
障害者雇用促進法は、障害のある方が公平に働く機会を得られるよう、雇用の場を広げ、職場での差別を防ぎ、合理的な配慮を求める権利を保障する法律です。企業に対しては、一定の雇用率で障害者を雇うことが義務づけられており、2024年現在では民間企業で2.5%、国や地方公共団体では2.8%と定められています。この法律により、精神障害者も雇用義務の対象として含まれるようになったことは、働き方の選択肢を大きく広げるきっかけとなりました。
障害者雇用促進法の基礎と実際の活用シーン
障害者雇用促進法は、単に「雇わなければならない」と企業に義務づけるだけではありません。「差別の禁止」「合理的配慮の提供義務」などを通じて、障害のある方が安心して働ける環境を整えることを求めています。実際の現場では、通勤や勤務時間への配慮、仕事内容の調整、メンタルケアの継続支援など、多様な実践が行われています。
たとえば、ある企業では、精神障害のある社員のために「就労サポート面談」を月1回実施し、体調や業務負担について話し合う機会を設けています。また、atGPやdodaチャレンジなどの支援機関が間に入って、企業と連携を取りながら配慮の実現をサポートしている事例も数多く見られます。
このように、法律は「守るべき義務」であると同時に、「働き方を調整できる権利」を保障するものです。その制度を一人で使いこなすのが難しい場合でも、支援事業所や専門エージェントとつながることで、必要な配慮を受けながら自分らしい働き方を見つけることができます。精神障害があっても、「制度を活かして働く力」は誰にでも育てていけるものなのです。
| 内容 | 概要 | 現場でどう活かされている? | 自分への関係性 |
| 雇用義務 | 従業員43.5人以上の企業に障害者雇用が義務付け | 「障害者枠」での応募が可能 | 企業が受け入れ体制を整えている前提になる |
| 合理的配慮の提供 | 障害に応じた配慮をする法的義務 | 通院配慮・作業環境調整などが事例として存在 | 「お願い」ではなく「当然の権利」として伝えられる |
| 公開求人・就職支援 | 専門窓口で求人紹介や面接支援を実施 | ハローワークや就労支援機関で対応 | 情報を正しく得ることで選択肢が広がる |
特例子会社・在宅勤務・副業対応の企業も増加中
精神障害や発達障害のある方が安心して働ける職場は、近年ますます多様化しています。かつては「障害者雇用=単純作業」といったイメージが先行していましたが、現在では本人のスキルや希望に応じて、事務職・IT・デザイン・ライティングなど、幅広い職種へのチャレンジが可能となっています。その背景には、特例子会社の増加や、在宅勤務、副業への柔軟な対応を行う企業の登場があります。
特例子会社とは、障害者雇用を目的に設立された親会社の子会社で、障害者が働きやすいように配慮された環境が整っているのが特徴です。作業の分担やコミュニケーション手段、支援員の常駐などにより、精神的な負担を減らしながら働くことができます。ミラトレやmanabyなどの支援事業所から特例子会社への就職実績も多く、安定して長く働ける環境として注目されています。
また、コロナ禍以降、在宅勤務制度を積極的に取り入れる企業も増えており、精神的なストレスや通勤負担を軽減できるという点で、多くの当事者にとって大きなメリットとなっています。たとえば、atGPやdodaチャレンジの求人の中には「フルリモート可」「週1~2日の出社のみ」といった働き方が可能なものもあり、柔軟な働き方を実現しやすくなっています。
さらに副業やフリーランス的な働き方を許容する企業も登場し、「自分の得意を活かした働き方」や「複数の仕事を並行して行うスタイル」も選べる時代になってきました。こうした働き方の多様化は、単に“働く機会”を広げるだけでなく、「自分にとって本当に無理のない働き方」を実現するための選択肢にもなります。支援事業所を通じて、自分に合った企業や勤務形態を探すことで、より納得感のある就労が目指せるのです。
特例子会社・在宅勤務・副業OKなど多様化する働き方
障害のある方の働き方は、もはや「ひとつの型」に縛られる時代ではなくなっています。たとえば、精神的な安定を重視し、静かな環境で自分のペースを守って働きたい人には「在宅勤務」が向いています。自宅での集中力に不安がある人には「週数日の出社×リモート併用」といったハイブリッド型勤務が適しているかもしれません。企業側もこのようなニーズを踏まえ、働き方の選択肢を広げてきています。
特例子会社では、障害特性を理解したスタッフが常駐し、相談しやすい環境が整っているのが大きな特長です。作業手順の視覚化、感覚過敏への配慮、業務量の調整なども細かく対応されるため、「働くことに不安がある」という方でも安心してスタートを切ることができます。たとえば、LITALICOワークスやココルポートでは、特例子会社へのマッチング実績が多数あり、職場見学や実習を通して働き方のイメージをつかむ支援も行われています。
また、副業OKな企業では、決まった時間に会社に縛られるのではなく、自分の生活リズムや体調に応じて働ける点が魅力です。「本業では週3勤務、残りの時間は在宅でクラウドワークスやライター業を行う」といった働き方も現実の選択肢となりつつあります。
こうした働き方の多様化は、「働くこと=無理をすること」という意識を根本から変えてくれます。精神障害があるからといって、可能性を狭める必要はありません。支援事業所やエージェントを活用しながら、「自分が安心して続けられる働き方」を見つけ、選び取ることが何より大切です。その選択肢は、思っているよりもずっと広がっているのです。
| 働き方 | 特徴 | 向いている人 | 利用時の注意点 |
| 特例子会社 | 障害者雇用専門部署として設立 | サポートを受けながら働きたい人 | 職種が限られる場合も |
| 在宅勤務 | 通勤不要/自分の環境で働ける | 感覚過敏・通院頻度が多い人 | 孤独・オンオフの切り替えに注意 |
| 副業OK企業 | 複数の収入源を持てる | 時間・体力の管理ができる人 | 労働時間や税務申告の管理が必要 |
助成金・職場定着支援・障害年金との併用例
| 支援内容 | 活用できるタイミング | 実例 | 相乗効果 |
| 助成金(雇用関係) | 雇用開始時/職場環境改善時 | 支援機器設置、時短制度導入 | 企業が配慮しやすくなる |
| 職場定着支援 | 雇用開始後6ヶ月~ | 定期面談・問題発生時の介入 | 離職リスクの低減と安心感 |
| 障害年金 | 働けない・働く前の準備期間 | 収入の穴を補いながら職探し | 経済的不安を減らし挑戦しやすく |
働きずらさを感じている人におすすめの転職サービス
dodaチャレンジ|ストレスを減らせる環境を一緒に考えてくれる
→dodaチャレンジ アフィリリンクを貼る
関連ページはこちら:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
LITALICOワークス|働く前に心の準備ができる就労支援
→LITALICOワークス アフィリリンクを貼る
ランスタッド|大手だから安心して相談できる環境がある
→ランスタッド アフィリリンクを貼る
atGP|理解ある職場紹介で再出発を後押ししてくれる
→atGP アフィリリンクを貼る
ミラトレ|小さな練習から始められる就労移行支援サービス
→ミラトレ アフィリリンクを貼る
【まとめ】精神障害 雇用制度 理解|制度を「知る」から「使う」へ
精神障害のある方が安心して働くためには、制度を「知っている」だけでは不十分です。「自分にとって何が必要か」を理解し、それを支える制度や支援を具体的に「使いこなす」ことが、働き続ける力になります。障害者雇用促進法や精神障害者保健福祉手帳、就労移行支援など、国や自治体、支援機関によって整備された支援策は確かにありますが、それらを自分の生活や働き方に落とし込むことが何より重要です。
たとえば、就職活動の際には配慮事項を整理し、面接や契約書でしっかりと伝えること。入社後には定着支援やジョブコーチ制度を活用し、継続的なサポートを受けながら無理のない働き方を模索すること。また、在宅勤務や特例子会社、副業可能な職場など、多様化する働き方の中から、自分にとって続けやすい選択肢を選ぶことも制度の「使い方」の一つです。
そして、制度を使ううえで大切なのは「一人で頑張らない」ことです。就労移行支援事業所や就職エージェントといった第三者の力を借りることで、交渉や手続き、職場との調整もスムーズに進みます。manaby、ココルポート、キズキビジネスカレッジ、atGPジョブトレなど、支援の質が高い事業所も増えており、それぞれの特性に合った支援を受けることが可能です。
「制度があるから安心」ではなく、「制度を使えるから働き続けられる」。この視点を持ち、自分に合った環境とつながることが、安定した就労への第一歩です。不安があるからこそ、知り、頼り、動く。その積み重ねが、自分らしい働き方を形にしてくれるのです。
関連ページはこちら
障害年金の手続きが必要な人へ
働けない・働きにくい時期を支える障害年金の申請方法を詳しく解説しています。
→関連ページはこちら「障害年金 申請 手続き」へ内部リンク
適応障害で仕事が続けられないと悩んでいる人へ
辞める・続けるに悩む時に考えたい、働き方の選び直しについて紹介しています。
→関連ページはこちら【体験談】適応障害で仕事が続けられなかった私が、退職を経て見つけた再出発の道
副業ができる企業ってどう探す?
精神的な余裕をもって働けるよう、副業対応の企業リストや特徴をまとめています。
→関連ページはこちら「副業 OK 企業 一覧」へ内部リンク
助成金の対象者ってどんな人?
就職時や職場定着の際に使える各種助成金の条件や申請方法を紹介しています。
→関連ページはこちら「助成金 対象者 条件」へ内部リンク
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
生活とお金に関するおすすめ情報まとめ(ドメイントップページ)を見る
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
厚生労働省「こころの健康」ページも参考になります

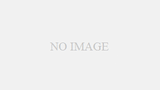
コメント