「今の仕事をずっと続けるのは不安…」そんな時こそ、リスキリングで“選べる未来”を手に入れる
毎日の仕事に追われるなか、「このまま今の仕事を続けていていいのだろうか」と、ふとした瞬間に不安を感じる方は少なくありません。特に働き方の多様化やAIの進化、社会情勢の変化によって、これまでの常識が通用しなくなる場面も増えてきました。そんな時代において、自分の価値を高め、より良い働き方を選べるようになるための手段として注目されているのが「リスキリング」です。リスキリングとは、将来性のある分野のスキルを新たに学び直すことを指し、転職やキャリアチェンジを考えている人にとっては、大きな武器となる可能性があります。特に、障害を抱えながらの就労や再出発を考える方にとっても、自分らしい働き方や安定した収入を実現するための第一歩となるのがこのリスキリングです。この記事では、リスキリングの基本から、就労支援サービスでどのようなスキルが学べるのか、実際の支援事例まで丁寧に紹介していきます。
【STEP1】リスキリングって何?なぜ今注目されているのか
リスキリングは単なる「学び直し」ではありません。働き方が激しく変化する現代において、新たな仕事や職場環境に対応するために求められるスキルを習得し、職業的な選択肢を広げるための行動を指します。特にDX(デジタルトランスフォーメーション)化が進む企業では、ITリテラシーやデータ分析、プログラミングなどのスキルが重視される傾向にあり、今や業種を問わず必要とされる力になりつつあります。厚生労働省や経済産業省も、職業能力開発やスキルギャップの解消を目的にリスキリング支援制度を推進しており、企業にとっても人材育成戦略の一環と位置付けられています。また、就労移行支援など福祉サービスの場でも、Neuro DiveのようにAIやRPAのスキルを提供する事業所や、manabyでWebスキルを学ぶ事例があるように、リスキリングは障害を持つ方の再就職や新しい働き方の選択肢としても浸透しつつあります。
リスキリングとは?「今」必要とされる理由を整理
リスキリングがこれほどまでに必要とされている理由のひとつは、急速な技術進化と、それに伴う雇用構造の変化です。かつては一つのスキルで定年まで働ける時代もありましたが、今は違います。特にデジタル分野の台頭により、旧来型の業務が自動化される一方で、まったく新しい職種が生まれています。この変化に対応するためには、継続的な学びが不可欠です。例えば、Neuro Diveでは、AIや機械学習、RPAといった先端技術を実践的に学べるプログラムが用意されており、未経験者でも段階的にスキルを習得できる環境が整っています。また、manabyでは在宅でのeラーニングを活用し、自分のペースでWebデザインやプログラミングを学びながら、働き方の可能性を広げていく取り組みが行われています。このように、働き方や生活環境に合わせた柔軟な学び方が可能になっている今、リスキリングはより多くの人にとって現実的な選択肢となっています。自分に合ったスキルを身につけることで、「やりたい仕事」だけでなく、「続けられる仕事」との出会いが生まれるかもしれません。
| 視点 | 従来の常識 | 今の変化 | リスキリングが必要な理由 |
| 雇用の前提 | 終身雇用/年功序列 | スキル重視/ジョブ型雇用へ移行中 | 働き続けるには“自分の武器”が必要 |
| 職種の選択肢 | 会社が用意したポストに従う | 副業・在宅・転職で「自分で選ぶ」時代へ | 自分でキャリアを設計する力が求められる |
| スキル寿命 | 一度覚えたら一生使える | 技術進化で“学び直し”が前提に | “今あるスキル”では不十分になる可能性大 |
キャリアの“棚卸し”から始まる、自分らしい学び直しの時代
リスキリングを始める第一歩として大切なのは、自分のキャリアを振り返る“棚卸し”です。これまでどんな仕事をしてきたのか、どんなことにやりがいを感じてきたのか、逆に苦手だったことは何かといった、自分の過去を見つめ直す作業が必要です。こうした棚卸しによって、自分が次に学ぶべきスキルや方向性が見えてきます。たとえば、manabyでは、利用者自身が自分に合った分野を見つけて進められるスタイルが導入されており、自分の「軸」を大切にしたリスキリングが可能です。また、キズキビジネスカレッジでは、過去の挫折や悩みを理解したうえで、それを強みに変える支援が行われています。学び直しの時代では、「これまで」が「これから」をつくる重要な材料となるため、自分自身を正しく理解することが、最も確実なスタート地点になります。
副業・転職・在宅勤務…あらゆる働き方に直結するスキルアップ
社会全体が多様な働き方を受け入れるようになった今、リスキリングによるスキルアップは、個人の選択肢を広げる大きな力となっています。副業で活かせるITスキルや、在宅勤務に適した事務スキル、転職市場で求められる専門スキルなど、習得できる分野は幅広くあります。ココルポートでは、600種類以上の多彩なプログラムが用意されており、事務職やデザイン、ITスキルなど、ニーズに合わせたスキル習得が可能です。また、ミラトレでは、職場を想定した疑似就労環境の中で、実践的にスキルを身につけることができるため、すぐに仕事へ活かせる力がつきます。このように、リスキリングによって得たスキルは、単に転職だけでなく、在宅勤務や副業など、さまざまな働き方に応用できるものとなり、より柔軟で自分らしい働き方を実現する後押しとなります。
【STEP2】リスキリング支援サービスの種類と特徴を知ろう
リスキリングを支える支援サービスには、実に多くの種類があります。それぞれのサービスは、対象者の状況や学びたい内容に応じて特徴が分かれており、自分に合ったものを選ぶことが重要です。たとえば、manabyのようにeラーニング形式でITやWebスキルを個別に学べる支援や、atGPジョブトレのように障害別のコースで専門的なスキルと安定就労に必要な力を習得できるタイプもあります。また、ココルポートでは、生活支援からビジネスマナーまで総合的に支える内容が整っており、定着率も高いことで知られています。これらのサービスは、単なるスキル習得にとどまらず、「就職後も続けられる働き方」を見据えた支援を行っている点が特徴です。自分の目的や生活スタイルに合った支援を選ぶことで、より実効性のあるリスキリングが実現できます。
リスキリング支援サービス比較表|公的・民間・特化型
| サービス種別 | 主な例 | 対象者 | 特徴 | おすすめな人 |
| 公的支援 | ハロートレーニング/教育訓練給付金 | 失業者・在職者・育児/障害当事者など | 安価 or 無料/修了後に就職支援あり | 費用を抑えて確実に進めたい人 |
| 民間オンライン講座 | TechAcademy/SHElikes/ストアカ | 誰でも利用可 | トレンドスキル対応/短期集中も可 | 今すぐ実践スキルを身につけたい人 |
| 就労支援連携型 | 就労移行支援/発達障害特化サービス | 障害者手帳あり or 主治医の意見書で可 | 支援員が学習〜就職まで伴走 | 配慮付きで働きたい・復帰したい人 |
公的:厚労省の職業訓練/ハローワーク講座/教育訓練給付金
費用面での不安を感じる方には、国や自治体が提供する公的支援を活用する方法があります。厚生労働省が主導する職業訓練やハローワークが実施する講座は、失業者や転職希望者向けに開かれており、再就職に必要なスキルを基礎から習得できるのが特徴です。例えば、パソコン操作、簿記、介護、プログラミングなど多岐にわたる分野があり、通所型だけでなく通信・オンライン型も選べるようになっています。さらに「教育訓練給付金」制度を使えば、対象となる講座の費用の20%から最大70%が補助される場合もあり、経済的負担を抑えつつスキルアップを目指せます。こうした公的支援は、求職者だけでなく在職中の方でも利用できる制度があるため、まずは最寄りのハローワークで相談してみることが第一歩となるでしょう。
民間:SHElikes・デジハリ・TechAcademy などの短期講座
即戦力を求められる分野でのキャリアチェンジを目指すなら、民間のリスキリング講座も有力な選択肢です。たとえば、SHElikesは女性向けにデザインやライティング、マーケティングなどの講座をオンラインで展開しており、自由な働き方を志す方に人気です。デジタルハリウッド(通称:デジハリ)は、Webデザインや動画編集、3DCGといったクリエイティブスキルを学ぶスクールで、転職・副業につなげやすい実践的な内容が魅力です。TechAcademyは、プログラミングやアプリ開発を短期間で習得できるオンラインブートキャンプとして定評があります。これらの民間講座は、学習ペースや講師のサポート、料金体系がそれぞれ異なるため、自分のライフスタイルやゴールに合わせて選ぶことが大切です。学び直しにスピード感や即効性を求める方にとって、民間講座は柔軟な選択肢となるでしょう。
障害者向け:就労移行支援を活用した“特性に合った学び方”も
障害のある方がリスキリングを進める上で頼れるのが「就労移行支援」です。これは障害の特性に応じた就労訓練を提供し、学びから就職までを一貫してサポートする仕組みで、多くの事業所が全国に展開しています。たとえばmanabyでは、自宅からオンラインで学べる環境を整えており、特性に応じたeラーニングでWebスキルやデザインを習得できます。また、atGPジョブトレでは障害別のコース制を設け、IT・Web・事務など多様な分野の訓練を提供しています。さらにココルポートでは、ビジネスマナーやコミュニケーション能力も身につけられ、定着率の高さも特徴的です。こうした支援を受けることで、自分の体調や特性に配慮しながら、自分に合ったペースでスキルを積むことができます。障害者雇用の現場でもリスキリングは高く評価されており、安定した就職への近道となる選択肢です。
【STEP3】自分に合うサービスを選ぶための3つの視点
リスキリングを成功させるには、数あるサービスの中から「自分に合うもの」を見極めることが重要です。そのためには、学びの内容だけでなく、学ぶ環境や支援体制、自分の現在の状況をしっかり把握する必要があります。今や、講座の内容はWeb系スキルや事務系、医療介護系など多岐にわたり、対面・オンライン・ハイブリッド型といった受講形態も選択可能です。また、就労移行支援や転職エージェントなど、伴走型の支援を受けられるサービスも充実してきました。つまり「何を学びたいか」だけでなく、「どこで・どうやって学びたいか」「将来どう働きたいか」という自分自身の条件や価値観と照らし合わせることが必要なのです。焦らず、じっくりと自分にとって最適なサービスを見つけることが、将来の安定したキャリアへの第一歩につながります。
サービス選びの「3つの自分軸」
自分に合ったリスキリング支援サービスを選ぶために意識すべき「3つの自分軸」は、①生活スタイル、②キャリアの方向性、③自分の強み・弱みの理解です。まず①の生活スタイルとは、通所が可能なのか、在宅中心なのか、家族や体調との兼ね合いがあるのかといった日々の過ごし方に合った形式を選ぶことです。たとえば、体調の波がある方はmanabyのような在宅型のeラーニングサービスが向いています。②キャリアの方向性では、自分が今後どう働きたいのか、たとえば事務系なのかITなのか、あるいは副業・フリーランス志向かによって選ぶ講座の内容や支援先は変わってきます。③最後に、自分の強みと弱みを正しく知ること。これは自己分析や支援員との面談で明確になっていくことが多く、就労移行支援ではこの点を丁寧に見極めて支援してくれる点が魅力です。これらの自分軸を意識することで、より納得感のあるサービス選びが可能となります。
| 軸 | 質問 | 向いているタイプ | 対応できるサービス例 |
| 目的軸 | 「転職?副業?職場復帰?」 | 明確なゴールがある人 | 公的支援/専門スクールが◎ |
| 時間軸 | 「週何時間使える?」 | 忙しい人/ブランク明けの人 | 夜間講座/短時間eラーニング |
| サポート軸 | 「学び+相談もしたい?」 | モチベ管理が苦手/初学者 | 就労支援/支援員付きサービス |
① 目的:キャリアアップ?副業?職種転換?
まずサービス選びで重要になるのが、「何のために学ぶのか」という目的を明確にすることです。現在の職場でスキルを高めてキャリアアップを目指すのか、副業で新たな収入源を得たいのか、あるいはまったく別の職種に転換したいのか──それぞれで選ぶべきサービスは異なります。たとえば、キャリアアップが目的であれば、仕事と両立しやすいオンライン講座や短期集中型のスクールが向いています。一方、職種転換を目指すのであれば、長期的な支援や実践的なトレーニングが用意された就労移行支援が力になります。就労移行支援の一例として、atGPジョブトレでは障害別の専門コースが用意されており、実務に必要なスキルとともに「続けて働ける力」を重視したカリキュラムが特徴です。自分が進みたい方向性を明確にすることで、より効果的なリスキリングを実現できます。
② 時間:平日夜?土日?どのくらい学べるか
次に重要なのが「時間軸」です。働きながら学ぶのか、退職後に集中的に取り組むのかによって、選ぶべきサービスのスタイルは大きく変わります。たとえば平日の夜や週末に学ぶ必要がある場合は、TechAcademyやSHElikesのような、オンラインで自分のペースに合わせて受講できるスタイルが適しています。反対に、就労移行支援のように日中の通所を前提とした支援機関では、訓練時間が平日の日中に設定されていることが多いため、就労支援に集中できる環境が整っている反面、スケジュールとの調整が必要です。manabyのように、在宅での学習が可能な支援もあるため、通所が難しい方や自宅で集中したい方にとっては有力な選択肢となります。自分の生活リズムや体調、他の予定との兼ね合いを考慮しながら、無理なく続けられる学習環境を選ぶことが大切です。
③ 支援内容:教材だけ?面談付き?就職先まである?
リスキリング支援の内容は、単なる教材提供から、就職までを見据えたトータルサポートまで様々です。たとえば、民間のオンラインスクールでは動画教材が中心で、講師とのチャットや課題提出などのサポートが含まれることもあります。一方、就労移行支援事業所では、学習に加えて面談や職場体験、就職後の定着支援まで一貫して支援が行われます。ミラトレでは、支援員が一人ひとりに合わせた個別支援計画を作成し、疑似就労環境での訓練も用意されているため、実務に近い経験を積みながら就職を目指せます。また、ココルポートのように、生活リズムの改善から面接対策までトータルでサポートする施設もあり、安心してステップアップできる環境が整っています。学びの「その先」まで見据えて支援内容を確認することで、自分に必要なサポートが受けられるかを見極めやすくなります。
「学び直すこと」から「安心して働ける場所」へ──次は“サポート付きの就職支援”を知ろう
リスキリングによってスキルを身につけたとしても、それを活かす「働く場」が見つからなければ、その努力が実を結ばない可能性もあります。だからこそ注目したいのが、「学び直しの後の就職」まで見据えたサポート付きの就労支援です。特に、障害やブランクなどで就職活動に不安がある方にとっては、就労移行支援サービスが大きな力となります。たとえば、atGPジョブトレやmanaby、ミラトレ、ココルポートなどでは、学習から実務体験、そして職場への定着支援までが一貫して行われており、利用者それぞれの特性に寄り添った支援が受けられます。単に「働くこと」だけでなく、「安心して働き続けられること」を目指すサポートがあるからこそ、自信を持って社会復帰できるのです。これからリスキリングを検討する方は、学ぶことだけでなく、その先の働き方や環境にも注目して、自分に合った支援サービスを見つけてください。
たとえば、こんな選択肢があります
| サービス名 | 特徴 | 向いている人 |
| 就労移行支援 | 資格取得・訓練から就職支援まで一貫サポート | 精神・発達・身体など、働き方に配慮が必要な方 |
| atGP/LITALICOワークス | 障害者雇用に特化した転職エージェント | 初めての就職・復帰が不安な方/配慮を前提に働きたい方 |
| 精神障害者職業センター | 「何ができるか」から一緒に整理 | 自分の適職や得意を客観的に整理したい方 |
リスキリング+支援で「働ける自分」が見えてくる
リスキリングを通じて新しいスキルを身につけたとしても、自分に本当にできるのか、実際に働けるのかといった不安はつきものです。そこで大切なのが「支援とセットで考えること」です。就労移行支援などのサービスでは、学んだことを実践に落とし込む環境が用意されており、現実の職場を意識した練習や職場体験を通して、“働ける自分”のイメージが具体的になります。たとえばミラトレでは、実際の職場を模した疑似就労環境でコミュニケーションや業務遂行の訓練が行われ、就職に必要な実践力を養うことができます。また、キズキビジネスカレッジのように、失敗やブランクがある方にも寄り添いながら「社会に戻るための準備」ができる支援もあります。学ぶだけでなく、支えてくれる人がいる環境で、少しずつ「できること」を増やしていく過程が、自信を取り戻し、次の一歩を踏み出す大きな支えになるのです。
「資格を取ったあと、どこで働く?」──支援付きの転職サービスを使えば“最初の職場選び”も安心
新しい資格やスキルを取得したあと、次に直面するのが「どこで働くか」という課題です。知識があっても、それを活かせる職場が見つからなければ意味がありません。そんなときに頼れるのが、支援付きの転職サービスです。これは、求人の紹介に加えて、面談や職場見学、就職後の定着支援までをトータルで提供してくれるサービスで、特に初めての転職や障害を抱える方にとって心強い存在です。自分ひとりで仕事を探すよりも、キャリアの専門家と一緒に「自分に合った職場」を見つけられるため、最初の就職でつまずきにくくなります。
“スキルはあるのに、働くのが不安”…それは“環境”の問題かもしれません
資格を取ったのに、なかなか就職に踏み出せない。そんな声の背景には、「自分に合った職場が見つからない」「続けられる自信がない」といった環境への不安があります。これは、個人の努力やスキル不足ではなく、職場とのミスマッチやサポートの有無が大きく影響しています。たとえば、atGPジョブトレでは、障害別の支援体制により、自分の特性に合った働き方や職場選びが可能となっており、結果的に長く安定して働ける人が増えています。また、マイナビパートナーズ紹介のように、非公開求人を含めて多様な働き方の提案が受けられるサービスもあり、「働ける環境」を重視したマッチングが実現しています。自分らしく働ける環境を見つけることこそが、リスキリングの成果を最大限に活かす鍵なのです。
支援付きの転職サービスとは?
支援付きの転職サービスは、単に求人を紹介するだけでなく、「あなたが安心して働ける」ことを前提に支援を行う仕組みです。たとえば、atGPやdodaチャレンジ、LITALICOワークスなどは、障害のある方を対象に、キャリアカウンセリングから履歴書の添削、面接対策、職場見学、入社後の定着支援までをワンストップで提供しています。利用者の中には、これまで就職に自信が持てなかった方や、職場でつまずいた経験がある方も多く、そうした人たちが安心して就職できるように、それぞれの「特性」や「希望」に応じた求人紹介を行ってくれます。支援員が面談を通して丁寧にサポートしてくれるため、働きたい気持ちはあっても一歩踏み出せない人にとって、強い味方となるサービスです。
資格+支援で就職した人の事例と、その活用法
実際に、資格を取得した後に就労移行支援を活用して就職に成功した人たちの事例を見ると、「学び+支援」の相乗効果がよく分かります。たとえばmanabyでプログラミングやデザインのスキルを学び、IT系企業への就職を果たしたケースでは、スキルを身につけただけでなく、自信を持てるようになったことが成功の要因となっています。また、キズキビジネスカレッジを経て、コミュニケーションが苦手だった方が、自分の強みを活かせる職場に出会い、安定して勤務を継続できている事例もあります。こうした成功事例に共通しているのは、「一人で頑張らず、専門家と一緒に進めたこと」です。自分に合ったサービスを活用すれば、スキルだけでなく就職そのものにも成功しやすくなり、安心して社会復帰ができるのです。
| 資格 | 職種 | 利用した支援 | 就職先での配慮 | 成功ポイント |
| MOS(Word/Excel) | 在宅事務 | 就労移行支援 | 業務量の調整/電話なし/朝礼なし | 練習→実習→採用の流れで安心 |
| 登録販売者 | ドラッグストア接客 | atGP(転職エージェント) | 通院日のシフト配慮/人間関係の仲介あり | 配慮内容を事前に明文化して伝えた |
| 簿記2級 | 経理アシスタント | ハローワーク×就職支援連携 | 部署の静音化/声かけの頻度設定 | 職場見学+試用期間で納得入社 |
資格だけでは不安な人にこそ、支援付き転職が合っている理由
資格を取ることで自信がつく一方で、「本当に仕事に就けるのか」「実際の現場で通用するのか」といった不安を感じる方も多くいます。とくに、初めての職種にチャレンジする人や、ブランクがある方、体調や障害への配慮が必要な方にとっては、資格だけで転職活動を進めるのは心理的ハードルが高く感じられるでしょう。そんな不安を抱える方にこそ、「支援付き転職サービス」が適しています。
支援付き転職では、履歴書の書き方や面接対策などの実務的なサポートだけでなく、「どんな職場なら自分に合うのか」といった相談も可能です。たとえば、atGPやdodaチャレンジ、マイナビパートナーズ紹介といった専門サービスでは、キャリアアドバイザーが個々の状況を丁寧にヒアリングしながら、働く環境や条件にマッチした求人を紹介してくれます。
また、支援付き転職サービスの多くは、就職後の定着支援も行っているため、「入社してからもサポートしてもらえる」という安心感があります。たとえば、障害者向けの就労移行支援事業所であるミラトレやココルポートでは、ビジネスマナーや職場のコミュニケーションを重視した訓練を行い、その後の職場適応までしっかりと支えています。
資格を取得したことは大きな一歩ですが、それを“働く力”に変えるには、実際の職場で経験を積むことが必要です。その橋渡しとなるのが、支援付きの転職サービスです。資格だけでは不安な方にとって、無理なく安心してキャリアを築いていくための心強いパートナーとなるはずです。
| 一般的な転職 | 支援付き転職(就労移行・障害者枠) |
| 面接準備を一人で行う | 支援員と一緒に“伝え方”を練習できる |
| 企業との条件交渉が難しい | 支援員が企業に配慮内容を説明・調整 |
| 入社後の定着支援なし | 継続的に相談できる“アフターケア”あり |
“安心して働ける最初の職場”に出会うには
転職や就職を考えるとき、多くの人が感じるのが「本当にこの職場でやっていけるだろうか」という不安です。特に初めての転職やブランクがある場合、最初に選ぶ職場の環境がその後の働き方に大きな影響を及ぼします。だからこそ重要なのが、“安心して働ける最初の職場”と出会うことです。そのためには、自分の体調や働き方の希望、特性に対してきちんと理解があり、相談できる体制が整っている職場を選ぶ必要があります。支援付き転職サービスや就労移行支援事業所では、そうしたマッチングを丁寧に行うため、就職後のミスマッチが少なくなります。たとえば、ミラトレでは本人の特性を踏まえた個別支援計画のもとでトレーニングを行い、働く準備を着実に整えたうえで就職につなげています。また、manabyのように在宅訓練も可能な支援機関では、自分のペースを崩さず就職活動ができるため、無理なく安心して第一歩を踏み出せるのです。
“無理なく働きたい”という希望を叶えるには|支援機関の力を借りるという選択
「フルタイムでは働けない」「人間関係が不安」「体調を優先したい」──そんな声は決して珍しくありません。けれど、自分一人だけで仕事探しを進めると、こうした希望をうまく伝えられなかったり、理解のある企業を見つけるのが難しかったりするものです。そんなときにこそ、就労移行支援や障害者向け転職サービスといった“支援機関”の力を借りるという選択肢があります。これらの機関は、就職のためのスキルやマナーの習得だけでなく、面接練習、体調管理のアドバイス、就職先との連絡調整、さらには定着支援までを一貫してサポートしてくれます。たとえば、ココルポートでは600種類以上のプログラムから、個人の特性に合ったトレーニングが選べ、職場定着率90%という高水準の支援実績を誇っています。無理なく、長く働ける職場に出会うには、自分だけで頑張るのではなく、信頼できる支援機関の存在を活用することが何よりの近道となるのです。
「働きたいけど、体調や特性が気になる…」その不安を一人で抱えなくていい
「働きたい」という意欲はあるものの、体調の波や発達・精神的な特性が気になり、なかなか一歩を踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。無理をすれば長続きせず、逆に体調を崩してしまう恐れもあるため、自分のペースや特性を尊重した働き方が求められます。就労移行支援事業所では、そうした個々の悩みに寄り添いながら、実際の職場で必要なスキルを身につけるとともに、企業とのマッチングや就職後のフォローまで丁寧に支援してくれます。manabyでは、発達障害や精神疾患を持つ方が安心して学べるよう、在宅で学習できる環境が整っており、定期的な面談を通じて体調に合わせた支援が可能です。こうした支援機関を利用することで、不安を一人で抱え込まず、専門家と一緒に働く準備を整えることができます。「不安があるからこそ、支援を受ける」──それは前向きな選択なのです。
サポート機関の役割と“できること”
サポート機関の最大の役割は、「一人では難しいことを、共に進める」ことにあります。就労移行支援や障害者専門の転職エージェントでは、スキルアップだけでなく、キャリア設計、職場探し、面接対策、定着支援といった就職活動全体をトータルで支えてくれます。たとえば、atGPジョブトレでは障害別の専門コースにより、自分の特性に合った内容で段階的にスキルを身につけられます。また、マイナビパートナーズ紹介やdodaチャレンジといった支援付き転職サービスでは、非公開求人の紹介から入社後のフォローまで一貫して行われており、働くことへの不安を少しずつ解消していけます。サポート機関の支援を受けることで、就職活動を“孤独な戦い”にせず、「自分らしく働く」未来を現実に近づけることができるのです。
| 機関名 | 主な支援内容 | 向いている人 | 特徴 |
| 就労移行支援 | 職業訓練/職場体験/配慮交渉 | 障害者手帳 or 主治医意見書がある人 | 2年間の支援/個別計画あり |
| 障害者職業センター | 職業評価/適職診断/面談練習 | 自分の「できること」を整理したい人 | ハローワークと連携して紹介も可能 |
| atGP/LITALICOワークス | 転職相談/企業マッチング/定着支援 | 一般就職が不安/職場配慮を求めたい人 | 支援員が企業との間に入ってくれる |
“ひとりじゃない”と感じながら働く準備を進める
「働くこと」に対して不安を抱えているとき、最も心強いのは「ひとりではない」と感じられる支援の存在です。就労移行支援や障害者向け転職サービスでは、利用者一人ひとりに合わせた支援が提供されるため、孤立感を感じずに就職準備を進めることができます。たとえばmanabyでは、自宅学習のスタイルを選べることで無理なく学び続けられ、必要に応じて面談やカウンセリングを受けられる体制が整っています。また、ミラトレやココルポートのような施設では、スタッフが日々の訓練を通して利用者と密に関わりながら、社会参加への一歩を支えてくれます。安心して前に進むためには、「誰かが一緒に考えてくれる」環境が何よりの支えになるのです。
・訓練・就職・アフターケアまで“一気通貫”の安心感
支援機関の大きな特長の一つは、「訓練から就職、そして定着支援まで」を一貫して行っている点です。たとえばatGPジョブトレでは、障害特性に合わせた職業訓練を実施し、企業とのマッチング後も定期的なフォローアップを行うことで、就職後の不安や問題にもしっかりと対応しています。このように就職して終わりではなく、働き続けるためのサポートがあることで、初めての職場でも安心して挑戦できます。
・配慮事項も“あなたの代わりに伝えてくれる”支援体制
面接や入社時に「自分の特性をどう伝えるか」は、多くの人が悩むポイントです。支援付き転職サービスでは、支援スタッフが本人に代わって企業に対して配慮が必要な点を事前に伝えてくれるため、無理をせず自分らしい働き方をスタートできます。たとえば、dodaチャレンジやマイナビパートナーズ紹介では、企業との調整役を担うキャリアアドバイザーが在籍し、職場環境や業務内容について事前に細かく擦り合わせを行っています。これにより、安心して入社できる土台が整えられています。
・働き方に合わせた“職場環境選び”ができる
「フルタイムで働ける日もあれば、休息が必要な日もある」──そんな個別の事情に寄り添った職場を探すには、支援機関のネットワークが有効です。就労移行支援事業所や支援付き転職サービスでは、時短勤務や在宅ワーク、配慮事項に理解のある企業など、利用者に適した職場環境の情報が蓄積されています。たとえば、manabyでは在宅勤務に対応した求人紹介も行っており、通勤が難しい方にも柔軟な選択肢を提供しています。こうした環境の選び方こそが、長く安心して働くための鍵となります。
スキルだけじゃない。“自分を理解してくれる職場”を探すことが、本当の意味でのリスタート
リスキリングによって新たなスキルを得ても、それを安心して発揮できる職場がなければ、働くことへの不安は払拭できません。だからこそ、本当の意味でのリスタートに必要なのは、「自分を理解してくれる職場」と出会うことです。職場での人間関係、業務の負荷、体調への配慮──これらを理解し、必要な対応をしてくれる職場環境こそが、スキルを活かすための土台になります。支援機関を通じた就職活動では、こうした環境を重視したマッチングが行われるため、自分の特性を無理に隠すことなく、ありのままの自分で働くことが可能になります。スキル習得はスタートラインであり、ゴールは「自分らしく働ける場を見つけること」なのです。資格や経験に加えて、自分に合った職場を選ぶ目を養うことで、ようやく本当の意味での再出発ができると言えるでしょう。
スキルより先に、「どんな環境なら安心して働けるか」を考えよう
「このスキルがあれば仕事に困らない」と思っていても、現実には職場とのミスマッチによって早期退職してしまうケースも少なくありません。だからこそ、スキル習得の前に考えるべきなのは、「どんな環境なら自分は安心して働けるのか」という視点です。たとえば、静かな職場で集中して作業したいのか、誰かと相談しながら進めたいのか、時間に柔軟な勤務形態が必要なのか──自分の働き方のスタイルを明確にすることで、より合った職場を選びやすくなります。就労移行支援や支援付き転職サービスでは、こうした希望を丁寧にヒアリングし、本人の体調や特性、ライフスタイルに合った職場を一緒に考えていく支援が行われています。働くうえで一番大切なのは、自分が無理をしないで続けられること。その第一歩として、スキルより先に「環境選び」を始めてみてください。
“理解のある職場”とはどんな場所?
“理解のある職場”とは、単に障害や特性について知識があるだけでなく、「その人が安心して働けるように実際に配慮や対応がされている場所」のことです。たとえば、静かな作業スペースの確保、業務指示の出し方の工夫、定期的な面談や体調確認の実施など、具体的な取り組みを通じて、個々の事情に寄り添っている職場です。こうした職場は、就労移行支援事業所や支援付き転職サービスを通じて見つけることができます。ココルポートでは、実際の企業とのマッチング前に疑似職場環境での訓練を行うことで、職場の雰囲気に慣れるステップを踏むことができ、就職後の定着にもつながっています。また、atGPやマイナビパートナーズ紹介を通じて紹介される企業は、配慮事項に理解があり、柔軟な対応が可能な職場が多いのが特徴です。理解のある職場に出会うことができれば、スキルを存分に活かし、長く安心して働き続けることができるのです。
| 理解のある職場の特徴 | 実例 | 利用された支援 |
| 通院日・勤務時間に柔軟性がある | 「通院日に午後出勤で調整」 | 就労移行支援+企業説明会 |
| 配慮事項を事前に共有できる | 「“声かけは1日1回まで”が了承された」 | 精神保健福祉士の同席面談 |
| “困ったときに話せる人”がいる | 「メンタルチェック面談が月1である」 | atGPの定着支援プログラム |
「スキル×理解される環境」=長く働ける場所
スキルを身につけたとしても、それを活かせる職場環境がなければ長く働き続けることは難しいものです。逆に、スキルが発揮できる「理解される環境」があれば、安心して自分らしい働き方を築いていくことができます。大切なのは、スキルと環境の両方が揃うことで初めて「長く働ける場所」が見つかるということです。就労移行支援や支援付き転職サービスでは、こうしたバランスを重視し、利用者一人ひとりに合った職場探しを支援しています。たとえば、manabyでは自宅でスキルを身につけながら、自分に合った働き方を模索するサポートがあり、継続して働くための準備が整えられます。このように、スキルの習得と環境づくりの両面から支援を受けることで、自分に合ったキャリアを安心して築いていけるのです。
・続けることが“キャリア”になる
転職や就職において重要なのは、「どれだけ続けられるか」です。高いスキルを持っていても、体調を崩したり職場の人間関係に悩んで離職してしまっては、それまでの努力が報われません。だからこそ、「続けられる環境」で働くことが、そのままキャリアとして積み上がっていくのです。支援機関では、本人の体調や希望に配慮した職場選びをサポートしてくれるため、継続した勤務が実現しやすくなります。
・「自分のままでいい」と思える職場がある
「自分を押し殺して働く」のではなく、「自分の特性を理解してもらった上で働く」ことができれば、精神的な負担も大きく減ります。たとえば、発達障害を抱える方が、苦手なことをカバーし合えるチーム体制の職場で働くようになった事例もあります。就労移行支援や支援付き転職サービスでは、そうした“自分らしさ”を尊重してくれる職場を見つけるためのサポートが受けられます。
・無理に“強がらない働き方”で、自信を取り戻せる
「できるふり」をし続けることは、長期的には心身の負担になります。支援機関では、自分の本当の状況や特性に向き合い、それを職場に理解してもらうことで、無理のない働き方を実現する支援を行っています。ミラトレでは、そうした自己理解を深めるプログラムが組み込まれており、働くことに自信を失っていた人が、少しずつ自信を取り戻していく事例も見られます。無理をしないことは、決して甘えではなく、自分を大切にする第一歩です。
【STEP4】実際にリスキリングで成功した人の体験談
リスキリングを通じて新たな道を切り拓いた人々の体験談には、同じように悩んでいる方へのヒントや勇気が詰まっています。たとえば、manabyを利用したある女性は、長年のブランクに不安を抱えていたものの、自宅でのeラーニングを通じてWebデザインのスキルを習得。サポートスタッフの面談で徐々に自信を取り戻し、在宅勤務に理解のある企業に就職しました。現在は自身のペースで仕事をこなせるようになり、「自分の力で働ける」という実感を得ています。
また、ミラトレを利用していた男性は、うつ病の療養からの再出発でした。復職に対して強い不安があったものの、疑似就労やグループワークを通じて、職場でのコミュニケーションスキルを身につけることに成功。支援スタッフの丁寧なサポートに支えられ、現在では一般企業での事務職に就いています。
さらに、atGPジョブトレでは、精神疾患を抱える方が、特性に応じた専門コースで実務訓練を積み、理解のある企業とマッチング。面接時にはスタッフが同席し、必要な配慮を伝えてもらえたことで、安心して就職することができたという事例もあります。
これらの事例に共通するのは、「一人で頑張らなかった」ということです。スキルを身につけるだけでなく、自分を理解してくれる環境と人の支えがあったからこそ、新たな一歩を踏み出すことができたのです。リスキリングは、自分の人生を再構築するための大きなチャンスです。そしてその先にあるのは、“無理をしなくても働ける”という確かな未来です。
リスキリング成功者3人のタイプ別ストーリー比較
| タイプ | 年代・背景 | 学んだ内容 | 就職・転職先 | ポイント |
| 主婦/在宅復帰型 | 40代・子育てブランク10年 | Webデザイン(SHElikes) | ECサイト運営のパート職 | 家事スキルを“デザイン感覚”に転換 |
| 障害配慮型 | 30代・うつ病からの再挑戦 | MOS+事務基礎(就労移行) | 在宅型データ入力 | 自分のペースで働ける職場選定が鍵 |
| 副業→本業型 | 20代・営業から転向 | ライティング+SEO | コンテンツ制作会社に転職 | 副業ポートフォリオが“実績”に |
・発達障害を持つ30代女性|就労移行×MOS取得→在宅事務へ転職
この女性は、長年人間関係の悩みから職場に定着できず、自己肯定感も低くなっていた時期に、就労移行支援事業所manabyに通い始めました。在宅でも通所でも学習が進められる柔軟な環境のなか、支援員との面談を通じて自分の特性と向き合い、無理なく取り組める「在宅での事務職」に目標を定めました。学習内容として選んだのは、パソコン操作の基礎スキルとMicrosoft Office Specialist(MOS)の資格取得。eラーニング形式の教材で少しずつ学びを積み重ねた結果、資格を取得し、自信をつけることができました。その後、支援員の紹介で在宅勤務可能な事務職に就職し、現在も安定した働き方を継続中です。
・40代主婦|SHElikesでWebデザインを学び、副業で月5万円
子育てが一段落したタイミングで、「自宅にいながら収入を得たい」と考えた40代女性は、キャリア支援サービスSHElikesに登録。未経験から始められるカリキュラムに魅力を感じ、Webデザインコースに挑戦しました。講義動画や課題制作、コーチングセッションを通じて、デザインの基礎からバナー制作、HTML/CSSの簡単な知識までを習得。卒業後はSNSでつながった知人経由で、小規模なWeb制作案件を受注するようになり、現在では月に2〜3本の案件をこなすことで、副収入として安定して月5万円前後を得られるようになりました。自宅でできる仕事で生活にゆとりが生まれ、自己肯定感も向上したと話しています。
・20代男性|失業中に無料訓練→介護職へ再就職+助成金活用
コロナ禍で勤務先を退職した20代男性は、ハローワークを通じて無料の公共職業訓練に参加しました。受講したのは介護職向けの基礎講座で、実技と座学の両面からケアの基本を学べるカリキュラムでした。職業訓練期間中には、生活支援としての職業訓練受講給付金を活用することができ、生活費の心配なく学習に専念できたことが再出発の大きな助けとなりました。訓練終了後には、訓練先の紹介で介護施設へ就職し、今では利用者との関係を大切にしたケアができる職員として活躍しています。スキル取得と再就職支援が一体となった体験を通じて、「学ぶことが生活を変える力になる」と実感したそうです。
【STEP5】“学びっぱなし”にしないための実践活用法
せっかくリスキリングで新しいスキルを習得しても、それを実際の仕事に活かせなければ「学びっぱなし」で終わってしまいます。学びを意味のあるキャリアへと変えていくためには、実践の場を意識して行動することが重要です。まずは小さなアウトプットから始めるのが効果的です。たとえば、SHElikesの卒業生がSNSや知人ネットワークを通じて仕事を得たように、自分のスキルを可視化し、試す場を自分で作る意識が必要です。また、manabyのように就労移行支援を通じて企業とのマッチングが支援される環境では、学んだ内容がそのまま実務につながるよう設計されています。
もう一つのポイントは、学びを「就職活動の武器」として活かすことです。資格やポートフォリオは、企業に対して自分のスキルを客観的に証明できるツールです。たとえばMOS資格やWebデザインの作品は、書類選考や面接での大きなアピール材料になります。また、支援付き転職サービスでは、これらを活かした職務経歴書の書き方や面接対応のアドバイスも受けられるため、自信を持って就職活動に臨むことが可能になります。
そして何より、学びは「継続」が大切です。一度きりの訓練で終わるのではなく、働きながら少しずつスキルを深めていくことで、自分の市場価値や働き方の幅を広げていくことができます。学びっぱなしにしないためには、支援と実践の場をうまく組み合わせて、自分の学びを日常に活かす「働き方のサイクル」を作っていくことが鍵なのです。
“学びっぱなし”を防ぐ実践活用プラン表
| スキル定着法 | 内容 | 実践例 | 成功ポイント |
| ポートフォリオ化 | 学んだ内容を形に残す | サンプル制作物/ブログ/GitHub | 「見せる実力」を持っておく |
| 副業実践 | 小さな案件に応募/練習 | クラウドワークス/ココナラ | フィードバックが成長につながる |
| 職務経歴書に反映 | 新スキル+成果を明記 | 「Excel業務×自動化経験あり」など | 数字で成果を見せると◎ |
ポートフォリオ作成/副業での実務化/職務経歴書への落とし込み
リスキリングで学んだ内容を“実務につなげる”ために有効なのが、ポートフォリオの作成です。たとえば、Webデザインやプログラミングを学んだ場合は、自作のバナーやコーディングしたサイトをまとめたポートフォリオを準備することで、自分のスキルを具体的に伝えることができます。ポートフォリオは、副業案件への応募や就職面接の場でも大きな武器になります。また、副業での実務経験を積むことも非常に有効です。クラウドソーシングやSNSを通じて小さな仕事を受けるだけでも、実績として職務経歴書に記載できる具体的な成果になります。
さらに、これらの経験やスキルを「職務経歴書」にしっかりと落とし込むことが重要です。単に「学びました」ではなく、「このスキルを活かして〇〇を作成・対応しました」という形で実績を言語化することで、採用担当者に説得力をもって伝えることができます。SHElikesでWebデザインを学んだ40代女性のように、実務経験と成果物を組み合わせて職務経歴書に記載した結果、副業から本業への足がかりを掴んだケースもあります。リスキリングを実践的なキャリアへ昇華するには、スキルを可視化し、活用実績として文書化することが欠かせません。
継続のコツ:小さく始める・スケジュール管理・仲間づくり
リスキリングを成功させるために大切なのは、「継続すること」です。しかし、最初から完璧を求めすぎると挫折につながりやすいため、まずは小さな一歩から始めることが継続の鍵になります。たとえば、毎日15分だけ学習する、週1回だけ副業案件を探すといった“無理のない目標設定”からスタートするのが効果的です。
また、自分で学び続けるためにはスケジュール管理が欠かせません。手帳やアプリを使って日々の学習・作業時間を見える化することで、モチベーションの維持と進捗の確認がしやすくなります。SHElikesのような学習サービスでは、受講スケジュールをオンラインで管理できる仕組みがあり、日々の学びを習慣化する工夫がされています。
さらに、孤独を感じずに学び続けるためには「仲間づくり」も大切です。オンライン講座や支援機関では、グループワークや交流会を通じて、同じ目標を持つ仲間とつながることができます。たとえば、manabyでは支援員との定期的な面談に加えて、利用者同士が学習内容や悩みを共有できる時間があり、継続のモチベーションを保ちやすくなっています。
「小さく始める」「時間を見える化する」「仲間と学ぶ」──この3つを意識することで、学びは日々の習慣となり、“学びっぱなし”を防ぎながら、実践につなげていくことができます。リスキリングを単なる知識習得で終わらせないために、こうした継続の工夫をぜひ取り入れてみてください。
働きずらさを感じている人におすすめの転職サービス
dodaチャレンジ|ストレスを減らせる環境を一緒に考えてくれる
→dodaチャレンジ アフィリリンクを貼る
関連ページはこちら:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
LITALICOワークス|働く前に心の準備ができる就労支援
→LITALICOワークス アフィリリンクを貼る
関連ページ:LITALICOワークスの口コミと評判|利用者が語るリアルな声と就職支援の実力
ランスタッド|大手だから安心して相談できる環境がある
→ランスタッド アフィリリンクを貼る
atGP|理解ある職場紹介で再出発を後押ししてくれる
→atGP アフィリリンクを貼る
ミラトレ|小さな練習から始められる就労移行支援サービス
→ミラトレ アフィリリンクを貼る
関連ページ:ミラトレの口コミ・評判は本当?通所経験者の声から見えるリアルな実態
【まとめ】リスキリング 支援 サービス|“今さら”じゃなく“今から”始める人が未来を変える
リスキリングは、今や限られた人だけの特別な選択ではなく、誰にとっても「働き方を見直すチャンス」となっています。副業や転職、キャリアの再設計を考える人、または体調や特性に不安を感じながらも「働きたい」と願う人にとって、リスキリングは“学び直し”だけでなく“自分らしさ”を取り戻すための一歩です。そしてその一歩を確かなものにするのが、就労移行支援や支援付き転職サービスといった専門機関の存在です。スキルの取得にとどまらず、職場選びや就職後の定着支援まで一貫してサポートしてくれることで、自信と安心を持って社会へ再び踏み出すことができます。
たとえ「今さら」と思っても、始めた瞬間から「今から」に変わります。実際に、30代・40代・50代と年齢に関係なく多くの方が、支援と学びを組み合わせて新しい働き方を実現しています。重要なのは、自分にとって無理のないペースと、自分を理解してくれる環境を選ぶこと。そして、スキルだけでなく「安心して続けられる職場」と出会うことが、本当の意味でのキャリア再スタートにつながります。これからの時代を前向きに生きるために、“今から”リスキリングを始めることは、きっと未来を変える力になるはずです。
関連ページはこちら
特性に合った学び直しをしたい方へ
発達障害支援サービスと連携したスキル習得の方法を解説しています。
→関連ページはこちら【発達障害と就職】自分らしく働くための支援サービス活用ガイド
副業を見据えたリスキリングをしたい方へ
副業OKな企業一覧と、収益化しやすいスキルの学び方を紹介しています。
→関連ページはこちら「副業 OK 企業 一覧」へ内部リンク
リスキリング費用を支援してもらいたい方へ
対象者・条件・申請の流れをわかりやすく解説しています。
→関連ページはこちら「助成金 対象者 条件」へ内部リンク
就労支援と学びを並行したい方へ
就労移行支援の利用方法と、資格取得・訓練内容を紹介しています。
→関連ページはこちら「就労移行支援 利用 方法」へ内部リンク
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
生活とお金に関するおすすめ情報まとめ(ドメイントップページ)を見る
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」も参考になります

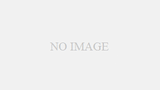
コメント