「自分が悪いのかも」と思っていた過去の私へ。パワハラからの転職で見つけた“心が安定する職場”の探し方
かつて、職場での日々が苦しみの連続だった私にとって、「自分が悪いのかもしれない」と感じる瞬間は幾度もありました。上司の顔色をうかがい、叱責されないよう必死に立ち回る毎日。けれど、それでも繰り返されるパワハラに、次第に自分を責めるようになり、心がすり減っていったのです。そんな私がようやく見つけたのは、「安心して働ける場所」の存在でした。心の健康を取り戻しながら働ける環境は、決して特別なものではありません。この記事では、パワハラから脱出し、心が安定する職場と出会えた体験をもとに、その見つけ方や考え方、就労移行支援サービスの活用方法についてご紹介します。同じように悩んでいる方が、少しでも前に進めるヒントになりますようにと思いを込めて、お伝えします。
上司の怒鳴り声が当たり前だった職場。気づいたらメンタルが崩れていた
働くうえで上司との関係は避けて通れないものですが、日常的に怒鳴り声や無視が繰り返される職場にいると、自分の存在意義まで見失ってしまいます。私の前職では、些細なミスに対して激しい叱責が飛び交い、会議中に吊し上げられることも日常茶飯事でした。最初は「自分がもっと努力すれば」と思い込もうとしていましたが、ある日突然、体が動かなくなり、診断結果は「適応障害」でした。会社に行こうとすると吐き気が止まらず、電車にも乗れない。心身ともに限界を迎えていたのです。この経験を通して気づいたのは、環境が自分を壊しているという事実でした。職場は本来、安心して働ける場所であるべきです。自分を責めるのではなく、環境を見直す勇気が必要なのだと、ようやく理解できた瞬間でした。
叱責、無視、孤立…パワハラの連続で日々が苦しくなっていった
パワハラは目に見える暴力だけではありません。無視されること、理不尽に責められること、会話を断たれることも立派なハラスメントです。私の場合、上司からの無視が始まったことで、職場内での孤立が進みました。報連相をしても返事がない、質問してもにらまれるだけ。そんな中でミスが起きれば、「なぜ確認しなかったのか」とさらに責められます。周囲もその空気に沈黙し、誰も助けてくれない。孤独と恐怖の中で働き続ける日々は、精神的に追い詰められるばかりでした。職場で孤立しながら、なおかつ成果を求められるという状況は、非常に過酷です。このような環境が続くと、自尊心が削られ、「自分がダメだからだ」と思い込むようになります。まさに悪循環でした。
パワハラによる苦しさが積み重なった日々の内訳
朝起きた瞬間から胃が痛み、出勤前には涙が出る。職場に着いても、無表情な同僚や冷たい上司の視線が怖くてトイレに隠れる。昼食も一人で食べ、午後の時間はただ「怒られないように」と怯えながら過ごす。そして退勤後も「明日もまた怒られるのではないか」と不安に押し潰される夜を迎える。これが、パワハラが続いていた頃の私の一日でした。このような状態が何ヶ月も続くと、心の疲れは限界に達します。やがて「もう働くこと自体が怖い」と思うようになり、転職すら考えられなくなるのです。ですが、実際には「逃げてもいい」し、「助けを求めていい」状況だったと今では思います。就労移行支援サービスの存在を知ったことが、私にとっての転機になりました。
次回は、どのようにして「安心して働ける職場」に出会えたのか、そしてその探し方の具体例について、キズキビジネスカレッジやココルポート、ミラトレといった支援サービスの情報も交えてご紹介していきます。
| 状況 | 上司・同僚の行動 | 自分の反応・感情 | 体への影響 | 気づいたこと |
| 毎朝の始業前 | 「声が小さい」「やる気あるの?」と詰められる | 頭が真っ白になる/声が出なくなる | 頭痛・動悸/通勤がつらい | 朝の通勤が“恐怖”になっていた |
| 業務中 | 曖昧な指示のあとに「何でできないの?」 | 自分を責め続ける/萎縮 | 集中できずミスが増加 | “失敗して当然”の空気に飲まれていた |
| 昼休み | 話しかけても無視される/独りぼっち | 存在を否定されているような感覚 | 食欲不振/無言の食事 | 無視されるだけでこんなに傷つくとは思わなかった |
「職場に行く=吐き気がする」状態でも、誰にも相談できなかった
パワハラが続いたある時期から、朝の出勤時間が近づくたびに吐き気に襲われるようになりました。起き上がろうとしても胃がキリキリと痛み、布団から出ることすら億劫に感じる日々。病院では「自律神経の乱れ」と診断されましたが、当時の私はそれすらも「自分の弱さが原因なのでは」と責めていました。本当は誰かに相談したかったけれど、職場の人には言い出せず、家族にも心配をかけたくなくて何も話せないまま、ただ時間だけが過ぎていきました。メンタルが追い込まれる中で、「会社に迷惑をかけたくない」「自分さえ我慢すれば」と、さらに自分を縛ってしまう悪循環。限界を感じながらも声をあげられなかった自分に、今だからこそ「逃げてもいい」と言ってあげたいのです。
「辞める=負け」じゃなかった。自分を守るための転職という選択
「仕事を辞める」という選択は、かつての私にとって「逃げ」や「負け」のように感じていました。どれだけ辛くても耐えなければならない、我慢が美徳であるという空気に影響されて、心身の不調を無視して働き続けていたのです。しかし、実際に限界を超えてしまったとき、ようやく気づきました。大切なのは、仕事を続けることではなく、「自分を守ること」だったのです。辞めることで得られたのは、安心して呼吸できる毎日と、心の余裕でした。そしてそこから、自分らしい働き方を模索する転職活動が始まります。今の時代、働き方は多様であり、適応障害やパワハラを経験した人のための支援制度やサービスも整いつつあります。辞めることは、決して後ろ向きな選択ではなく、新しい人生を切り開くための一歩なのです。
退職の決意と同時に考えた“逃げた後どうする?”という不安
退職を決めた瞬間、重荷が取れたような感覚と同時に、将来への大きな不安が押し寄せました。仕事を辞めてしまったら収入はどうなるのか、再就職できるのか、同じような職場だったらどうしようという思いが頭をよぎります。特にパワハラを経験していると、自信を失ってしまい、面接でうまく話せる自信すらなくなってしまいます。そうした不安をひとりで抱えていた私にとって、転機となったのが就労移行支援サービスの存在でした。キズキビジネスカレッジのように、発達障害やうつの経験があるスタッフが相談に乗ってくれる環境は、まさに「安心できる場所」でした。プロの支援を受けながら、焦らずにスキルを身につけ、心を整えていくプロセスは、ただの「再就職」ではなく、「再スタート」に近いものでした。
退職の決意から「この先どうすれば…」と悩んだ不安の整理
退職した後に待っていたのは、想像以上に深い不安でした。これまでのように毎日通勤することもなくなり、社会とのつながりが急に消えてしまったような感覚に陥りました。貯金の残高ばかりが気になり、「このままで大丈夫なのか」という焦燥感に駆られる日々。しかし、そんな時に就労移行支援の無料相談を受けたことで、少しずつ気持ちが整理されていきました。例えば、ココルポートでは生活リズムを整えるプログラムや自己分析のサポートがあり、自分の強みと向き合い直す時間が持てました。また、ミラトレでは実際の職場を模した疑似就労環境での訓練があり、社会復帰への不安が徐々に和らいでいきました。支援を受けることで、「この先どうすれば」と悩んでいた気持ちが「次はこうしてみよう」という前向きな思考へと変わっていったのです。
| 不安の内容 | 実際に起きたこと | 乗り越え方 | 心の変化 |
| お金がなくなるかも | 収入が途絶え生活が不安に | 傷病手当金を申請/支援制度を調べた | 「すぐ働かなくても大丈夫」と思えた |
| 履歴書が空白になる? | 「1ヶ月何してた?」と聞かれるかも | 回復期間として正直に話す準備をした | “正直に話していい”と思えるように |
| 社会から取り残される | 働いてない自分を責めそう | SNS・支援員との交流で外との繋がり継続 | 「一人じゃない」安心感があった |
傷病手当金を活用して、まずは心のリカバリーに集中
退職に至るまでの過程で心身の不調が限界を迎えていた私は、医師の診断を受け、「適応障害」と診断されました。その際に教えてもらったのが「傷病手当金」の存在です。これは、健康保険に加入していた被雇用者が病気やけがで働けなくなった際、最長1年6ヶ月にわたり支給される生活保障の制度です。この制度を活用することで、焦って働き口を探すことなく、まずは自分の心身の回復に集中できました。経済的な不安が軽減されることで、「今は休む時期だ」と自分に言い聞かせることができ、リカバリーの第一歩が踏み出せたのです。通院しながらゆっくりと休養を取り、無理のないペースで日常を整えていく中で、「もう一度働きたい」と思えるようになっていきました。傷病手当金は、心が回復するまでの貴重な“猶予期間”となったのです。
「働ける場所は他にもある」―それを実感できた出来事
心のリカバリー期間中に、ふとしたきっかけで参加した就労支援事業所の見学会。それが私の意識を大きく変える出来事となりました。キズキビジネスカレッジでは、精神的な不調や発達障害などに理解があるスタッフが迎えてくれ、初対面なのに「あなたのままで大丈夫ですよ」と言ってくれた言葉が胸に残っています。また、ココルポートのように生活リズムの整え方から社会復帰へのプロセスを丁寧に設計してくれる支援機関では、再就職を焦らずに考えられる環境が整っていました。そうした場所で同じように苦しんできた人たちと出会い、自分だけが特別につらかったわけではないと知ることができたのです。「あの職場がすべてではなかった」「私に合う場所は他にもある」―そう実感できたことで、未来への選択肢がぐっと広がりました。
「自分を受け入れてくれる職場はある」と実感できた瞬間
支援を受けながら就職活動を進めていく中で、ある企業との面接で「あなたのこれまでの経験も、きっと強みになりますよ」と言われた時、思わず涙がこぼれました。パワハラの経験、休職したこと、傷ついた心。それらはずっと「隠さなければいけない過去」だと思っていたのに、それを包み隠さず話しても、否定されるどころか肯定されたのです。その企業は、障がい者雇用に積極的に取り組んでおり、メンタル面のサポート体制も整っていました。実際に就職した後も、定期的な面談や相談の場があり、「無理をしない働き方」が可能でした。このような環境があることを実際に体感し、「自分を受け入れてくれる職場は確かに存在する」と確信できた瞬間でした。ミラトレやatGPなどの支援機関でも、同様の企業との橋渡しを行ってくれる体制が整っており、一人では見つけられなかった道を一緒に歩んでくれる心強さがありました。
| 出会った出来事 | 相手の対応 | そのときの気持ち | 行動につながった変化 |
| 就労支援の初回面談 | 「ゆっくりでいいですよ」と話を聴いてくれた | 涙が止まらなかった/安心した | 通う決意ができた/通院も続けられた |
| 面接で配慮を伝えたら | 「では、その配慮を前提に考えますね」と即答 | 初めて“否定されなかった”感覚 | “この会社に行ってみよう”と思えた |
| 支援員のひとこと | 「逃げたんじゃなくて、自分を守っただけ」 | 否定感がスッと抜けた | 転職活動への罪悪感が減った |
転職活動で見えた“心が安定する職場”の条件とは
退職後、心と体を整えながら少しずつ始めた転職活動の中で、私は「心が安定する職場」にはいくつかの共通点があることに気づきました。単に業務内容や給与の条件が良いというだけでは、本当の安心にはつながりませんでした。むしろ、過去の職場のような人間関係のストレスや過度なプレッシャーがないかどうか、自分の存在が尊重されているか、安心して働ける環境が整っているかという点が、最も大切な基準になっていったのです。就労移行支援サービスを通じて紹介された企業の中には、働く人の心を守ることを第一に考えている会社も多く、「職場選びは、自分を大切にする行動」だと強く実感しました。この記事では、私が転職活動を通して見えてきた“心が安定する職場”の具体的な条件について、順にお伝えしていきます。
① 人を責める文化がない職場
転職活動を続けるなかで、最も重要だと感じたのは「人を責める文化がない」ことです。どんな職場でもミスは起こります。しかし、その時に“誰が悪いか”を追及する空気があるかどうかで、職場の雰囲気は大きく変わります。以前の職場では、ミスがあるたびに責任の所在を明確にすることに時間が費やされ、誰かが吊し上げられることで他の社員も萎縮していました。一方で、良い職場ではミスを個人の責任とせず、「どうすれば同じことが起きないか」をチームで考える風土がありました。そうした文化があると、「自分もここにいていい」と思えるようになり、自然とパフォーマンスも安定していきました。人を責めない環境は、心の回復にも、成長にも欠かせない要素だと感じています。
人を責める文化がない職場に共通する特徴
人を責めない職場には、いくつかの明確な共通点があります。まず第一に、「相談しやすい雰囲気」があること。困ったことや不安を抱えていても、気軽に話せる上司や同僚がいることで、問題を早期に共有・解決できます。次に、「フィードバックが建設的であること」も重要です。感情的な叱責ではなく、「次にどうしたら良いか」を一緒に考える文化があることで、ミスや失敗を学びに変えることができます。また、「個々の違いを受け入れる多様性」が浸透している職場では、価値観の押し付けが少なく、社員一人ひとりが安心して自分らしく働けます。ココルポートやミラトレなどの支援機関から紹介された企業の中には、このような文化が根付いた職場が多く、長期的に安心して働ける環境であることが伺えました。こうした特徴を見極めることが、「心が安定する職場」を見つける大きな鍵になるのです。
| 特徴 | 具体例 | なぜ大切か | 見極めるポイント |
| ミスの捉え方 | 「原因を一緒に探そう」と言ってくれる | 個人責任ではなくプロセス改善 | 面接時のトラブル質問に対する答え |
| フィードバックの質 | 改善点と一緒に「できた点」も伝えてくれる | 自信を失わず次に活かせる | 話し方が感情的でないかを確認 |
| 空気感 | ミスしても周囲がピリつかない | 萎縮しなくていい環境 | 職場見学時の雰囲気・表情を見る |
面接で「この会社は人をどう扱うか」が伝わってくる
転職活動において面接は、単に自分をアピールする場ではなく、企業の本質を見抜く重要な機会でもあります。特に「この会社は人をどう扱うか」という点は、面接時の雰囲気ややり取りの中に表れやすいものです。たとえば、面接官の言葉づかいや質問の仕方に、相手への敬意があるかどうか、否定的な口調や圧迫感がないか、といった点に注意を向けると、その企業の人間関係の在り方や組織風土が見えてきます。私自身の経験でも、ある企業では話をさえぎられることなく、こちらの考えにじっくり耳を傾けてくれました。その時点で「この会社では、自分が一人の人間としてきちんと扱われる」と直感しました。また、就労移行支援を通じて出会った企業は、ほとんどが「障がいへの理解」や「対話を重視する文化」を持っており、面接の段階から安心感を覚えることができたのです。企業の本質は、面接時の何気ない対応にこそ表れるのだと思います。
② 無理のないコミュニケーションの距離感
心の安定を保ちながら長く働き続けるためには、「人間関係の密度」が重要なカギになります。たとえば、毎日プライベートなことを深く聞かれたり、雑談や飲み会への参加を強要されたりするような環境では、気を遣いすぎて心が疲弊してしまいます。一方で、まったく関わりがなく孤立するような職場も、安心して働けるとは言えません。理想的なのは、「必要な時に協力できて、無理のない範囲で関われる」関係性が保たれている職場です。私が支援を受けたミラトレでも、グループワークと個別作業のバランスがうまく取られていて、自分のペースで他者と関わる練習ができました。また、manabyのように完全在宅訓練に対応しながらも、支援員とのオンライン面談で適度なつながりが持てる仕組みもあります。このように、自分の状態や性格に応じて距離感を調整できる職場は、非常に心が落ち着く場所となります。
無理のないコミュニケーションの距離感がある職場の特徴
無理のないコミュニケーションの距離感がある職場には、まず「強制」がないという特徴があります。たとえば、業務以外の交流は自由参加であったり、上司が部下との距離を適切に保っていたりする職場では、人間関係に過度なストレスを感じることが少ないと感じました。また、報連相(報告・連絡・相談)が一方通行ではなく、双方向で行われている環境も大きなポイントです。意見を求められる場がありながらも、それを無理に発言させないというバランス感覚が保たれていることが大切です。就労支援の現場では、キズキビジネスカレッジのグループワークがちょうどよい距離感で構成されており、最初は苦手意識があった私でも徐々に会話に加われるようになりました。このような経験を通して、「関係を築くペースは人それぞれでいい」と受け止めてくれる職場こそが、心を安定させる大きな要素であると実感しました。
| 要素 | 良い例 | ストレスの少なさ | チェック方法 |
| 雑談の頻度 | 必要なときだけで、無理に合わせない | 無理な会話ストレスがない | 「昼休みの過ごし方」などを質問 |
| チャット・メールの文化 | 文面が丁寧で、返信に余裕がある | 即レス圧力がない | 社内のやりとりがどう進むか確認 |
| 報連相のルール | 決まったタイミングでOK | 常に気を張る必要がない | 面接時に業務の流れを聞いておく |
雑談の少なさが“楽”だと気づいた
以前の職場では、業務の合間に無理に雑談を求められることが多く、気を遣いながら会話を続けることにストレスを感じていました。相手の機嫌を損ねないよう話題を選び、会話の空気を読んで笑うことが、いつの間にか日常となっていたのです。しかし、就労移行支援事業所での訓練や、いくつかの企業の見学を通して、「雑談が少ない環境=冷たい」わけではないと知りました。むしろ、必要なコミュニケーションが端的に行われる職場は、非常に居心地がよく、仕事に集中しやすい空間でした。特にmanabyのように、在宅での訓練や業務が中心となる環境では、過度な雑談が発生せず、自分のペースで業務を進めることが可能でした。他者との関わりが煩わしいわけではなく、「気を遣いすぎない距離感」が心の安定に直結するのだと、改めて感じるようになりました。雑談の有無よりも、互いに尊重しあえる関係性こそが、働きやすさの本質だと気づかされたのです。
③ 勤務時間や働き方が柔軟に選べる
心身の状態に波がある人にとって、柔軟な勤務時間や働き方は非常に大きな支えになります。毎日決まった時間に出勤することが難しい時期でも、「午前中だけ」「週に数日だけ」といった選択肢があれば、無理なく社会とつながり続けることができます。また、在宅勤務のように通勤の負担がない働き方は、精神的にも身体的にも余裕が生まれやすく、安心感を得やすいと感じました。私が見学した中では、ミラトレの支援プログラムが段階的な就労復帰を想定した構成になっており、最初は短時間からスタートして、徐々にフルタイム勤務を目指す設計になっていました。また、atGPジョブトレでは、個別に応じた働き方の提案をしてくれるため、無理のない復帰が実現可能となっていました。働くことに対するハードルが下がると、心にも余裕が生まれ、自信を取り戻すきっかけにもつながります。
柔軟な働き方ができる職場が与えてくれる安心
柔軟な働き方ができる職場には、単に「制度がある」だけではなく、それを利用しやすい空気があることが重要です。制度が整っていても、「周囲が使っていないから遠慮してしまう」「時短勤務に罪悪感を覚える」という環境では、本当の意味での安心は得られません。一方で、「無理せず、できる範囲で」と自然に言ってもらえる職場では、気持ちがほぐれ、自分の体調やペースを優先しながら働くことができます。特に在宅勤務や時差出勤を取り入れている企業では、自分の生活リズムに合わせて業務に取り組むことができ、心身のコンディションを整えやすい環境が整っています。就労移行支援事業所でも、そうした働き方を想定した訓練プログラムが組まれており、たとえばmanabyではオンラインを活用した自宅訓練の中で、自律的に仕事を進める力を養うことができます。このような柔軟性がある職場は、長期的に働き続ける上での大きな安心材料となります。
| 項目 | 対応例 | 向いているタイプ | 気持ちの変化 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制・時短勤務可 | 朝が苦手/通院がある人 | 「出勤が怖い」がなくなる |
| 勤務日数 | 週3〜から相談可能 | 体力に波がある人 | 負担を感じず働ける |
| 勤務場所 | 在宅OK/通所と併用可 | 感覚過敏/通勤困難な人 | 「このまま続けられる」と思える |
フルタイムじゃなくていい。それだけで気持ちが軽くなる
パワハラを受けていた頃の私は、「働くならフルタイムでなければいけない」という思い込みに縛られていました。しかし、心身が限界を迎えた後、就労移行支援を通じて知ったのは、働き方にはもっと多くの選択肢があるということでした。たとえば、午前中だけの勤務や週3日から始める働き方でも、社会とつながり、生活のリズムを取り戻していくことが可能です。支援先のmanabyでは、訓練プログラムも完全在宅で無理のないスケジュールが組まれており、体調に合わせて学習や作業を進めることができました。また、ミラトレやatGPジョブトレでも、段階的な就労復帰に対応した訓練カリキュラムが用意されており、少しずつ「働く感覚」を取り戻していける設計になっています。フルタイムに戻ることを急がなくてもいいと知るだけで、心の負担は大きく軽減されました。「自分のペースで働く」ことが許される環境は、心のリカバリーにとって何よりの安心材料となります。
パワハラのトラウマを乗り越えて働けるようになった体験談
パワハラの被害を受けて心が壊れた経験は、想像以上に深く傷を残しました。「また同じことが起きるのではないか」「自分は働くことに向いていないのでは」といった思いが頭から離れず、新しい環境に踏み出す勇気すら持てなかったのです。ですが、就労移行支援を通じて出会った安心できる人たち、そして、無理なくステップを踏めるサポート体制のおかげで、少しずつ前を向けるようになりました。初めて「怒られない」「否定されない」環境で過ごす時間は、それだけで心を癒してくれました。新しい職場に入社したときも、はじめのうちは不安でいっぱいでしたが、少しずつ、少しずつ、自分の居場所があることを実感できるようになっていきました。今では、以前よりも落ち着いて働けており、「あの時、逃げてよかった」と心から思えるようになりました。
理解ある上司との出会いで「もう怒られない」安心感を得た
新しい職場で最も心に残っているのは、上司が最初にかけてくれた「困ったことがあったら、無理せず相談してね」という言葉です。それまで私は、上司という存在に対して「怒る人」「責める人」という印象しか持てていませんでした。けれども、この職場では、業務で分からないことがあっても、まず丁寧に聞いてくれ、「大丈夫、徐々に覚えていけばいいよ」と声をかけてもらえました。そのたびに、「ああ、ここでは自分を守らなくていいんだ」と感じることができ、心がほっとしたのを覚えています。理解のある上司との出会いは、過去のトラウマを少しずつ癒してくれました。ミラトレやキズキビジネスカレッジなどの支援機関では、企業側にも障がいへの理解があるところを選んで紹介してくれるため、安心して働き始めることができたのです。
理解ある上司との出会いがくれた“安心”の正体
その上司との関係の中で私が得た“安心”の正体は、「自分の感情を否定されない場所にいる」という実感でした。以前の職場では、少しでも弱音を吐けば「甘えるな」と突き放され、相談しても「そんなことで?」と返されるのが常でした。しかし、新しい職場では、気持ちを口にすること自体が受け入れられ、共感してもらえる経験を重ねることができました。上司だけでなく、同僚もまた「お互いさま」の精神で関わってくれたことで、人間関係への恐怖心が少しずつほどけていきました。心が安心していると、自然と仕事にも集中でき、自信も取り戻せるようになります。この“安心”は、制度や待遇では測れない、職場の人間関係から生まれるものだと痛感しました。そしてそれは、就労移行支援機関が企業と丁寧にマッチングしてくれたからこそ、実現できたのだと思っています。
| シーン | 上司の対応 | 自分の気持ちの変化 | 長期定着につながった理由 |
| 体調が悪い日 | 「無理しないで」と一言 | “怒られない”だけでホッとした | 自分を責めなくなった |
| 報告の仕方を間違えたとき | 「次はこうしてみよう」と提案 | 責められない安心感 | 成長意欲が戻ってきた |
| 週末の予定に合わせた調整希望 | 快くOK/日程再調整 | 信頼されている感じがした | 相手の期待に応えたくなった |
「今の自分でもできること」に集中することで、少しずつ自信が戻ってきた
パワハラの影響で心が折れてしまった私は、自分に対する自信をすっかり失っていました。「また怒られたらどうしよう」「仕事でミスをしたら、見捨てられるかもしれない」といった不安が常につきまとい、就職活動すら怖くて手をつけられない日々が続きました。そんな私にとって、就労移行支援サービスは“リハビリ”のような存在でした。無理に「完璧な社会人」を目指すのではなく、「今の自分ができること」に集中するという姿勢が、少しずつ自信を取り戻すきっかけになったのです。
| ステップ | 実際にやったこと | 得られた感覚 | 自分に起きた変化 |
| ステップ1 | 軽作業・1日3時間勤務から始めた | 「無理なくできる」感覚 | 成功体験が少しずつ増えた |
| ステップ2 | チェック作業などの単独作業 | 評価される実感 | 自己否定感が減った |
| ステップ3 | 課題があれば支援員と相談 | 解決の道筋が見えた | “対処できる”という安心感が生まれた |
働きずらさを感じている人におすすめの転職サービス
dodaチャレンジ|ストレスを減らせる環境を一緒に考えてくれる
→dodaチャレンジ アフィリリンクを貼る
関連ページはこちら:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
LITALICOワークス|働く前に心の準備ができる就労支援
→LITALICOワークス アフィリリンクを貼る
ランスタッド|大手だから安心して相談できる環境がある
→ランスタッド アフィリリンクを貼る
atGP|理解ある職場紹介で再出発を後押ししてくれる
→atGP アフィリリンクを貼る
ミラトレ|小さな練習から始められる就労移行支援サービス
→ミラトレ アフィリリンクを貼る
【まとめ】パワハラ 転職 体験談|「あの職場がすべてじゃない」と気づけたことが回復の第一歩でした
パワハラによって心が壊れ、「自分が悪いのでは」と思い詰めていた過去の私にとって、転職という選択は逃げではなく「自分を守るための大切な行動」でした。怒鳴られ、無視され、孤立し続けた職場の日々は、心の傷となって残りましたが、そこから一歩踏み出して環境を変えることで、少しずつではありますが心が回復していきました。就労移行支援サービスを通じて、「理解ある人たちがいる」「無理なく働ける場所がある」と知ることができたのは、私にとって大きな転機でした。
面接や企業見学の中で「人を大切にする文化」や「無理のない距離感」を感じられる職場に出会えたことで、再び働く勇気が湧いてきました。また、「フルタイムでなくていい」「在宅でも大丈夫」という柔軟な働き方の選択肢があることも、心の負担を大きく和らげてくれました。何より、「今の自分にできること」を認めてくれる環境に身を置くことで、自分の存在価値を再確認することができました。
かつての私と同じように、苦しい状況にいる方へ伝えたいのは、「あの職場がすべてではない」ということです。働く場所は他にもありますし、支えてくれる人も必ずいます。少し勇気を出して環境を変えることで、見える世界はきっと変わっていきます。自分を守る選択をしたその先に、新しい未来はきっと待っています。
関連ページはこちら
同じように苦しんでいる方へ、今できる対処法を紹介
職場のいじめを受けている人が取れる具体的な対策をまとめています。
→関連ページはこちら【保存版】職場いじめの対処方法|我慢しないための行動ステップと、次の環境を見つけるコツ
上司との関係に悩んだら読んでほしい
距離感・対処法・相談の仕方について紹介しています。
→関連ページはこちら【限界を感じる前に】上司との関係にストレスを感じたときの対処法|逃げずに自分を守る方法
退職すべきか迷ったら、この記事を
メンタルが限界に近づいたときの判断軸を体験談ベースで解説しています。
→関連ページはこちら【体験談】メンタル不調で退職を選んだ理由と、限界の中で見つけた再出発の道
生活費の不安がある人へ
退職後も支援を受けながら次の一歩に進む方法を解説しています。
→関連ページはこちら「傷病手当金 申請 方法」へ内部リンク
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
生活とお金に関するおすすめ情報まとめ(ドメイントップページ)を見る
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
厚生労働省「こころの健康」ページも参考になります

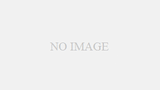
コメント