「働きたいけど、自信がない…」発達障害と向き合いながら、自分に合った働き方を見つけた話
「働きたい気持ちはあるけれど、自信がない」――これは、発達障害を抱える多くの方が感じている率直な想いです。周囲の人と同じように働こうとしてもうまくいかず、自己否定を重ねてしまう経験を持つ方も少なくありません。特に、職場でのコミュニケーションや複数作業の同時進行など、見えにくい部分での困難に直面すると、「自分は社会でやっていけるのだろうか」と不安になってしまうものです。そんな中でも、自分に合った環境や支援を受けながら、一歩ずつ前に進んでいる方がいます。例えば、就労移行支援事業所「manaby」では、自分のペースでスキルを学び、個別に対応してもらえる訓練スタイルによって、自信を取り戻しながら就職につなげている利用者が多くいます。この記事では、発達障害と向き合いながらも、自分に合った働き方を見つけていく過程を紹介します。同じように悩む方にとって、きっと参考になるはずです。
なぜ“普通の転職”がうまくいかなかったのか?
「転職してもすぐに辞めてしまう」「面接でいつも落ちる」――こうした経験は、単なるスキル不足ではなく、自分の特性と職場の環境が合っていないことが原因かもしれません。発達障害のある方の場合、対人関係や環境の変化に敏感であることが多く、慣れるまでに時間がかかったり、周囲とのペースの違いに苦しむことがあります。一般の求人では、こうした特性に対する理解や配慮が不十分な場合も多く、結果として「仕事が続かない」「評価されない」といった悪循環に陥ることもあります。特に「空気を読む力」や「臨機応変な対応」が重視される場面では、発達障害の方にとって大きな壁となることがあります。こうした経験が積み重なると、ますます自己肯定感を失い、働くこと自体が怖くなってしまうこともあるのです。自分に合った職場を見つけるには、特性を理解し、配慮のある環境であることが重要になります。
面接で緊張しすぎる、職場で空気が読めない…自分の特性に合っていなかった
発達障害のある方にとって、一般の面接や職場環境は想像以上に負担が大きいものです。面接では質問の意図がつかめず、答えに詰まってしまったり、想定外の質問にパニックになってしまうこともあります。また、職場では上司や同僚とのあいまいなコミュニケーションに困り、注意されることが重なって、居場所がないと感じてしまうことも多いです。これは能力の問題ではなく、環境や文化が合っていないだけなのです。たとえばmanabyで学んだある利用者は、以前は職場で孤立しがちでしたが、個別訓練の中で自分に合った働き方や強みを見つけたことで、今はIT系業務で活躍しています。このように、自分の特性を正しく理解し、それに合った働き方を模索することで、大きく環境は変えられるのです。
特性に合わなかった職場で感じたギャップとその理由
発達障害のある方が「働きづらさ」を感じる職場には、いくつかの共通点があります。例えば、業務の指示が口頭だけで曖昧だったり、突然の変更が多かったりする職場では、混乱しやすくなります。また、評価基準が不明確だったり、感情で判断される場面が多いと、自信を失いやすくなる傾向があります。こうした環境は、情報の受け取りや処理が独特な発達障害の方にとって、大きなストレス源となりえます。一方で、manabyやココルポートのような就労移行支援では、こうしたギャップを埋めるために、事前に業務内容や職場の雰囲気を丁寧に説明し、必要に応じて配慮事項を企業側と調整してくれる体制が整っています。特性に合っていない職場に無理に適応しようとするよりも、自分にとって無理のない環境を選ぶことが、長く安定して働くための鍵となります。
| 状況 | 困ったこと | 職場の反応 | 自分の気持ち | 学んだこと |
| 面接 | 質問が頭に入らず答えが飛ぶ | 「緊張しすぎだね」と言われた | 自信を失った | 面接対策は“想定外”にも慣れが必要 |
| 業務中 | 曖昧な指示が理解できない | 「空気読んで」と言われた | 自分だけがズレてるように感じた | 明確な指示・可視化が必要 |
| 休憩中 | 雑談ができない/話が読めない | 「ノリが悪い」と言われた | 孤立感を覚えた | 無理に会話を合わせる必要はない |
“がんばる”ではなく、“工夫する”働き方を知ることが大切だった
「もっと頑張らなければ」「迷惑をかけたくないから人一倍努力しよう」と思って無理を重ねてしまうのは、発達障害のある方にとってよくあることです。しかし、頑張り続けるだけでは体調を崩してしまったり、精神的に追い詰められたりすることも少なくありません。本当に大切なのは、自分の特性に合わせて“工夫して働く”という視点を持つことです。たとえば、メモを活用して指示を視覚化したり、作業工程をあらかじめパターン化しておいたり、環境を整えることでパフォーマンスが安定することがあります。こうした工夫は、自分を責めることなく、安定して働くための重要なスキルでもあります。ミラトレでは、このような「自分に合った工夫」を一緒に見つける個別支援があり、働くことに前向きになれるきっかけを与えてくれます。頑張るだけではなく、無理のない範囲で成果を出せる工夫を知ることで、働くことが苦痛から「生活の一部」へと変わっていくのです。
支援サービスと出会って、「働き方を選べる」ということを知った
多くの人が「働くとは我慢すること」「与えられた仕事に合わせること」と考えてしまいがちですが、就労支援サービスと出会うことで、「働き方にも選択肢がある」ことに気づけたという声は少なくありません。特に発達障害や精神障害のある方にとっては、生活リズムや人間関係に無理のない働き方を見つけることが、就労の継続には欠かせません。支援サービスでは、自己理解を深めた上で、自分に向いている職種や業種を一緒に探し、必要なスキルの習得もサポートしてくれます。たとえば、atGPジョブトレでは障害別に専門のコースが用意されており、それぞれの特性に合ったトレーニングを受けられます。支援を通じて、「自分にはこんな働き方が向いているんだ」「職場に合わせるだけでなく、自分も選んでいいんだ」と気づくことで、就職活動そのものに対する意識が変わり、自信にもつながっていきます。
支援サービスとの出会いで変わった「働き方」への認識
支援サービスと出会う前は、「働くこと=苦しいもの」「自分の障害では続けられない」といったネガティブな印象を抱いていた方も多いのではないでしょうか。しかし、実際に支援サービスを利用することで、その認識が大きく変わったというケースは多くあります。たとえば、キズキビジネスカレッジでは「もう一度働きたい」という気持ちを応援し、ビジネススキルと同時にセルフケアや人間関係の築き方も学べるようになっています。また、ココルポートでは体調管理や通院配慮を含めた「長く働き続ける」ことを見据えた支援が行われており、支援員との信頼関係の中で安心感を持って就職活動に臨めます。こうした支援を受ける中で、「働くことはつらいだけではなく、工夫や支援があれば自分にもできる」「苦手を補う手段がある」といった前向きな認識が育っていきます。職場でのつまずきや不安を乗り越え、より良い選択をしていくためには、こうした「働き方そのものを見直す」経験が非常に重要なのです。
| 出会う前の考え | 支援との出会い | 気づいたこと | 行動の変化 | 気持ちの変化 |
| 「働く=我慢」 | 無理せず話せるスタッフと面談 | “選べる”ことが前提の支援がある | 条件を整理して就活スタート | 「働けるかも」と思えた |
| 「どこでもいいから早く決めないと」 | 自分の特性に合う求人を提案された | 焦らなくても良いと気づいた | 面接前に職場見学を希望 | 自分に合ったスピードでOKと納得 |
| 「配慮を求めたら落ちる」 | 配慮前提の求人があることを知った | 伝えていい・交渉していい | 苦手なことを整理し自己開示 | 自分を責めずに話せるように |
相談できる人がいるだけで、こんなに心が軽くなるとは思わなかった
発達障害のある方にとって、「誰かに相談できる環境があるかどうか」は、働き続ける上で非常に大きな意味を持ちます。これまで孤独に悩みを抱え込み、誰にも本音を言えなかったという方も、就労移行支援の現場で「安心して話せる相手」と出会うことで、気持ちが大きく変わることがあります。キズキビジネスカレッジでは、利用者一人ひとりに寄り添った面談を重ねることで、「もう一度社会に出たい」という気持ちを少しずつ引き出していきます。また、ミラトレでは支援員が個別に計画を立て、悩みや体調の変化を丁寧に受け止めながら伴走してくれます。一人で悩み続けるのではなく、「話せる場所がある」「味方がいる」と実感できることで、自然と前向きな気持ちになり、行動にも変化が生まれます。支援者との関係は、単なる就職支援にとどまらず、自分の人生を立て直す大きな支えとなるのです。
発達障害に特化した支援サービスの種類と特徴
発達障害のある方に向けた支援サービスは、就労を目指すものから生活の安定や社会参加を支えるものまで、さまざまな種類があります。その中でも特に注目されているのが「就労移行支援」です。これは、働いた経験が少ない、もしくは職場での不安が大きい方を対象に、仕事への準備から実際の定着支援までを一貫して行う福祉サービスです。サービス内容は事業所によって異なりますが、たとえば「atGPジョブトレ」では、発達障害やうつなど障害特性ごとに専門コースを設け、それぞれの課題に応じた支援を実施しています。また、「manaby」では在宅訓練やITスキル習得など、柔軟な学び方が可能となっており、通所が難しい方にも対応しています。このように、支援サービスにはそれぞれ特色があり、自分の特性や状況に合った場所を選ぶことが成功のカギとなります。
就労移行支援|働く準備から職場定着までサポート
就労移行支援は、障害のある方が「働く力」を身につけ、実際の就職までを目指すための福祉サービスです。発達障害のある方にとっては、一般就労に向けた「準備」の段階が特に重要であり、ここでのサポートが就職後の安定にも直結します。たとえば、ココルポートでは生活リズムを整えることから始まり、SST(ソーシャルスキルトレーニング)やビジネスマナー、模擬面接など実践的なカリキュラムが提供されています。加えて、就職後も定着支援として定期面談や職場との橋渡しが行われるため、働き始めてからの不安にも対応できます。また、ミラトレでは一人ひとりに合わせた個別支援計画を立て、体調や性格に応じて無理のない形でステップアップできる仕組みが整っています。このように、就労移行支援は「働くことが不安」「続けられるか心配」という方にとって、安心して一歩を踏み出せる仕組みを提供してくれる重要な制度です。
就労移行支援で経験できる「働く前の準備」一覧
| ステップ | 内容 | 初心者が不安に思うこと | 支援で得られた安心 |
| 生活リズム調整 | 朝起きて毎日通う | 起きられるか不安 | 通うことで体内時計が整った |
| 基本スキル訓練 | メール/電話/報連相 | やったことがない | 一緒に練習できる環境がある |
| 職場体験 | 軽作業や事務作業など | ちゃんと働けるか? | スモールステップで進める |
| 就活サポート | 面接練習/書類添削/求人紹介 | 何を準備すればいい? | マンツーマンで並走してくれる |
生活リズム、ビジネスマナー、職場体験まで段階的に進める
発達障害のある方が就労に向けて準備を進める際には、いきなり働き始めるのではなく、「生活リズムを整える」「ビジネスマナーを学ぶ」「実際の職場を体験する」といった段階を踏むことが非常に重要です。就労移行支援では、こうしたステップを一人ひとりの状態に合わせて進めていく仕組みが整えられています。たとえば、ココルポートでは朝の通所習慣づけや体調管理を支援しながら、基礎的なビジネスマナー研修やSST(ソーシャルスキルトレーニング)などを通して社会性を育てていきます。さらに、実際の企業での職場体験を通して、自分に合った仕事や働き方を見極める機会も提供されており、就職後のミスマッチを減らす効果があります。このように、段階的に就労準備を進めることで、自信をつけながら少しずつ「働くこと」に近づくことができます。焦らず一歩ずつ前に進む環境があることで、就労に対する不安が軽減され、自分のペースで社会復帰を目指すことが可能になります。
特化型支援事業所|発達特性に応じた個別サポートが強み
発達障害のある方が安心して利用できる支援サービスの中でも、特に注目されているのが「特化型支援事業所」です。これは、発達障害やうつ症状、統合失調症など、特定の障害に焦点を当てて支援を行う就労移行支援事業所で、それぞれの障害特性に合わせたプログラムが用意されています。たとえば、atGPジョブトレでは、発達障害コースやうつ症状コースなどが明確に分かれており、それぞれの困りごとに応じた専門的な支援を受けることができます。一般的な支援事業所では幅広い障害に対応しているため、支援内容が画一的になりやすい一方、特化型ではより個別性の高い対応が可能です。たとえば、職場でのコミュニケーションが苦手な人に対しては、対人スキルを重点的にトレーニングしたり、感覚過敏のある方には静かな作業スペースの確保を提案したりと、細かな配慮が行き届きます。このような特化型支援事業所は、障害の特性を深く理解したスタッフと共に「自分らしい働き方」を模索できる場として、多くの利用者に支持されています。
特化型支援事業所のサポートと、一般的支援との違い
特化型支援事業所と一般的な支援との大きな違いは、「専門性」と「個別性」にあります。一般の就労支援事業所では、障害の種類に関係なく幅広く対応することが多いため、支援内容が一律になりがちです。その一方で、特化型事業所では、発達障害やうつなど特定の障害に特化しているため、その障害に特有の困難やニーズに対して、的確なアプローチができるのが強みです。たとえば、atGPジョブトレの発達障害コースでは、特性による苦手を理解した上で、職場での具体的な困りごと(指示の受け取り方、優先順位の判断、対人ストレスへの対応など)に特化したトレーニングが行われています。また、スタッフがその分野の支援経験を積んでいるため、悩みを共有しやすく、信頼関係を築きやすいという利点もあります。一般的支援では手薄になりがちな部分に丁寧に寄り添ってくれるため、「これまで理解されなかった」「相談できる人がいなかった」という人ほど、特化型のサポートで安心感を得られるケースが多くあります。働くうえで自分に必要な支援とは何かを明確にし、それをしっかりと受け取れる場を選ぶことが、就労成功への第一歩となります。
| サポート内容 | 一般的支援 | 発達特化型支援 | 特化型が向いている人 |
| コミュニケーション支援 | ロールプレイ中心 | 表情・言葉の選び方も細かく指導 | 会話が苦手、感覚が独特な人 |
| スケジュール管理 | 自己申告がベース | タスクを可視化して共有 | 頭の中で整理しづらい人 |
| 感覚配慮 | 基本なし | 照明・音・香りなど配慮あり | 感覚過敏がある人 |
| スタッフの理解度 | ばらつきがある | 発達支援専門スタッフ在籍 | 自分の特性を深く伝えたい人 |
視覚化、スモールステップ、感覚配慮などが充実
発達障害のある方が働く力を身につけていくには、「自分に合った学び方」「無理のない進め方」「感覚的な負担への配慮」がとても重要です。特化型の就労移行支援事業所では、こうしたポイントを丁寧に押さえたサポートが行われています。たとえば「視覚化された情報提示」は、口頭での説明が苦手な方にも理解しやすい工夫の一つです。スケジュールや業務の進め方を見える形で提示することで、安心感が生まれ、集中して取り組めるようになります。また「スモールステップ」は、いきなり高い目標を求めるのではなく、小さな成功体験を積み重ねることで、着実に自信を育てていく支援方法です。さらに、感覚過敏への配慮として、静かな訓練スペースやイヤーマフの貸し出し、照明や温度管理への対応なども重視されています。こうした環境の中で支援を受けることで、自分の特性を否定せず、安心して成長していける土台が整います。manabyやミラトレのような事業所では、こうした配慮が自然に組み込まれており、利用者の声に柔軟に応じながら支援が行われています。
オンライン支援|自宅で相談・訓練ができる新しい選択肢
近年、就労支援の新たな選択肢として注目されているのが「オンライン支援」です。これは、自宅にいながら支援員との面談やスキル訓練、生活リズムのサポートを受けられる仕組みで、通所が難しい方や自分のペースで進めたい方に特に適しています。発達障害のある方にとっては、通勤のストレスや他者との接触による不安が大きな負担となることがあるため、自宅からリラックスした状態で支援を受けられることは大きな利点です。たとえばmanabyでは、完全オンラインでのeラーニングプログラムや定期的なオンライン面談を提供しており、全国どこからでも自分に合った支援を受けることが可能です。また、在宅訓練を希望する方にも対応しており、働き方の選択肢を広げる後押しとなっています。自宅での支援が中心であっても、就職活動や企業とのやり取りまで一貫してサポートしてくれるのが大きな特徴です。
オンライン支援のメリット・活用方法と続けるコツ
オンライン支援の最大のメリットは、「自分のペースで無理なく続けられる」という点にあります。通所の負担がなく、慣れた環境で支援を受けられるため、外出に不安のある方や体調の波が大きい方にとっては非常に有効です。また、通勤時間が必要ない分、生活リズムを整える余裕が生まれ、集中して取り組める時間を確保しやすくなります。manabyのように、動画講座やチャットでの質問サポートを提供している事業所では、学びたいときに学べる柔軟性も高く評価されています。ただし、オンライン支援を効果的に活用するためには、「生活リズムの自己管理」「定期的な振り返り」「支援員とのコミュニケーションの継続」が重要になります。画面越しのやり取りだけで終わらせず、必要に応じて対面相談やリアルな体験にもつなげていくことで、より実践的な力が養われていきます。継続するコツは、「完璧を求めず、少しずつ進めること」。自宅でも支援とつながっているという安心感が、長く働くための土台となっていきます。
| 特徴 | オンライン支援 | 通所支援 | 向いている人 |
| 利用環境 | 自宅から参加 | 施設に通所 | 通勤がストレスの人 |
| サポート内容 | 面談・訓練・グループワークも可能 | 対面での作業練習あり | 生活リズムに余裕を持ちたい人 |
| 続ける工夫 | スケジュール管理/習慣化支援あり | 通所による強制力あり | 体調に波がある人 |
| デメリット補完 | 通信・集中環境に依存 | 人間関係の練習がしやすい | 外出が不安な人/静かな環境が必要な人 |
通所が難しい人でも「今できる形」で始められる
体調の波が大きかったり、外出への不安が強いなどの理由で「通所が難しい」と感じる方にとって、就職の準備をどう始めればいいのかは大きな悩みです。しかし、最近では通所しなくても利用できる支援サービスが増えており、「今できる形」でスタートできる環境が整いつつあります。たとえばmanabyでは、在宅でのオンライン支援を中心に、動画学習やチャット相談、Web面談など、全てのプログラムを自宅から参加できるよう設計されています。無理をして通所するのではなく、自分のペースを大切にしながら、必要な準備を少しずつ積み上げていくことが可能です。また、オンライン支援をきっかけに生活リズムが整い、結果として通所訓練や職場実習への参加にステップアップする利用者もいます。「何もできない」ではなく、「できることから始めてみる」という考え方が、再出発の第一歩になります。
支援を受けて気づいた「就職に必要な力」は“自分を知る”こと
就職のために必要なのは、単にスキルや資格だけではありません。支援を受けながら就労を目指す中で、多くの人が気づくのは「自分自身を深く理解すること」の大切さです。どんな仕事が得意で、どんな環境だとストレスを感じやすいのか、どんな配慮があれば働きやすいのか——こうした「自己理解」が進むことで、職場選びの精度が上がり、就職後のミスマッチを防ぐことができます。就労移行支援では、この「自分を知る」プロセスを支援員とともに丁寧に進めていく時間が用意されています。ココルポートやキズキビジネスカレッジなどでは、自己分析やキャリアカウンセリングを通して、自分らしい働き方を見つける支援が行われています。これは、単なる就職準備ではなく、自分の人生をどう歩んでいくかを考えるプロセスでもあります。「自分に合った職場」は、自分を知ることから始まるのです。
得意・不得意を知り、環境に合わせて工夫する力
「自分を知る」とは、ただ自己紹介を上手にすることではなく、日常の中でどんなことが得意で、何に困りやすいのかを把握し、それに対してどう工夫できるかを考えられる力を指します。たとえば、作業を段取りよく進めるのが苦手であれば、メモやToDoリストで補う、口頭指示が苦手であれば書面で依頼してもらうなど、自分なりの対策がとれるようになることが大切です。こうした工夫の力は、まさに「環境に適応する力」であり、発達障害のある方にとっては長く働くための大きな武器になります。就労支援の現場では、こうした力を育む訓練として、模擬業務、役割分担、職場体験などが取り入れられています。たとえばatGPジョブトレでは、職場での困りごとを想定したケーススタディに取り組み、どう対応すれば良いかを考える練習が行われています。得意を伸ばし、不得意を工夫で乗り越える——それが、自分らしい働き方への第一歩です。
| スキル・特性 | 状況例 | 工夫したこと | 結果 | 気づき |
| 読解は得意/音に敏感 | 会議で議事録担当になった | メモに集中しやすい席にしてもらう | スムーズに記録できた | 得意を活かせば貢献できる |
| マルチタスクが苦手 | 電話対応とデータ入力の同時進行 | 「同時作業NG」とあらかじめ伝える | 作業ミスが減った | 苦手を伝える=迷惑ではない |
| 会話が苦手/文字が得意 | 伝達ミスが多かった | 書面やチャットでのやりとりを提案 | 誤解が減り評価も上がった | 自分に合う伝え方でいい |
無理しない働き方を選べる“自己理解”の大切さ
就職活動や職場での人間関係に悩む中で、発達障害のある方がよく感じるのは「どうして自分だけうまくいかないんだろう」という孤独や不安です。しかし、うまくいかない理由は「能力がないから」ではなく、「自分の特性と環境が合っていなかったから」であることが多くあります。このギャップを埋めるカギとなるのが“自己理解”です。自分がどんなことにストレスを感じ、どんな場面で力を発揮しやすいかを知ることで、「無理しない働き方」が初めて見えてきます。
たとえば、ココルポートやキズキビジネスカレッジなどの就労移行支援事業所では、自己理解を深めるプログラムが組み込まれており、ワークシートや支援員との面談を通じて、自分の特性を客観的に見つめ直す機会が用意されています。このプロセスによって、「人と話すより黙々と作業する方が向いている」「体調の波があるから柔軟な勤務時間が必要」など、自分に合った条件が明確になり、職場選びもスムーズになります。
“自己理解”が深まることで、無理して人に合わせようとするのではなく、「自分はこう働きたい」と言えるようになります。これは、働くことへの恐怖心や不安を減らし、安心して仕事を続けるための大きな一歩です。就職はゴールではなく、自分らしく生きるための手段。その出発点として、“自己理解”の大切さに気づくことが、発達障害のある方にとって本当の意味でのキャリアのスタートになります。
| 自己理解項目 | 過去の思い込み | 実際の気づき | 選んだ働き方 | 結果 |
| 働く時間帯 | 「9時から働くのが常識」 | 午前が苦手でミスが多い | フレックス勤務 | 生産性が上がった |
| 対人接触の頻度 | 「雑談は職場の潤滑油」 | 会話がストレスだった | 1人作業中心の職場 | 疲れが激減した |
| 評価の基準 | 「周りに合わせるのが正解」 | 自分の軸で判断する方がラク | 個別評価制度ありの職場 | 継続して働けている |
“苦手”を伝えることが、信頼につながる場面もある
「自分の苦手なことを職場で伝えるのは怖い」「迷惑をかけてしまうかもしれない」と感じる方は多いかもしれません。特に発達障害のある方にとっては、「空気を読めないと思われたらどうしよう」「仕事ができない人だと思われたら困る」といった不安がつきまといます。しかし、実際には“苦手”を正直に伝えることが、かえって信頼関係の構築につながることがあります。大切なのは、単に「できません」と伝えるのではなく、「こういう理由で苦手です」「こうすれば対応できます」といった具体的な説明や代替案を添えることです。
就労移行支援では、この「伝える練習」も重要なプログラムの一つとして取り入れられています。たとえばミラトレでは、自己表現のトレーニングや模擬面接、ロールプレイなどを通して、支援員と一緒に伝え方を身につけることができます。atGPジョブトレでも、「配慮事項をどのように伝えるか」「苦手をどう説明するか」といった相談を丁寧に行い、実践力を養っています。
“苦手”をうまく伝えられるようになると、上司や同僚も配慮しやすくなり、無理のない協力体制が築かれていきます。「苦手なことを抱え込む」のではなく、「苦手だからこそ工夫する姿勢」を見せることで、誠実さや主体性として受け止められることも少なくありません。信頼とは完璧であることではなく、自分の特性を正直に伝えながら、協力を求める姿勢から生まれていくのです。
| 状況 | 伝えた内容 | 相手の反応 | その後どうなったか | 学んだこと |
| 面接 | 「電話対応が苦手です」 | 他の業務で調整してくれた | 無理なく仕事に集中できた | 苦手も立派な情報 |
| 配属前の面談 | 「指示は文書でいただきたい」 | 快くOKされた | 作業ミスがなくなった | 最初に伝えるのがコツ |
| チーム作業 | 「雑談が多いと集中できない」 | 雑談タイムを業務外に移した | 居心地がよくなった | 困りごとは共有してOK |
成功体験:支援サービスを利用して、自分らしく働けた例
就職に不安を抱えていた発達障害のある方が、就労移行支援サービスを利用することで、無理なく自分らしい働き方を手に入れた事例は数多くあります。共通しているのは、「いきなり就職を目指すのではなく、小さな成功体験を積み重ねるプロセス」があったという点です。たとえば、ミラトレでは個別の支援計画に基づき、生活リズムの安定からスタートし、ビジネスマナーやグループワークを通じて、少しずつ社会との接点を広げていく支援が行われています。また、キズキビジネスカレッジでは、自分の特性に合った環境や配慮を丁寧に整理しながら、徐々に「働ける自分」への実感を深めていくカリキュラムが組まれており、一人ひとりの進度に応じた支援が可能です。
成功体験を得た方々の多くは、最初は「自分には働けないのではないか」「また失敗するのでは」といった不安を抱えていました。しかし、支援員との信頼関係や、居心地の良い訓練環境に支えられることで、自分の特性を受け入れながら、自分らしい働き方を見つけることができたのです。これらの実例は、「どんな状態からでも、一歩ずつ積み重ねていけば働ける未来がある」という強いメッセージを持っています。
職場見学から始まり、少しずつステップアップできた
いきなり就職を目指すのではなく、まずは「職場を見てみる」ことから始めるという方法は、発達障害のある方にとって非常に効果的です。実際にどんな仕事が行われているのか、どんな人たちが働いているのかを目にすることで、漠然とした不安が具体的な理解へと変わっていきます。たとえばココルポートでは、利用者が興味のある職種に応じて、企業見学や職場体験の機会を複数回設けており、現場での雰囲気を肌で感じながら「自分に合うかどうか」を確かめられるようになっています。
職場見学のあと、実際の職場で短時間の実習に参加したり、支援員が同行してフォローする形で現場を体験するステップへと進むこともできます。この段階的なアプローチにより、「自分にもできそう」「思ったより落ち着いていられる」といったポジティブな気づきが生まれやすくなります。また、見学を通じて「ここは自分には合わないかもしれない」と判断することも、無理のない働き方を見つける上では重要なプロセスです。焦らず、少しずつステップアップしていくことで、自信と実感を積み上げながら、自分にとって本当に居心地の良い職場にたどり着くことができるのです。
| ステップ | 実施内容 | その時の気持ち | 気づいたこと | 次の行動 |
| 1.職場見学 | 社内見学+雰囲気チェック | 緊張していたが安心できた | 職場の空気が大切だと実感 | 支援員と希望条件を相談 |
| 2.短期実習 | 1週間の軽作業に参加 | 疲れたけど「できた」感覚 | 無理しなければ働ける | 働く時間の調整を希望 |
| 3.本採用面接 | 配慮事項を自分の言葉で伝える | 不安はあったけど誠実に話せた | 面接=評価ではなく対話 | 合格後、安心してスタート |
職場と支援員がつながっていたことで安心して働けた
発達障害のある方が安定して働き続けるためには、「職場」と「支援者」がつながっていることが大きな安心材料になります。就職した後に環境が変わると、慣れない人間関係や業務内容に戸惑い、体調やメンタルのバランスを崩してしまうことも少なくありません。そんなとき、支援員が職場と継続的に関わってくれる体制があると、「困ったときに相談できる」「自分を理解してくれる人がいる」と感じられ、精神的な安定につながります。
たとえば、ミラトレでは「定着支援」に力を入れており、就職後も定期的に支援員が職場を訪問したり、本人と面談を行ったりしています。実際に、業務の進め方や職場のコミュニケーションで困りごとがあったときも、支援員が間に入って職場に状況を伝えてくれたことで、大きなトラブルにならずに済んだという声もあります。また、atGPジョブトレでは、企業との連携を密に行い、配慮事項の説明やフォローアップ面談を通して、本人が働きやすい環境づくりを支援しています。
こうした「つながりのある支援」は、単なる就職支援ではなく、職場生活全体を支える土台となります。仕事がうまくいかないときでも「ひとりで抱え込まなくていい」という安心感があるだけで、長く働く力が育まれていきます。支援員との連携があるからこそ、企業側も本人の特性を理解しやすくなり、職場の定着率も高まるという好循環が生まれているのです。
| つながりの場面 | 支援員の役割 | 職場の対応 | 利用者の気持ち | 長期定着につながった理由 |
| 配属前 | 働き方の希望を共有 | 必要な配慮を導入 | 「自分のことを分かってくれてる」 | 最初から環境が整っていた |
| トラブル発生時 | 状況を中立的に整理 | 配慮の再調整を実施 | 第三者がいることで安心 | 途中で辞めずにすんだ |
| 月次面談 | 状況報告と感情の確認 | 継続して受け止めてくれた | ひとりで抱えなくていい | 長く働く土台ができた |
就職後も定着支援があって、ひとりじゃないと思えた
発達障害のある方が「働き続ける」ためには、就職そのものよりも「就職後のサポート」がどれだけ手厚いかが重要になります。特に、働き始めてから気づく不安やストレスは想像以上に大きく、周囲に相談できる人がいないと、些細な悩みが大きな離職理由へとつながってしまうこともあります。そんなとき、支援サービスによる「定着支援」があることで、「自分はひとりじゃない」と感じられることが大きな支えになります。
たとえば、ミラトレでは就職後も定期的に利用者と連絡を取り、体調や職場での人間関係、業務の進め方などについて継続的にフォローを行っています。また、atGPジョブトレでは企業との橋渡し役として、勤務環境や配慮事項が適切に保たれているかを確認し、必要があればすぐに調整を行える体制が整っています。
実際に支援を受けた方の多くが、「不安を感じたときにすぐに話せる場所があった」「支援員が自分の状況をわかってくれているという安心感があった」と語っています。こうした“見守られている”感覚は、就職後の安定につながり、長く働くことへの自信にもなります。ひとりで不安を抱え込まず、定着支援を受けながら「働き続けられる環境」を築いていけることは、発達障害のある方にとって大きな安心材料となるのです。
| サポート内容 | 利用した場面 | 効果 | 続ける決め手になったこと |
| 月1面談 | 感情の整理ができなかったとき | 安心して気持ちを吐き出せた | 否定せず聞いてくれる場所があった |
| 職場との調整 | 業務量が合わずパンクしそうに | 勤務時間を見直してもらえた | 無理せず続けられるようになった |
| 窓口としての存在 | 体調悪化で休職か迷ったとき | 医師と職場をつないでくれた | 自分だけで判断しなくていいと実感 |
働きずらさを感じている人におすすめの転職サービス
dodaチャレンジ|ストレスを減らせる環境を一緒に考えてくれる
→dodaチャレンジ アフィリリンクを貼る
関連ページはこちら:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
LITALICOワークス|働く前に心の準備ができる就労支援
→LITALICOワークス アフィリリンクを貼る
ランスタッド|大手だから安心して相談できる環境がある
→ランスタッド アフィリリンクを貼る
atGP|理解ある職場紹介で再出発を後押ししてくれる
→atGP アフィリリンクを貼る
ミラトレ|小さな練習から始められる就労移行支援サービス
→ミラトレ アフィリリンクを貼る
【まとめ】発達障害 就職 支援 サービス|「働けるかも」と思える居場所を見つけよう
発達障害のある方にとって、就職活動や職場での人間関係は、非常に大きな不安や負担を伴うものです。「働きたい」という気持ちがあっても、特性に合わない環境では力を発揮できず、自信を失ってしまうこともあります。そんなとき、自分を理解してくれる人がいて、少しずつでも安心して進める場所があれば、「働けるかもしれない」という前向きな気持ちを取り戻すことができます。
manabyやミラトレ、atGPジョブトレ、ココルポート、キズキビジネスカレッジなどの就労移行支援事業所では、それぞれの発達特性に応じた個別支援を行っており、生活リズムの整えからスキル習得、職場見学、就職後の定着支援に至るまで、一貫したサポート体制が整えられています。通所が難しい方にはオンライン支援の選択肢もあり、どんな状況にあっても「今できること」から始められる環境が用意されています。
働くことは、単なる労働や収入だけではなく、「自分らしく社会とつながること」にもつながります。そのために必要なのは、「頑張りすぎる」ことではなく、自分の特性を理解し、工夫しながら向き合っていくことです。そして、そのプロセスを支えてくれる人や場所と出会うことが、これからの働き方を大きく変えるきっかけになります。「どうせ自分には無理」と思わずに、まずは一歩踏み出せる場所を探すことから始めてみましょう。きっと、自分らしく働ける居場所が見つかるはずです。
関連ページはこちら
精神障害のある方が働くために知っておきたい制度
制度の違いや企業側の理解について、わかりやすく紹介しています。
→関連ページはこちら【精神障害×就職】雇用制度を正しく知れば、働きやすさは変えられる
30代でキャリアチェンジを考えている人へ
発達特性に気づいたあと、異業種に転職した人の実体験を紹介しています。
→関連ページはこちら「キャリアチェンジ 方法 30代」へ内部リンク
スキルを磨いて転職を成功させた人の話
小さな強みを活かして希望の仕事を見つけた例を紹介しています。
→関連ページはこちら「スキルアップ 転職 成功例」へ内部リンク
自宅でできる働き方を探している人へ
テレワークの求人の探し方や、発達特性に合った在宅勤務の工夫をまとめています。
→関連ページはこちら「テレワーク 求人 探し方」へ内部リンク
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
生活とお金に関するおすすめ情報まとめ(ドメイントップページ)を見る
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
厚生労働省「こころの健康」ページも参考になります

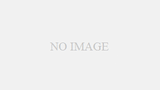
コメント