「こんなこと、誰に話せばいいの?」――職場での悩みはひとりで抱えなくていい
職場での人間関係に悩んでいるとき、最もつらいのは「誰にも話せない」と感じてしまうことです。「自分の感じ方が大げさなのかもしれない」「相談したところで変わらないかも」と考えて、心の中に押し込めてしまう人は少なくありません。特に、ハラスメントや孤立などの繊細な問題は、誰にどのように伝えればいいのかがわからず、結果として“ひとりで耐える”という選択をしてしまう傾向があります。
しかし、どんなに小さく見える問題でも、自分にとって苦しいと感じているなら、それは相談していいサインです。悩みを打ち明けることは弱さではなく、自分を守るための大切な行動です。就労移行支援サービスや転職エージェントの中には、メンタルケアや相談窓口を設けているところもあり、会社の外側に「話を聞いてくれる場所」があると知るだけでも、気持ちはぐっと楽になります。たとえば、atGPやキズキビジネスカレッジでは、就職前後の悩みに寄り添いながら、定着支援を通じて心の安定をサポートしてくれます。
「こんなこと」と思わずに、自分の心の声に正直になってみてください。話せる場所を見つけることが、回復の第一歩になることもあります。
これってハラスメント?相談してもいい“サイン”を見逃さない
毎日のように繰り返される叱責、陰口、無視、過度な干渉や管理。それが日常になってしまうと、「これって普通のことなのかも」と自分の感覚が麻痺してしまうことがあります。けれども、職場で感じる不安や違和感には、必ず何かしらの“理由”が存在します。大切なのは、その違和感を無視せず、「これは相談すべきサインではないか」と自分自身に問いかけることです。
特に、パワハラやモラハラの兆候は、受け手の気づきに委ねられる部分が多いため、相談のタイミングを逃してしまいがちです。就労移行支援を利用している方の中にも、「もっと早く相談すればよかった」「自分のせいだとばかり思っていた」と語る方が多くいます。そうした後悔を繰り返さないためにも、“サイン”を早めに認識し、信頼できる機関に相談することが重要です。
これってハラスメント?相談していい“サイン”チェック表
以下のような状態に当てはまることがあれば、それは「相談してもいいサイン」かもしれません。
* 上司や同僚の態度で毎日気分が沈む
* ミスを必要以上に責められる/大声で怒鳴られる
* 仕事に必要な情報を意図的に伝えられない
* 無視や仲間外れが続いている
* 体調を崩しても休みにくい、配慮がない
* 勤務後や休日にも執拗に連絡がある
* 「自分がいなくなれば楽になる」と思うことがある
* 会社に行こうとすると吐き気や頭痛がする
これらに心当たりがある場合は、我慢せず、まずは社内の相談窓口、もしくは就労移行支援や外部の労働相談機関に話してみることをおすすめします。たとえば、LITALICOワークスやmanabyでは、利用者の不調にいち早く気づき、必要に応じて企業側と連携を取ることで、安心して働ける環境づくりをサポートしています。
あなたの感じている「おかしいかも」という感覚は、決して間違いではありません。その直感を信じて、自分の心を守る行動をとってみてください。ひとりで抱え込む必要はないのです。
| 状況 | 内容 | 自分の感情 | 相談の目安 |
| 叱責 | 人前で怒鳴られる/人格を否定される | 「自分が悪いのかも」「消えたい」 | 月1回以上あれば相談対象 |
| 無視・排除 | 話しかけても反応がない/LINEグループから外される | 「存在を否定されている」 | 日常的に起きているなら危険信号 |
| 不公平な扱い | 自分だけシフトがきつい/評価されない | 「努力が無意味に感じる」 | 理由なく差別があれば要相談 |
日常的な叱責、人格否定、無視…「自分が悪いのかも」と感じているあなたへ
毎日のように繰り返される叱責や人格を否定するような言葉、あるいは無視される態度に晒されていると、「私が悪いのかもしれない」と感じてしまうことがあります。特に、真面目で責任感が強い人ほど、自分を責める傾向が強く、「もっと頑張らなきゃ」「私の努力が足りない」と限界を超えて耐え続けてしまうのです。しかし、それはあなたが悪いからではありません。問題があるのは、そのような態度をとる側であり、あなたの人格ではありません。
人間関係のストレスは、気づかぬうちに心を蝕み、次第に体調不良や自己肯定感の低下にもつながります。私自身、長い間そうした状況に置かれ、「我慢が美徳」と信じて踏ん張ってきましたが、最終的には心が悲鳴をあげる結果となりました。そこから回復するまでには時間も必要でしたが、「これは私のせいじゃない」と気づくことが、回復への大きな一歩でした。あなたも、自分を責めずに、まずは「話してもいい」「助けを求めていい」と思ってください。それだけでも、状況は少しずつ変わっていきます。
記録をとる、信頼できる人に話す――はじめの一歩が未来を変える
職場での嫌がらせや理不尽な扱いに直面したとき、まず行うべきは「事実を記録すること」です。誰に、どんなことを、いつ、どのように言われたのか――感情と事実を分けて記録しておくことで、いざ相談するときにも冷静に伝える材料になります。感情に流されず、第三者に状況を説明するためにも、客観的な記録は大きな力になります。
そしてもう一つ大切なのは、信頼できる人に「話す」ことです。職場内であっても、家族や友人、あるいは就労移行支援のスタッフなど、安心して話せる人に気持ちを打ち明けることが、精神的な負担を軽減します。LITALICOワークスやatGPジョブトレでは、利用者の悩みに寄り添い、必要に応じて企業側と調整を行う支援体制が整っており、「誰かに話してもいい」と思える環境が用意されています。
一人で耐え続ける必要はありません。あなたの声を聞いてくれる場所は、必ずあります。その最初の一歩が、未来を大きく変えていくことにつながるのです。
【相談先①】社内の相談窓口を利用する
まず検討したいのが、社内に設置されている相談窓口の利用です。多くの企業では、パワハラやセクハラなどのハラスメント行為を未然に防ぐための制度が整えられています。人事部、産業医、またはハラスメント専用の相談窓口がある場合、それらを活用することで、社内での問題解決を目指すことが可能です。「職場に言いにくい」と感じるかもしれませんが、相談を行ったことで処遇が不利になることを禁止する法律もあり、安心して声をあげられる体制がつくられています。
人事・産業医・専用窓口がある場合の動き方
相談する際には、まず「どこに・誰に・どう伝えるか」を整理しておくと安心です。人事部には一般的な就業規則や社内トラブルに関する窓口が設けられていることが多く、産業医は体調面・精神面の不調に対して、医学的な観点から対応してくれます。会社によっては第三者機関が運営する「外部相談窓口」を導入している場合もあるので、相談のハードルが下がる仕組みがあるかどうか、社内のポータルや就業規則を確認してみましょう。
会社が設けている“ハラスメント対策制度”を活用するコツ
制度があるだけで実際に活用されていないケースも少なくないため、制度を上手に使うためには事前準備が重要です。たとえば、記録を取っておくこと、同じような経験をしている人がいないか情報を集めることなどがポイントになります。相談するときには、感情的にならず、事実を冷静に伝えるよう意識すると、相手に伝わりやすくなります。また、社内で対応が難しいと感じた場合には、就労移行支援サービスのスタッフや外部の労働相談機関と連携することで、より安心して行動に移すことができます。
社内窓口を使うときのポイント
社内の相談窓口を利用する際は、以下の点を意識すると効果的です。まずは記録(日時、状況、発言など)を時系列で整理しておくこと。次に、「何に困っているか」「何を改善してほしいか」を自分の中で明確にしておくこと。そして可能であれば、直接の上司ではなく、第三者的な立場にある人事や相談担当者を選ぶと安心です。相談後は、対応の経過や結果についても書き留めておくと、万が一の備えになります。
「話してもムダかも」と思っていた悩みが、話してみたことで初めて整理されることもあります。まずは一度、あなたの感じている“違和感”を誰かに伝えることから始めてみましょう。自分を守るための制度を、遠慮なく使ってください。
| 窓口の種類 | 役割 | メリット | 注意点 |
| 人事部 | 会社内の人事トラブル調整 | 内部調整がしやすい/配置換えも可能 | 会社側に情報が残る可能性 |
| 産業医 | 心身の不調の相談・診断 | 医学的立場から勤務継続の可否を判断 | 出社義務との調整が必要な場合も |
| ハラスメント相談窓口 | 専門担当による第三者対応 | 担当者変更が可能/守秘義務あり | 記録を取っておくとベター |
【相談先②】外部の専門窓口に相談する
職場の人間関係に悩み、社内の相談窓口では話しづらい、もしくは相談しても改善の兆しが見えないというときには、「外部の専門窓口」を活用するという選択肢があります。特に、ハラスメントや長時間労働、メンタルヘルスに関する問題は、職場の内部だけでは解決が難しいことも少なくありません。外部の専門機関では、第三者の立場から冷静に話を聞き、今後どう行動するべきかの具体的なアドバイスを受けることができます。
たとえば、「労働局」や「労働基準監督署」では、労働法違反やハラスメントに関する無料相談を随時受け付けており、必要があれば企業への指導やあっせん制度の案内を行ってくれます。また、厚生労働省が設置している「ハラスメント悩み相談室」や各自治体の相談窓口では、匿名での相談にも対応しており、「名前を知られたくない」「会社に知られるのが怖い」という場合でも安心して利用できます。
こうした外部窓口では、電話やWebフォームなど、複数の手段で相談ができるようになっているため、精神的に不安定なときでも負担なく話しやすいのが特徴です。また、必要に応じて弁護士や産業カウンセラーなどの専門職につなげてくれるケースもあり、自分では気づかなかった選択肢が見えてくることもあります。
実際に相談する際には、できる限り具体的な状況を整理して伝えることが大切です。たとえば、「いつ」「誰に」「どんなことを言われたか」「その後どう感じたか」をメモに残しておくと、相談員も状況を理解しやすく、適切なアドバイスをもらえる可能性が高まります。
外部の窓口に話すことは、「会社に逆らうこと」ではありません。むしろ、自分の身を守るための冷静な行動であり、将来の働き方や生活を見直す大きな一歩です。ひとりで抱えず、信頼できる第三者に気持ちを打ち明けてみることで、今の状況が少しずつ動き出すかもしれません。自分の心と身体を守るためにも、「相談すること」を恐れずに選択肢の一つとして持っておくことが大切です。
外部窓口を選ぶときの比較表
| 相談先 | 特徴 | 向いている人 | 相談内容の一例 |
| 労働局 | 行政機関/法的相談も対応 | 社内対応に不信感がある人 | パワハラ・解雇・労働条件 |
| ハラスメントホットライン | 匿名/電話・チャット可 | 話すのが怖い/記録がない人 | 嫌がらせ・モラハラなど幅広く対応 |
| 労働組合 | 組織で交渉してくれる | 職場に改善を求めたい人 | 異動/謝罪要求などの交渉 |
労働局/労働基準監督署/ハラスメントホットライン
職場の人間関係に強いストレスを感じているにもかかわらず、社内に相談しづらい場合や、相談しても改善されない場合には、公的な相談機関を活用するという方法があります。代表的な窓口としては、「労働局」「労働基準監督署」「厚生労働省のハラスメントホットライン」などがあります。これらは企業外の第三者が対応してくれるため、安心して相談しやすいという特徴があります。
労働局では、パワハラ・セクハラなどの労働環境に関する相談を受け付けており、必要に応じて企業への指導や助言を行います。また、労働基準監督署では、労働時間や安全衛生、賃金に関する相談のほか、明らかなハラスメント行為についても状況に応じて対応してくれます。さらに、厚生労働省の「職場のハラスメント相談ダイヤル」などでは、匿名でも相談ができるため、まずは話を聞いてもらいたいという場合にも利用しやすい仕組みです。
無料・匿名でもOKな窓口の特徴と違い
こうした公的な相談窓口の多くは、相談者のプライバシーを守りつつ、無料・匿名での対応を行っています。たとえば、ハラスメントホットラインは、匿名で相談ができるだけでなく、相談内容をもとに今後どう行動するべきかのアドバイスも受けられるため、「今すぐ会社には言えないけど、何かできることはないか知りたい」という方にとっても利用しやすい窓口です。
一方、労働局や労基署は、具体的な証拠(記録や資料など)がある場合に、企業に対して直接的な指導や是正を求める手続きに進むことができるため、「自分だけでは解決できない段階」に入っているケースで特に有効です。ただし、対応の可否は内容や状況により異なるため、まずは現状を相談し、方針を一緒に考えてもらうことが大切です。
いずれの窓口でも「相談するだけ」で終わっても構いません。自分ひとりで抱えず、客観的な視点を持つことで、少しずつ冷静に状況を整理できるようになります。
【相談先③】就労支援機関で職場との“間に立ってもらう”
職場での人間関係に悩んでいる場合、社内や公的機関に直接相談することに不安を感じる人も少なくありません。そのようなときに、より安心して相談できるのが「就労支援機関」の存在です。特に、就労移行支援や就労定着支援といった福祉サービスでは、職場との“間に立って”問題を調整してくれる役割を果たしてくれるため、当事者が一人で企業と向き合わなくて済むというメリットがあります。
就労移行支援・就労定着支援の役割
就労移行支援は、一般企業への就職を目指すために必要なスキル訓練や就活サポートを提供する福祉サービスですが、それだけでなく、職場で働き始めた後の「定着支援」にも大きな力を発揮します。定着支援では、職場の上司や人事担当者と利用者の間に入って、「働きやすい環境」や「配慮事項」のすり合わせを行ってくれます。atGPジョブトレやミラトレ、manabyなどの支援機関では、定期的な面談や企業訪問を通じて、円滑な人間関係の構築をサポートしてくれます。
就労支援を通して職場とつなぐ例
たとえば、ある利用者は職場の先輩からの圧力的な言動に悩んでいましたが、自分から会社に伝える勇気が持てずにいました。そこで支援スタッフが間に入り、企業と面談を行った結果、担当部署の変更と働き方の調整が実現しました。本人は「自分だけで言っていたら、ここまで動いてもらえなかったと思う」と話していました。このように、就労支援機関は「第三者の視点」で冷静に状況を伝え、必要な配慮や改善を企業に働きかけてくれる存在です。
また、LITALICOワークスやキズキビジネスカレッジのような支援機関では、働く上での困難をあらかじめ共有しておく「職場定着シート」などを活用し、トラブルを未然に防ぐ取り組みも行っています。こうした支援を受けることで、職場での人間関係に対する不安を大きく軽減することが可能です。
自分一人で職場と向き合うのが難しいと感じたら、支援機関を頼ることは決して特別なことではありません。あなたの気持ちや働きやすさを最優先に考えてくれる存在と一緒に、安心できる環境をつくっていきましょう。
| 支援機関 | 主な役割 | 支援内容 | 利用してよかった点 |
| 就労移行支援 | 就職・職場定着のサポート | 職場訪問・配慮調整・第三者面談 | 感情的にならず伝えられた |
| 定着支援事業所 | 雇用継続のフォロー | 月1回の職場面談/支援員同席 | ひとりで抱え込まなくて済んだ |
| 障害者職業センター | 雇用支援+職業適性評価 | 状況を中立的に整理/診断あり | 「働き続ける工夫」を一緒に考えてもらえた |
合理的配慮とトラブル調整をセットでサポートしてもらえる仕組み
職場での人間関係やハラスメントに悩む中で、「こんな環境では働き続けられない」と感じながらも、「でも、退職以外に方法はないのか」と迷うこともあるでしょう。そんなとき、合理的配慮とトラブル調整を一体的に支援してくれる仕組みを知っておくことは、とても大切です。特に就労移行支援や就労定着支援では、障がいやメンタル面の不調などに配慮しながら、本人にとって働きやすい環境づくりを企業とともに進める役割があります。
たとえば、LITALICOワークスやatGPジョブトレ、manabyといった支援機関では、利用者が職場で困っていることを丁寧にヒアリングした上で、企業側へ「どのような配慮が必要か」「何を改善すべきか」といった内容を明確に伝え、必要な調整を行います。これは、単なる職場紹介にとどまらず、働き始めたあとも「安心して続けられる環境」を作るための伴走支援です。
合理的配慮とは、業務量の調整、静かな作業環境、定期的な面談など、個々の状況に応じた対応のことを指します。一方で、トラブル調整は、上司との関係や同僚との摩擦など、具体的な問題が発生したときに第三者が介入し、冷静に改善策を提案していくものです。これらがセットで受けられる体制があることで、「辞めなくても状況は変えられるかもしれない」と思える安心感が生まれます。
実際に相談した人の声から学ぶ“相談してよかった”体験談
「相談することで本当に何かが変わるのか」と疑問を感じる方は少なくありません。しかし、実際に相談した人たちの声には、「勇気を出して話してよかった」という実感が多く寄せられています。とくに、誰にも言えずに抱え込んでいた悩みを言葉にしたとき、「それはあなたの責任じゃない」と受け止めてもらえたことが、心の回復の大きな一歩になったというケースは少なくありません。
相談後、職場の環境が変わった人の例
ある女性は、職場での上司からの継続的な叱責と監視によって心身の不調をきたし、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」に相談しました。支援スタッフが企業と連携し、業務内容の再調整と上司の指導体制の見直しが行われた結果、以前とはまったく異なる働きやすい環境へと変化しました。彼女は、「相談していなければ、おそらく辞めるしかなかった。けれど、続ける道があると気づけた」と語っています。
また、別のケースでは、atGPの定着支援を受けていた方が、同僚との人間関係で悩んだ際に相談したところ、社内での業務配置を変更してもらい、心の負担が軽減されたことで就労を継続できたという例もあります。このように、問題が表面化したときに第三者のサポートを得ることで、自分だけでは見つけられなかった「もうひとつの選択肢」が見えてくることがあるのです。
「相談=弱さ」ではなく、「相談=前に進むための力」。困ったときに頼れる場所があることは、働き続けるうえでの大きな安心材料になります。誰かに話してみることが、あなたの働き方を変える第一歩になるかもしれません。
| 相談前 | 相談先 | 起きた変化 | 本人のコメント |
| 出社が怖くなり休職寸前 | ハラスメント相談窓口 | 上司の配置換え/謝罪対応 | 「誰かが信じてくれたと感じた」 |
| 評価されず退職を考えた | 就労移行支援+人事 | 職場の業務変更/支援面談定期化 | 「ここで働き続けてもいいかもと思えた」 |
| 無視される日々で自信喪失 | 労働局 | 注意喚起+再発防止の指導 | 「泣くほど怖かったけど、行動してよかった」 |
異動・転職を前向きに考えるきっかけになった話
職場での人間関係に悩み、誰にも相談できずにただ時間が過ぎていく。そんな状況に心当たりのある方も多いのではないでしょうか。実際に、ある利用者は「上司からの圧が強く、ちょっとしたミスで人前で叱られるのが日常だった」と語っていました。はじめは耐え続けていたものの、体調を崩して就労移行支援に通いはじめたことが、環境を変えるきっかけとなりました。
その方は、LITALICOワークスを通して支援スタッフに自分の状況を打ち明け、企業側に業務内容の調整を提案してもらいました。しかし、根本的な環境改善が難しいと判断され、異動や転職も選択肢として視野に入れたところ、別部署での再スタートが実現。新しい上司との相性も良く、徐々に仕事への自信も回復していったそうです。
このように、最初は「逃げるようで後ろ向き」と感じていた異動や転職が、「自分を大切にするための前向きな決断」へと変わるケースは少なくありません。atGPやミラトレでも、同様に「環境を変えたことで長く安定して働けるようになった」という声が数多く寄せられています。自分にとって無理のない場所を選び直すことは、決して消極的な選択ではなく、働き続けるための前向きな一歩なのです。
【相談前に準備】話すときに整理しておきたいこと
誰かに悩みを相談しようと思っても、「何から話せばいいのかわからない」「感情的になってしまいそう」と不安に感じることはよくあります。だからこそ、相談前に最低限の準備をしておくことで、冷静に、かつ具体的に状況を伝えることができ、支援する側もより適切な対応が取りやすくなります。準備といっても難しいことはありません。以下のようなポイントを押さえておくと安心です。
まずは、「いつ」「誰に」「どんなことをされたか(言われたか)」という事実を簡単に時系列で整理しておくことです。できれば、日時や発言内容、状況などを簡単にメモに残しておくと、相談時に役立ちます。また、「そのことでどんな気持ちになったか」「どのような影響が出ているか(眠れない、吐き気がするなど)」といった、自分の状態についても伝えられるようにしておくと、相談先も配慮の方向性を考えやすくなります。
次に、「どうしてほしいか」という希望を明確にしておくことも大切です。たとえば「部署を変えてほしい」「直接の接触を減らしてほしい」「異動や退職を前提に話を進めたい」など、できる範囲で自分の希望を整理しておくことで、相談が具体的かつ建設的な方向へ進みやすくなります。
こうした事前準備ができていなくても、就労支援機関では、相談しながら一緒に整理していくサポートもあります。キズキビジネスカレッジやmanabyでは、初回の面談から丁寧にヒアリングを行い、本人の言葉を尊重しながら相談内容を整えていくため、安心して相談を進めることができます。
話すことが怖いときほど、ひとりで抱え込まず、準備の段階から支援してくれる存在とつながることが、回復への近道になります。相談は、あなたの味方を見つけるための第一歩です。
相談前に整理しておきたい情報まとめ表
| 整理項目 | 記載例/準備方法 | なぜ必要? | メモのコツ |
| 時期・頻度 | 「2024年11月〜現在」「週3回以上」 | 客観的に説明しやすい | 日記・メモを元に時系列化 |
| 内容の具体性 | 「昼礼で○○と言われた」「会話中に笑われた」 | 抽象的すぎると説得力が弱い | 5W1Hを意識する |
| 心身の変化 | 「寝つきが悪い」「通勤時に動悸」 | 医療機関の診断にもつながる | 医師に見せる資料にもなる |
| 求めたいこと | 「異動」「相手との面談」など | 相手に何をしてほしいか明確に | 遠慮しない/現実的に提案する |
・いつ/どこで/誰が/何をしたか
相談内容を明確に伝えるために、ハラスメントが発生した具体的な事実を「いつ」「どこで」「誰が」「何をしたか」の視点で整理しておくことが大切です。たとえば、「〇月〇日、会議室で上司から『能力が低すぎる』と大声で叱責された」「昼休みに他の社員の前で無視された」といった出来事を、できる限り客観的かつ簡潔にメモしておくと、相談時に話が伝わりやすくなります。もし可能であれば、メールやチャットの履歴、録音など証拠として残せるものがあれば、より説得力が増します。
・心身の状態や業務への影響
その出来事によって「どのような気持ちになったか」「どんな体調の変化があったか」「仕事にどんな影響が出たか」といった、自分の変化を具体的に伝えられると、相談を受ける側も問題の深刻度を把握しやすくなります。たとえば、「夜眠れなくなった」「会社に行くと動悸や吐き気が出る」「集中力が続かなくなり、ミスが増えた」といったように、自分の心と体の状態を見つめ直し、ありのままに伝える準備をしておきましょう。
・どんな支援・配慮を求めたいのか
相談を通じて「何を望んでいるのか」を自分の中で整理しておくことも重要です。「直接関わらない部署へ異動したい」「加害者と距離を置きたい」「在宅勤務など柔軟な働き方を認めてほしい」など、自分にとって必要な配慮を明確に伝えることで、解決に向けた具体的な対応を取りやすくなります。必ずしもすべてが実現できるとは限りませんが、まずは「どう働き続けたいか」を自分なりに考えておくことが、次の一歩につながります。
【まとめ】ハラスメント 相談 窓口|声をあげることは“わがまま”じゃない。“働き続ける”ための行動です
職場でのハラスメントや人間関係の問題に直面したとき、多くの人が「自分が悪いのかも」「こんなことで相談してもいいのか」と悩み、声をあげることをためらってしまいます。しかし、自分が日々感じている苦しさや違和感は、決して気のせいではありません。そして、それを誰かに伝えることは“わがまま”ではなく、自分の心身を守るための「働き続けるための行動」なのです。
社内の相談窓口、労働局や労働基準監督署、匿名で使えるホットライン、さらに就労移行支援や定着支援など、頼れる窓口はたくさんあります。特にLITALICOワークスやキズキビジネスカレッジ、atGPなどの就労支援機関は、相談するだけでなく、職場との調整や働き方の見直しまで、継続的に支援してくれる存在として頼りにできます。
相談の前に少し準備をすることで、より安心して自分の状況を伝えられるようになります。そして、相談した先で「あなたはひとりじゃない」と言ってもらえることが、心の支えになるはずです。無理をして働き続けるのではなく、自分に合った環境や支援を選ぶことも、立派な選択肢です。働くことをあきらめないために、今できることから少しずつ始めてみてください。声をあげることは、未来を変えるきっかけになります。
関連ページはこちら
配慮を受けながら働ける職場を探したい方へ
合理的配慮が明記された求人の選び方や、実際の配慮例を紹介しています。
→関連ページはこちら【実例あり】合理的配慮がある求人とは?働きやすさを重視した求人の選び方ガイド
制度を知って働き方を変えたい人に
精神障害がある人のための雇用制度と、職場で活用できる仕組みを紹介しています。
→関連ページはこちら【精神障害×就職】雇用制度を正しく知れば、働きやすさは変えられる
配慮ある求人を探す具体的な方法を知りたい方へ
障害者雇用枠で自分に合った求人を探す手順やポイントをまとめています。
→関連ページはこちら【知らなきゃ損】障害者雇用の求人の探し方|理解ある職場に出会うための実践ガイド
支援者と一緒に進めたいと考えている人へ
就労移行支援での職場選びや相談サポートの内容を詳しく紹介しています。
→関連ページはこちら「就労移行支援 利用 方法」へ内部リンク
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
生活とお金に関するおすすめ情報まとめ(ドメイントップページ)を見る
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
厚生労働省「こころの健康」ページも参考になります

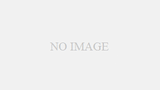
コメント