合理的配慮がある求人ってどうやって見分ける?本当に働きやすい求人の“中身”を具体例で解説!
障害者雇用の求人を探していると、「合理的配慮あり」と書かれているものを目にすることがありますが、具体的にどのような内容なのか分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。実際、求人票だけでは企業の本当の姿までは見えてこないこともあります。大切なのは、「配慮があると書いてある」だけで判断せず、自分にとって本当に働きやすい環境かどうかを“中身”で見極めることです。
たとえば、配慮があるといっても「通院が可能」「短時間勤務に対応」といった形式的な内容だけではなく、具体的なサポート体制や上司・同僚の理解度、業務の進め方に柔軟性があるかといった視点で確認することが必要です。就労移行支援事業所や転職エージェントと連携することで、求人票に書かれていない情報も得られる場合があります。今回は、そんな「合理的配慮がある求人の見分け方」と「本当に働きやすい職場の中身」について、実例を交えて解説していきます。
合理的配慮とは?ただの“優しさ”ではなく、働く権利を支える法的支援です
「合理的配慮」という言葉を聞くと、企業の好意的な対応のように思えるかもしれませんが、実際には法的に定められた「義務」であり、障害者が平等に働けるようにするための重要な仕組みです。2016年に施行された障害者差別解消法により、事業者は障害のある人に対して、合理的配慮を行うことが義務付けられています。つまり、配慮を求めることは「特別扱いしてほしい」というわがままではなく、「働く権利を保障してもらう」ための正当な行為なのです。
企業にとっての「義務」であり、働く人にとっての「安心材料」
合理的配慮は、企業にとっては“法律上の義務”であり、障害のある人にとっては“働き続けるための安心材料”となる存在です。たとえば、通院が必要な方に対しては勤務スケジュールを柔軟に調整したり、感覚過敏のある方には静かな作業スペースを用意するなど、業務内容や勤務環境を可能な範囲で調整することが求められます。
合理的配慮は「義務」と「安心」の両面を持つ制度
この制度は、「企業が配慮して“あげる”」という上下の関係ではなく、「必要な配慮を前提に、双方が協力して働きやすい環境をつくる」という対等な関係を目指すものです。たとえば、atGPやdodaチャレンジといった障害者専門の転職エージェントを通じて紹介される求人には、合理的配慮の具体例が記載されていることも多く、「この企業はどこまで対応してくれるか」が事前に分かる場合があります。
たとえば、ある企業では「業務マニュアルを視覚化して提供する」「日々の体調チェックをSlackなどのツールで行う」といった取り組みが導入されており、精神的な負担を最小限に抑える工夫がなされています。こうした具体的な配慮がある職場では、障害を抱えていても安心して能力を発揮できる環境が整っていることが多いです。
つまり、合理的配慮とは、制度としての「義務」であると同時に、「自分らしく働くための手段」でもあります。だからこそ、求人を選ぶときには「配慮があるかどうか」だけでなく、「どのような配慮があるか」「実際に活用できるか」を見極める視点が重要になります。企業にとっても、働く側にとっても、配慮のある環境は信頼と安定を築く土台となるのです。
| 観点 | 企業にとって | 働く側にとって | 共通の目的 |
| 法的義務 | 障害者雇用促進法に基づく | 保護される権利 | 働きやすい職場づくり |
| 実務面の意味 | 採用・配置・評価での公平性 | 自分に合った働き方の確保 | 長期的な雇用継続 |
| 配慮提供の意識 | 採用時点からの明示が求められる | 面接・配属時に具体的に希望を伝えられる | 「不公平ではなく、“適正”」という考え方 |
障害者雇用促進法に基づいた実効性のある制度
合理的配慮は、単なる職場の「気遣い」ではなく、障害者雇用促進法に基づいた制度的な裏付けを持つ重要な支援です。この法律では、企業が障害のある従業員に対して働きやすい環境を整備するために「合理的配慮を提供する努力義務」を負うことが明記されています。これは身体障害、知的障害、精神障害のいずれにも適用され、特に精神障害のある方にとっては、職場定着を支える非常に大切な枠組みとなっています。
実際の運用としては、「通院への配慮」「業務内容の調整」「静かな職場環境の提供」などが挙げられますが、これらは企業側が「必要な範囲で」個別に対応することが求められています。この“必要な範囲”は本人の申告によって変わるため、求職者が自分に必要な配慮をしっかり言葉にして伝えることが、制度の実効性を引き出すうえで非常に重要です。
就労移行支援事業所やエージェントサービスでは、こうした制度を背景とした支援交渉をサポートする体制が整っており、manabyやatGPジョブトレなどでは、制度に基づいた配慮事項の整理や交渉の練習も実施されています。制度があることで安心できる一方で、それを活かすためには、本人の理解と行動が必要不可欠です。
【求人に見られる配慮の実例】こんな内容が書いてあったらチェック!
障害者雇用の求人票には「配慮あり」と書かれているものの、具体的にどのような支援があるのか明記されていないことが多く、自分に合った職場かどうかを判断しづらいのが現実です。しかし、いくつかのチェックポイントを押さえることで、「配慮の中身」が読み解きやすくなります。特に精神障害や発達障害を持つ方にとっては、「どんな働き方ができるのか」「どの程度の柔軟性があるのか」が明確にされているかが重要な判断基準になります。
以下では、実際の求人に書かれていた合理的配慮の例と、それをどう読み解けばよいかについて紹介します。
通院配慮:定期通院のための勤務時間調整が可能
通院が必要な方にとって、「通院配慮あり」という記載があるかどうかは非常に重要なポイントです。これは、精神科や心療内科、カウンセリングなど、定期的な医療機関への通院が就業時間と重なりがちな人にとって、業務を安定して継続するための土台となる配慮です。
通院配慮付き求人で見られる例とチェックポイント
通院配慮がある求人では、たとえば以下のような記載が見られます:
* 「月1〜2回の定期通院に伴う勤務時間調整可」
* 「午前休または午後半休取得が柔軟に可能」
* 「主治医の診断書に基づいた勤務調整に対応」
こうした文言が求人票に明記されていれば、その企業は通院を前提とした勤務調整に慣れている可能性が高く、精神障害のある方にとって働きやすい環境が整っていると判断できます。チェックポイントとしては、「具体的な頻度・時間帯への言及があるか」「医師の診断に基づく調整と明記されているか」「実績として配慮を受けている社員の有無を確認できるか」などが挙げられます。
dodaチャレンジやatGPでは、こうした求人の背景情報を事前に確認し、求職者に合わせた配慮内容があるかをヒアリングのうえで紹介してもらえるため、不安なく応募しやすい体制が整っています。求人の文言だけに頼らず、必要に応じて支援員やエージェントに確認してもらうことも、安心して就職先を選ぶための賢い手段です。
| 項目 | 求人に書かれている内容 | 応募前に確認したいこと | 活用のコツ |
| 配慮例 | 「通院に合わせた勤務時間調整可」 | 勤務日の振替や有給との組み合わせは可能か | 通院の頻度と曜日を整理しておく |
| 配慮される背景 | 通院頻度が高い人材を前提に設計されている | 何時までに出社・何時に退社OKかを確認 | 面接で率直に相談しやすくなる |
| メリット | 継続通院と就労が両立しやすい | 無理に隠さなくて良い | 体調安定に繋がる環境になる |
業務配慮:入力業務中心/対人対応なしなどの選択肢がある
精神障害や発達障害のある方にとって、「どんな業務を任されるか」は働き続けるうえでの大きなポイントです。特に注意が必要なのは、自分の苦手とする業務(たとえば電話応対、マルチタスク、人前での発表など)が日常的に含まれているかどうかです。求人票に業務配慮の有無が記載されていれば、応募前に「自分に合うかどうか」を判断しやすくなります。
実際の求人では「PC入力中心」「電話応対なし」「対人対応少なめ」といった業務配慮の記載がある場合、その企業はすでに障害者雇用の実績があり、特性に応じた業務設計に慣れている可能性が高いと考えられます。こうした業務内容は、集中力を活かせる特性を持つ方や、感覚過敏・不安障害などにより対人場面でのストレスが大きい方にとって、安定した就労に結びつくケースが多く見られます。
業務配慮あり求人の特徴と実際の職種例
業務配慮がある求人の特徴は、「業務範囲が明確で、変更が少ない」「マニュアル化されていて対応に迷わない」「周囲と頻繁なコミュニケーションを取らなくても完結できる」などが挙げられます。また、業務の進捗確認が定期的に支援員や上司と行われる仕組みがあれば、不安やトラブルも未然に防ぐことができます。
これらの職種は、ココルポートやミラトレ、atGPジョブトレといった就労移行支援事業所の実習先としても提供されており、利用者が「本当に自分に合うか」を体験しながら選ぶことができるようになっています。
また、manabyのようなオンライン型支援では、事務職に必要なスキル(Word、Excel、ビジネスメールなど)を自宅で習得しながら、実際の業務配慮のある求人へとつなげることが可能です。
求人を選ぶ際には、「自分の苦手が回避できるか」だけでなく、「得意な部分が活かせるか」も大切です。業務配慮のある求人は、そうした自己理解を前提に働ける環境を提供してくれる可能性が高いため、積極的にチェックしていきましょう。配慮を受けながら働くことで、徐々に自信を取り戻し、将来的なステップアップにもつながります。
| 配慮対象 | 内容 | 向いている特性 | 実際の職種例 |
| 対人ストレス | 「接客なし/電話対応なし」 | 対人コミュニケーションに不安がある人 | データ入力/在宅ライター |
| 複数タスク困難 | 「業務内容を分割/担当業務固定」 | マルチタスクが苦手な人 | 経理補助/事務作業 |
| ストレス低減 | 「ルーチンワーク中心」 | 変化が苦手な人 | 梱包・検品・清掃など |
環境配慮:照明・音・席配置に配慮ありと明記
精神障害や発達障害のある方の中には、感覚過敏や集中困難などの理由から、職場環境そのものが大きなストレス要因となることがあります。そのため、業務内容だけでなく「どんな空間で働くか」も就職先を選ぶうえで非常に重要な視点です。最近では、感覚過敏や疲労のコントロールに配慮した職場づくりを意識する企業が増えており、「照明の種類」「音の大きさ」「席の配置」などに柔軟な対応をしている職場が登場しています。
求人票に「環境配慮あり」と書かれている場合、たとえば「自然光を活かした照明環境」「パーテーションで仕切られた個別ブースあり」「私語が少ない職場」「静かなBGM環境」「イヤーマフなどの支給可」など、具体的な工夫があると、実際の働きやすさにもつながりやすくなります。こうした記載がある求人は、単に制度上の配慮ではなく、現場レベルでの対応が期待できるポイントになります。
環境配慮付き職場のチェックポイント
環境配慮が実際に機能しているかを確認するためには、求人票の文言だけでなく、以下のようなポイントをチェックすることが効果的です。
まず、「どのような環境配慮をしているか」が具体的に書かれているかどうかを確認します。たとえば、「集中しやすい静かな環境」「フロア内の照明調整が可能」「必要に応じて個別ブースを用意」といった記載があれば、企業側が感覚面の特性に理解があると判断しやすくなります。逆に、単に「配慮あり」だけでは曖昧なため、実際の職場見学やエージェントを通じた詳細確認が必要です。
次に重要なのは、「自分にとってどのような環境がストレスになるのか」を明確にしておくことです。光に敏感な方であれば「間接照明が望ましい」、音が気になる方であれば「フロア内での私語や電話が少ないこと」など、自分なりの快適な環境条件を言語化しておくことで、事前に相談しやすくなります。
LITALICOワークスやキズキビジネスカレッジなどの支援事業所では、実際の訓練室でも照明や音に配慮した設計が取り入れられており、利用者自身が「どうすれば集中できるか」「どんな環境が合っているか」を体験的に理解する機会が用意されています。また、企業見学時に支援員が同席し、本人では聞きづらい環境面の確認を代わりに行ってくれるなどの支援もあります。
環境配慮は、日々の疲労の蓄積やストレスを軽減し、働き続けるうえでの「見えない支え」になります。求人を選ぶ際には「業務内容」だけでなく「職場環境」も重視し、自分に合った空間で働けるかどうかをしっかり確認することが、安定した就労につながります。
| 環境要素 | 配慮例 | どんな人に向いているか | 求人で確認すべきこと |
| 音 | イヤーマフOK/電話音が少ない部署 | 音過敏・集中力が削がれる人 | フロア配置・個別スペース有無 |
| 光 | 間接照明/明るさ調整あり | 光に敏感な人/疲れやすい人 | 作業エリアの光環境に関する説明 |
| 匂い・空気 | アロマなし/換気対応 | 匂い過敏/呼吸器に配慮が必要な人 | 換気頻度/喫煙エリアとの距離 |
柔軟勤務:在宅勤務/時短勤務が初期から選べる
精神障害や発達障害を抱える方にとって、体調の波やストレス耐性に合わせて働き方を調整できるかどうかは、就職先を選ぶ上で非常に重要なポイントです。近年は、企業側でも柔軟な働き方を導入する動きが広がっており、「在宅勤務可」「時短勤務可」などを初期段階から選べる求人も増えてきました。これにより、フルタイム勤務や出社前提の職場に不安を感じていた方でも、無理なく働き始めることが可能になっています。
特に「週3日から勤務OK」「1日4時間からスタート」「最初は在宅勤務で慣れてから通勤に切り替え」など、段階的にステップアップできる求人もあり、働くことに自信が持てない人でも挑戦しやすい仕組みが整いつつあります。こうした柔軟勤務を前提とした求人は、合理的配慮のひとつとして認識されており、本人の希望に応じた働き方を企業と一緒に調整していくことが可能です。
柔軟勤務OK求人の働き方パターンと特徴
柔軟勤務が可能な求人には、いくつかの代表的なパターンがあります。
**1. 在宅勤務中心の働き方**
在宅勤務が可能な求人では、自宅のPCから業務を行い、週1回だけの出社や、フルリモート対応のケースもあります。manabyのようなオンライン支援型事業所で就労準備をしていた方にとって、スムーズに働き始められる環境です。在宅勤務は、通勤の負担をなくすだけでなく、自分のペースで業務に集中できるという利点があります。
**2. 時短勤務・短日勤務**
「週3日・1日4時間勤務からスタート可」「午後から勤務OK」など、勤務時間に柔軟性をもたせている企業もあります。特に通院がある場合や、朝の体調に波がある方にとっては、こうした働き方が現実的で続けやすい選択肢になります。キズキビジネスカレッジやココルポートなどの事業所では、就職先との交渉を含めてこうした働き方の導入を支援しています。
**3. ステップアップ型勤務**
「まずは週2日短時間勤務で慣れてから、少しずつ日数や時間を増やす」というように、段階的に勤務を増やしていける企業もあります。これは、体力や集中力に不安がある方にとって、非常に実践的な配慮であり、就職に対する心理的なハードルを下げてくれます。
dodaチャレンジやatGPといった転職エージェントでは、こうした柔軟な働き方が可能な求人を個別に紹介してもらえるため、「どんな勤務スタイルが可能なのか」「自分に合う条件かどうか」を相談しながら探すことができます。
柔軟な勤務形態は、「働くことを続ける」ための工夫でもあります。無理なく、自分のペースに合わせて仕事を始めたいと考えている方にとって、こうした求人をしっかり見極めることが、長く働ける職場と出会うための第一歩になります。
| 柔軟性の種類 | 対応例 | 向いている人 | 注意点 |
| 在宅勤務 | 「フルリモート・週2〜3在宅」など | 通勤ストレスが大きい人/通院が多い人 | 業務報告・ツール使用ルールの確認 |
| 時短勤務 | 「週3〜/1日4時間〜可」など | 体力・集中力に限界がある人 | 希望時間と実労働条件のすり合わせ |
| フレックスタイム | 「コアタイムなし」「10〜17時の間で調整可」 | 朝が苦手な人/波がある人 | 業務のタイミングが合うか確認 |
合理的配慮付き求人の探し方|見逃さない3つのコツ
合理的配慮がしっかりある求人を見つけるには、単に「障害者雇用」と書かれた求人を探すだけでは不十分です。自分に合った働きやすい職場を選ぶためには、求人票に記載された内容を注意深く読み取る力と、必要であれば支援機関を通じて企業の実情を確認する姿勢が求められます。特に精神障害や発達障害のある方にとっては、職場環境や業務内容、勤務条件における細かな配慮が就労継続のカギとなるため、「どの求人を選ぶか」で将来が大きく変わることもあるのです。
dodaチャレンジやatGPなどの専門エージェント、またLITALICOワークスやココルポートのような就労移行支援事業所では、求人票に書かれていない配慮の詳細を確認できることが強みです。こうしたサービスを活用しながら、自分にとって必要な配慮が受けられる求人を、丁寧に選んでいくことが大切です。
① 求人票に「具体的配慮内容」が書いてあるかを見る
まずチェックしたいのが、求人票に「どのような配慮があるのか」が明文化されているかどうかです。合理的配慮がある職場であっても、求人票にその内容がまったく書かれていない場合、自分にとって必要な支援があるのか判断できません。逆に、具体的な記載がある求人は、企業が配慮の必要性を理解し、障害者雇用に前向きに取り組んでいる可能性が高いと考えられます。
たとえば「通院配慮あり」「静かな作業スペースあり」「週3日勤務から応相談」など、明確な表現がされていれば、それだけで安心材料になります。求人票の文言をしっかり読み取る習慣をつけましょう。
求人票で確認したい「具体的配慮内容」のチェックリスト
求人票を読む際には、以下のような具体的な表現があるかを確認することで、その企業がどこまで合理的配慮に対応しているかを見極めやすくなります。
* **勤務時間の調整について**:「時短勤務可能」「午前のみ・午後のみ勤務OK」「週3日から応相談」
* **通院配慮について**:「定期通院に配慮」「診断書に基づき勤務調整」
* **業務内容について**:「入力作業中心」「電話応対なし」「単純作業メイン」
* **環境配慮について**:「照明や音への配慮可」「パーティションあり」「静かな作業スペース完備」
* **コミュニケーション配慮について**:「定期的な1on1面談あり」「指示は書面・チャット対応可能」
* **就労支援との連携について**:「就労移行支援との連携実績あり」「職場定着支援実施中」
求人票にこうした表現があるかどうかをチェックし、不明な点はエージェントや支援員を通じて企業に確認してもらうのが安心です。特に精神的な負担を感じやすい方にとっては、事前に業務内容や職場環境が自分に合っているかを見極めておくことが、長期就労の土台をつくる第一歩になります。
合理的配慮は「特別扱い」ではなく、「平等に働くための仕組み」です。その制度がどのように運用されているかを求人票から見抜く目を養いましょう。
| 項目 | チェック内容 | 見落としやすいポイント | 読み解きのヒント |
| 通院・体調配慮 | 勤務時間変更/欠勤制度の明記 | 「相談可」だけでは曖昧 | 「午前通院」「短時間勤務」など具体例の有無 |
| 作業環境 | 音・照明・席配置の記述 | 「配慮あり」だけでは詳細不明 | 実際に何に配慮しているか明記されているか |
| 業務内容 | 「電話なし」「作業固定」など | 実際に配属される業務の確認が必要 | 決まった作業内容かどうかをチェック |
② 企業名で口コミ検索する(実際に配慮されているか)
求人票に「配慮あり」と書かれていても、実際にどの程度の支援や対応がされているかは働いてみないとわからないという不安を感じる方も多いのではないでしょうか。そんなときに役立つのが、企業名での口コミ検索です。実際にその企業で働いた経験がある人の声を確認することで、「本当に配慮があるのか」「建前だけで実際は支援が不十分だったのか」といったリアルな職場の様子を把握することができます。
特に精神障害や発達障害のある方にとって、「上司や同僚の理解があったか」「職場の雰囲気は落ち着いていたか」「通院や体調不良への対応は柔軟だったか」といった要素は、求人票だけでは見えてこない重要な判断材料です。そうした“実態”を知るうえで、口コミサイトやSNS、匿名掲示板などの情報は貴重なヒントになります。
口コミや評判で「実際の配慮」がわかる検索方法
口コミ検索をするときは、以下のような具体的なキーワードを組み合わせると、より的確な情報にたどりつきやすくなります。
* 「企業名+障害者雇用+口コミ」
* 「企業名+合理的配慮+実際」
* 「企業名+就労支援+評判」
* 「企業名+働きやすさ+精神」
たとえば「〇〇株式会社 障害者雇用 口コミ」で検索すると、転職系掲示板やレビューサイトに実際の体験談が掲載されていることがあります。口コミが見つからない場合は、dodaチャレンジやatGPなどのエージェントに相談して、過去の支援実績をもとにした企業の実態を教えてもらうのも有効です。
また、就労移行支援事業所を利用している場合、支援員が過去にその企業へ利用者を送り出した実績があれば、実際の職場環境や配慮の実態を教えてもらえるケースもあります。たとえばLITALICOワークスやキズキビジネスカレッジ、ココルポートなどでは、支援の一環として職場見学や事前の職場情報提供を行っており、口コミ以上に信頼できる情報が得られることもあります。
求人票の情報だけではわからない部分こそ、第三者のリアルな声や支援者からの情報を組み合わせることで、安心して応募できる企業かどうかを見極めることができます。信頼できる情報源をうまく活用しながら、自分にとって本当に配慮のある職場を見つけるための判断材料を増やしていきましょう。
| 調べ方 | 使用するサイト | 見るべき情報 | 判断基準 |
| 企業名+障害者雇用 | Google/Yahoo | 経験者の体験談/働きやすさ | 評価が具体的かどうか |
| 就職支援口コミサイト | atGP・LITALICO仕事ナビ | 支援を受けた上での実体験 | 支援員の同行など詳細があると信頼性高い |
| SNS(Twitterなど) | #障害者雇用/会社名検索 | 現在の職場環境の声 | 継続的な投稿で信ぴょう性を判断 |
③ 面接時に「想定されている配慮内容」について質問する
求人票や口コミ、支援者の情報を通じてある程度の見極めはできても、最終的に「この企業は自分に合っているか」を判断するには、やはり面接の場で直接確かめることが大切です。特に精神障害や発達障害がある場合、自分にとって必要な配慮が実際に提供されるかどうかを確認することは、安心して働くうえで欠かせないステップとなります。
面接時に配慮の話を切り出すことに不安を感じる方もいますが、合理的配慮は“わがまま”ではなく、“働くために必要な調整”です。むしろ事前にきちんと伝えることで、入社後のミスマッチや早期離職を防ぐことにもつながります。採用担当者にとっても、応募者が自己理解と意欲を持っていることが伝わるため、誠実な姿勢として受け止められることが多いです。
面接時に聞くべき「配慮内容」の質問例とコツ
面接で合理的配慮について尋ねる際は、「自分の特性に対してどんな支援があるか」を具体的に聞くことがポイントです。以下に質問例と、その聞き方のコツを紹介します。
【質問例】
* 「通院が月に1回ありますが、勤務調整は可能でしょうか」
* 「静かな作業環境での業務を希望していますが、座席の配慮はいただけますか」
* 「マルチタスクが苦手で、業務の優先順位を明確にしていただけると助かります。そういった指示の工夫は可能でしょうか」
* 「過去に障害者雇用で配慮を提供した実績について、具体的にお聞かせいただけますか」
* 「入社後に状況が変わった場合も、配慮の内容を相談することは可能でしょうか」
【質問のコツ】
1. **“お願い”より“相談”の姿勢を意識する**
「〜してもらえますか」より「〜といった配慮があると働きやすいのですが、ご相談可能でしょうか」と伝えると、印象が柔らかくなります。
2. **具体的な希望を伝える**
「配慮がほしい」だけではなく、「どのような場面で、何が苦手で、何があれば安心か」を言葉にすることで、企業も対応しやすくなります。
3. **支援者の同行を活用する**
就労移行支援やエージェントを通じて応募する場合は、面接に支援者が同席してくれることもあります。自分でうまく伝えられない部分は、支援者に補足してもらうのも一つの方法です。
atGPジョブトレやココルポート、キズキビジネスカレッジなどでは、模擬面接や事前相談を通じて、こうした配慮の伝え方を練習する機会も用意されています。事前準備をしっかりして臨むことで、面接がただの評価の場ではなく、「お互いに理解し合う対話の場」になるのです。
働き始めてから「こんなはずじゃなかった」とならないためにも、面接の段階でしっかりと配慮の中身を確認することは、未来の自分を守る大切な行動です。勇気を持って聞くことが、納得できる就職につながります。
| 配慮項目 | 質問例 | 伝える意図 | うまく伝えるコツ |
| 勤務時間調整 | 「通院があるのですが、勤務時間の調整は可能ですか?」 | 継続的に働ける前提を提示 | “希望”ではなく“必要条件”として話す |
| 業務内容の固定 | 「得意分野に業務を集中させる配慮は可能ですか?」 | 配属のミスマッチ防止 | “職場に貢献するために”という前置きを添える |
| 環境配慮 | 「静かな場所で働けるような配慮はありますか?」 | 作業効率に直結するため | “集中力が上がるため”という効果を伝える |
合理的配慮を受けて働くリアルな働き方事例
合理的配慮は「制度」ではありますが、実際の職場でどのように活かされているかは人それぞれです。制度として存在していても、本人の希望や企業側の理解度によって、配慮の内容や形は変わってきます。ここでは、実際に合理的配慮を受けながら働いている人たちの事例を紹介します。とくに「在宅勤務」や「通院配慮」「業務内容の調整」など、働くうえで不安を感じやすいポイントに対して、どのような支援があったのかを具体的に知ることで、自分の働き方を考えるヒントにもなるでしょう。
就労移行支援事業所やエージェントを通じて就職した方々の中には、入社前から配慮内容を整理し、企業と連携しながら無理のない形で働き続けているケースが数多くあります。ここでは、その中から「在宅勤務」を中心にした事例を取り上げて紹介します。
在宅勤務で働けた人の声:体調に合わせて業務ができた
精神障害のあるAさん(30代・女性)は、外出や人との接触に強い不安を抱えており、フルタイムの出社勤務に大きな負担を感じていました。過去には、勤務初日から緊張が続き、数日で体調を崩してしまうということもあったそうです。しかし、dodaチャレンジを通じて「在宅勤務可」の求人に出会い、面接時から自分の特性と希望を正直に伝えたことで、フルリモートでの勤務が認められました。
在宅勤務では、朝の体調に応じて始業時間を調整できる日もあり、必要に応じて1時間程度の中断も相談の上で可能でした。さらに、日々の業務もチャットでやり取りされ、会議も最小限に抑えられていたため、Aさんは落ち着いた環境で集中して仕事に取り組むことができました。こうした配慮があったことで、これまで続かなかった仕事を半年以上継続できるようになり、業務の成果も安定して評価されています。
在宅勤務で配慮を受けた人の働き方ビフォーアフター
Aさんの働き方は、支援を受ける前と後で大きく変わりました。
**ビフォー(支援前)**
・フルタイム勤務に不安があり、就職活動が進まなかった
・面接でうまく話せず、自分の特性を説明することも難しかった
・通勤ストレスで体調を崩し、就業が長続きしなかった
**アフター(在宅勤務導入後)**
・在宅勤務を前提に応募、勤務開始前に業務内容やスケジュールを事前調整
・支援員の同行面接で配慮内容を明確に伝えることができた
・ストレス要因が減り、無理なく日々の業務に取り組めるようになった
このように、「働き方の選択肢」があるだけで、精神的な負担が大きく軽減され、自信を持って仕事に向き合えるようになったという声は多く聞かれます。就労移行支援事業所のmanabyや、オンライン支援を提供するatGPジョブトレ オンラインなどでも、自宅で働くための準備や訓練、企業との調整支援が整っており、自分の生活スタイルに合った働き方を現実にできるサポートが受けられます。
働きたいという気持ちがあっても、無理な環境では続けることができません。合理的配慮を上手に活用することで、自分らしい働き方を実現した人たちの事例から、あなた自身の働き方も見つけていけるはずです。
| 状況 | 在宅勤務前 | 在宅勤務後 | 感じた変化 |
| 通勤 | 朝の満員電車で体調が悪化 | 通勤不要で体調安定 | 朝の不安感がなくなった |
| 作業環境 | 職場の音・匂いで集中困難 | 静かな自宅で作業 | ミスが減り自信がついた |
| 仕事の進め方 | 時間管理に苦労 | 自分のペースで集中 | ストレスが軽減され継続できた |
時短勤務で復職できた例:通勤・業務負担が軽減された
精神障害や発達障害のある方の中には、いったん離職を経験したあと、もう一度働きたいという気持ちはあっても、「フルタイムでまた働けるだろうか」という不安を抱えている方も多くいます。そんな中で、時短勤務という選択肢は、復職の第一歩として非常に有効です。実際に、働く時間をあらかじめ短く設定することで、通勤や業務の負担を軽減しながら、無理なく仕事に慣れていくことができたというケースが多く報告されています。
たとえば、精神疾患による長期休職を経験したBさん(40代・男性)は、回復後もフルタイム勤務に戻ることに大きな不安を感じていました。しかし、atGPのエージェントを通じて「時短勤務OK」の求人に出会い、週5日・1日4時間からスタートできる業務に応募。職場側との調整によって、最初は午前中だけの勤務から始めることができました。
勤務時間が短いことで体力の消耗が抑えられ、帰宅後も疲れすぎることなく生活リズムを維持できたことが、職場復帰の成功につながりました。短時間であっても安定して出勤することが評価され、半年後には少しずつ勤務時間を延ばすことも可能になったそうです。
時短勤務で復職できたケースの要点
このような時短勤務を活用した復職の成功には、いくつかの重要なポイントがあります。
**1. 最初から無理をしないスタートが可能**
復職直後にフルタイムを求められると、心身ともに大きな負担になります。最初から短時間勤務が認められていることで、「慣れていく」プロセスを大切にできました。
**2. 通院や体調の波に対応しやすい**
Bさんは通院治療も続けていたため、午前勤務のみとすることで午後に医療機関へ行ける時間が確保され、仕事と治療の両立ができました。
**3. 業務内容も配慮されていた**
最初の数ヶ月は、定型的なデータ入力や文書チェックといったシンプルな作業に絞られており、精神的な負荷を抑えた業務内容となっていました。
**4. 周囲の理解と定期的なフォローがあった**
エージェントや就労移行支援事業所が企業と定期的に連絡を取り合っていたことで、本人に無理がかからないよう調整が続けられた点も成功の鍵です。たとえば、ココルポートやキズキビジネスカレッジでは、復職後も支援員が定着支援を行い、働き続けるサポート体制が整っています。
このように、時短勤務は「少しずつ仕事に慣れる」「生活リズムを整える」「復職に対する不安を軽減する」といった意味で非常に有効な働き方です。合理的配慮として、勤務時間の柔軟性をあらかじめ交渉・設定できる求人を選ぶことが、復職や再スタートを安心して踏み出すための現実的な選択肢になるでしょう。支援機関を通じて丁寧に調整していくことで、自分に合ったペースで社会復帰することは十分に可能です。
| 復職前の課題 | 採用された配慮 | 取り入れた工夫 | 安定して働けた理由 |
| 通勤+フルタイム勤務が難しい | 週3・1日5時間勤務からスタート | 朝の準備時間に余裕を持った | 無理をせず段階的に体を慣らせた |
| 職場の雑音で集中できない | 個別ブースでの作業 | ノイズキャンセリングの活用 | 配慮のある環境で安心して働けた |
配慮内容が明記された契約で長く働けたケースも
精神障害や発達障害のある方にとって、「配慮は口約束ではなく、契約に明記しておくこと」が働きやすさの安定につながります。就職活動の場で企業側が配慮を口頭で伝えてくれることはありますが、実際に職場でその配慮が継続されるかどうかは、契約内容に記載されているかどうかが鍵になります。配慮があいまいなまま就業すると、異動や上司の交代といった環境の変化により、急に理解や対応が得られなくなるリスクもあるため注意が必要です。
実際に、契約書に配慮内容を記載することで長期的に安定就労を続けられた事例もあります。Cさん(30代・女性)は、ASDの診断を受けており、対人対応に強い苦手意識がありました。応募時に「電話応対なし」「座席位置の固定」「在宅勤務可」の配慮を希望し、面接で具体的に伝えた上で、これらの内容を雇用契約書に明記してもらいました。
契約書に配慮内容が書かれていたことで得られた効果
Cさんのケースから見えてくるのは、配慮内容を明文化することによる以下のような効果です。
**1. 環境が変わっても配慮が継続される**
たとえば上司が変わったり、業務チームが変わった場合でも、契約書に記載された配慮事項がベースになっているため、新しい担当者にも確実に共有されました。これにより、業務内容や職場環境が一貫して安定し、ストレスの少ない就労が継続できました。
**2. 配慮の「範囲」と「内容」が明確になった**
「できること」と「できないこと」をはっきり言葉にして記載したことで、周囲との認識のズレが起きにくくなり、自分自身も安心して働くことができました。例:「通院のため週1回は15時退勤可」「業務連絡はチャットメインでOK」など。
**3. 本人の安心材料となり、自己肯定感が高まった**
「自分の特性を理解してもらえた」「書面に残してもらえた」という経験が、Cさんにとって大きな安心材料になり、毎日の仕事への自信と安定につながりました。
こうした契約への明記は、atGPジョブトレやdodaチャレンジなどの支援機関を通じた場合、企業との間で支援員が橋渡しをしてくれるためスムーズです。ココルポートやLITALICOワークスなどの就労移行支援でも、面接同行時や内定後の雇用条件のすり合わせの段階で、配慮内容を文章化するサポートを受けることができます。
合理的配慮は、“制度として存在すること”以上に、“具体的にどのように反映されるか”が重要です。そして、その反映を確かなものにするには、契約書や雇用条件通知書への明記が最も効果的な方法です。長く働きたいと考えるなら、「配慮内容は最初に言葉にし、書面に残す」ことを忘れないようにしましょう。
| 記載内容 | なぜ書いてもらったか | 実際の効果 | 書面化してよかった点 |
| 通院時間の確保 | 口約束では不安だった | 通院日はシフト固定 | 替えが効かない条件として認められた |
| 業務範囲の限定 | 過去に配属ミスマッチがあった | 得意な作業だけに集中できた | 適性に合った仕事で成果が出せた |
| フレックスタイム利用可 | 朝が苦手な特性がある | 10時出社で体調が安定 | 生産性と定着率が上がった |
求人に応募する前に|職務経歴書で配慮を伝えるコツ
精神障害や発達障害のある方が求人に応募する際、「自分に合った働き方ができるかどうか」を企業に理解してもらうためには、職務経歴書での伝え方が大切なポイントになります。とくに配慮を求める必要がある場合は、職務経歴書の中に「できること」と「必要な配慮」の両方をバランスよく記載することで、企業側に前向きな印象を持ってもらいやすくなります。
合理的配慮の申請は、本来であれば面接時や採用後にも行えますが、応募の段階である程度の配慮希望を示しておくことで、ミスマッチを防ぎ、スムーズな選考につながることが多いです。企業もあらかじめ特性を把握していれば、業務内容や配置、人間関係への配慮を事前に検討しやすくなります。
「できること」と「必要な配慮」を併記するスタイル
配慮の伝え方で効果的なのが、「できる業務内容やスキル」を前提にしたうえで、「その業務を継続するために必要な配慮」を記載するスタイルです。これは、単なる要望や制限に聞こえるのを避け、「働き続けるための具体的な工夫」として伝えることができる表現方法です。
| セクション | 記載例 | ポイント | 伝わる印象 |
| 実績 | 「事務処理月200件、誤記率0.5%」 | 強みを数字で見せる | 実務力が明確に伝わる |
| 得意分野 | 「ルーチン作業や集中力を要する業務に強みあり」 | 自分の“使いどころ”を提示 | 配属ミスを避けられる |
| 配慮希望 | 「通院対応が可能な勤務体制を希望」 | 働くために必要な前提を伝える | 無理を避けつつ誠実さを演出 |
無料テンプレートを使って、スムーズに情報整理
自分に必要な配慮や得意・不得意を整理して、職務経歴書に落とし込む作業は簡単ではありません。特に精神障害や発達障害がある方にとっては、「何をどこまで書いていいのか」「ネガティブに受け取られないだろうか」と悩みやすいポイントでもあります。そこで有効なのが、就労支援機関などが提供している無料の自己分析テンプレートや、配慮事項整理シートを活用することです。これらを使えば、あらかじめ用意された項目に沿って記入していくだけで、自分の状況や希望をスムーズに言語化できます。
たとえばmanabyやLITALICOワークス、ココルポートでは、配慮内容や希望条件を整理するための独自のワークシートやヒアリングシートが用意されており、支援員のアドバイスを受けながら記入できます。自分ひとりでは気づきにくい「働きづらさの原因」や「工夫してうまくいった経験」を言葉にする手助けにもなり、就職活動全体がぐっと進めやすくなります。
無料テンプレートを活用した情報整理の実例
たとえば、ある利用者Dさん(20代・男性・ADHD)は、頭の中で考えていた内容が整理できず、支援員から配慮事項の記述があいまいだと指摘されていました。しかし、manabyの支援員が提供する「配慮内容整理シート」を使い、「業務上不安な場面」「過去に困った経験」「それをどう乗り越えたか」という観点で具体的に記入していくことで、自分でも驚くほど整理が進んだそうです。
| 活用ツール | 使用した目的 | 記入した項目 | 効果 |
| 職務経歴書テンプレート | 配慮事項と実績の同時整理 | 実績・得意業務・配慮要望 | 書類作成の時短+自己理解が深まった |
| 面接準備シート | 質問対策と伝える内容整理 | 想定問答・伝える順番 | 自信を持って話せるようになった |
| 配慮チェックリスト | 面接前の確認用 | 配慮項目・優先度・例文 | 忘れず伝えられてミスマッチ回避 |
働きずらさを感じている人におすすめの転職サービス
dodaチャレンジ|ストレスを減らせる環境を一緒に考えてくれる
→dodaチャレンジ アフィリリンクを貼る
関連ページはこちら:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
LITALICOワークス|働く前に心の準備ができる就労支援
→LITALICOワークス アフィリリンクを貼る
ランスタッド|大手だから安心して相談できる環境がある
→ランスタッド アフィリリンクを貼る
atGP|理解ある職場紹介で再出発を後押ししてくれる
→atGP アフィリリンクを貼る
ミラトレ|小さな練習から始められる就労移行支援サービス
→ミラトレ アフィリリンクを貼る
【まとめ】合理的配慮 求人 例|“働きやすい環境”は、選ぶ段階から始まっている
精神障害や発達障害がある方にとって、安心して長く働くためには、「どの職場を選ぶか」が何よりも大切です。そしてその選び方には、合理的配慮の有無や中身をしっかり見極めることが欠かせません。求人票に具体的な配慮内容が書かれているかを確認し、企業の口コミを調べ、面接では配慮の内容を自分から質問する。この一連の流れが、自分に合った職場を見つけるための実践的な手段となります。
さらに、職務経歴書で「できること」と「必要な配慮」をバランスよく伝え、配慮内容を契約書に明記することができれば、入社後のミスマッチを減らすことができます。また、在宅勤務や時短勤務など、柔軟な働き方を選べる求人も増えており、自分の体調や生活スタイルに合った働き方を実現することが可能になってきています。
このように、合理的配慮は“制度”として存在するだけでなく、“どう活かすか”“どこで受けるか”を見極めることで、実際の働き方を大きく変える力を持っています。だからこそ、「働ける場所」を探す段階から、自分の特性と向き合い、選択の軸を持つことが必要なのです。
就労移行支援事業所や転職エージェントの活用、無料テンプレートによる情報整理など、支援を受けながら進めることで、無理なく、安心して、自分らしい働き方に一歩ずつ近づいていけます。「働きやすい環境」は、誰かが与えてくれるものではなく、自分で選び、つくっていくもの。その第一歩を、今日から始めてみましょう。
関連ページはこちら
配慮がある求人をもっと探したい方へ
自分に合った働きやすい求人を見つけるための検索方法と判断ポイントを解説しています。
→関連ページはこちら【知らなきゃ損】障害者雇用の求人の探し方|理解ある職場に出会うための実践ガイド
通勤が負担な方のための働き方実例
在宅勤務を取り入れた転職成功談をもとに、配慮の実情を紹介しています。
→関連ページはこちら「在宅勤務 転職 体験談」へ内部リンク
無理なく働ける時間帯で求人を探したい方へ
時短勤務に対応した職場の探し方や面接時の伝え方を紹介しています。
→関連ページはこちら「時短勤務 可能 職場 探し方」へ内部リンク
応募書類にも配慮の工夫を加えたい方へ
配慮希望がスムーズに伝わる職務経歴書のテンプレートを無料で提供しています。
→関連ページはこちら「職務経歴書 テンプレート 無料」へ内部リンク
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
生活とお金に関するおすすめ情報まとめ(ドメイントップページ)を見る
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
厚生労働省「こころの健康」ページも参考になります

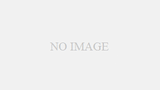
コメント