障害者雇用で働きたいけど「どこで探せばいいの?」という疑問に応える記事です
「障害者雇用で働きたい」と考えたとき、多くの方が最初につまずくのが「どこで求人を探せばいいのか」という疑問です。一般の求人サイトにも障害者枠の求人は掲載されていますが、情報が限られていたり、配慮の有無が分かりにくかったりといった問題があります。そこで注目されているのが、障害者に特化した転職支援サービスや就労移行支援事業所です。dodaチャレンジ、atGP、LITALICOワークス、ミラトレ、manaby、キズキビジネスカレッジなど、全国には多くの選択肢があり、それぞれが異なる支援内容や強みを持っています。これらのサービスでは、障害の特性に応じた職業訓練や面接対策、就職後の定着支援までを一貫してサポートしてくれるため、「自分に合った働き方を見つけたい」という方にとって心強い味方となります。この記事では、障害者雇用の基本から、就職先の探し方、実際の支援事例までを分かりやすくご紹介していきます。
そもそも障害者雇用ってどんな働き方?普通の求人と何が違うの?
障害者雇用とは、企業が障害のある方を雇用する際に、その特性に応じた合理的配慮を前提に採用し、働きやすい環境を提供する制度のことです。日本では、一定規模以上の企業に対して障害者の法定雇用率が定められており、その枠組みに則って雇用されるケースが多く見られます。一般の求人と最も大きく異なるのは、就労環境に「配慮」が組み込まれている点です。たとえば、体調に波がある人には時短勤務や在宅勤務が認められたり、発達障害のある人には明確な指示や静かな作業環境が用意されたりといった対応がなされます。こうした職場では、事前に障害の内容を開示するオープン就労が基本となるため、自身の特性や困りごとを理解してもらったうえで働くことができます。単に「仕事を得る」だけでなく、「長く働き続ける」ことを目指した支援が整っているのが、障害者雇用の大きな特徴と言えるでしょう。
障害者雇用は「配慮」があることが前提の職場
障害者雇用では「配慮」が制度的に前提となっており、これは大きな安心材料となります。多くの障害者雇用支援サービスでは、就職活動の段階から支援員が利用者に寄り添い、どんな配慮が必要なのかを一緒に整理してくれます。たとえば、manabyでは在宅でのトレーニングが可能で、自宅での仕事を希望する方にも対応しているのが特徴です。また、LITALICOワークスでは、体調の波や通勤の不安に配慮した職場実習を通じて、自分に合った働き方を見つけられるようサポートしています。一方で、dodaチャレンジなどのエージェント型サービスでは、非公開求人を含む多数の選択肢の中から、自分の希望に近い職場を紹介してもらえるため、安心して活動を進めることができます。こうした「配慮」の内容は、通勤時間や勤務時間の調整だけでなく、業務内容の選定や人間関係に対するサポートまで多岐にわたります。障害者雇用では、自分にとって働きやすい条件を事前に伝え、それを尊重してくれる体制が整っているため、「無理なく」「長く」働き続けるための第一歩として非常に有効です。
「配慮が前提」の職場とは?一般職場との違い
一般的な職場では、働く人が「健常者」であることを前提として業務や評価が構成されている場合が多く、自分の特性に合わない仕事や環境でも、我慢して働かなければならないことが少なくありません。しかし、「配慮が前提」の職場では、働く人の特性や体調、生活スタイルに合わせて業務が調整されます。たとえば、ココルポートでは600種類以上のプログラムを通じて、自分の障害特性を理解し、どんな配慮が必要かを言語化する訓練が行われています。また、キズキビジネスカレッジでは、発達障害やうつ病を抱える方を対象に、専門スキルを活かしたビジネススクール型の支援を実施しており、就職率は83%と高い実績を誇っています。このように、障害者雇用では「その人らしく働く」ことを大切にしており、配慮事項を事前に企業と共有することで、就職後のミスマッチを防ぎ、安定した職業生活を送りやすくなるのです。自分のことを理解し、尊重してくれる職場で働けるという安心感は、一般の職場にはない大きな魅力です。
| 項目 | 一般求人 | 障害者雇用枠 |
| 勤務時間 | フルタイム前提が多い | 時短・週3勤務など柔軟に相談可 |
| 仕事内容 | 幅広くマルチタスク要求されがち | 得意な分野を任されることが多い |
| 環境配慮 | 基本的に一般仕様 | 音・光・空間に配慮されている場合も |
| 上司との関係 | 評価・指導が中心 | 定期面談やフォロー制度があることも |
| 配慮の姿勢 | 自己申告が必要なことが多い | 最初から“配慮あり”として設計されている |
業務内容・勤務時間・通院配慮など、無理のない設計がされている
障害者雇用においては、本人の特性や健康状態に応じて、業務内容や勤務時間が無理のないように設計されています。たとえば、集中力が続きにくい方には短時間勤務や作業工程の分割、精神的な疲労を感じやすい方には静かな作業スペースの確保など、実際の職場ではさまざまな工夫がされています。また、定期的な通院が必要な方に対しては、診察日に合わせた勤務調整が可能な職場も多く見られます。就労移行支援の現場では、こうした配慮を事前に企業と調整する役割も担っており、たとえば「atGPジョブトレ」では障害ごとの専門コースを設けて、本人に合った働き方を一緒に模索していきます。このような配慮があることで、体調を崩すことなく、自分のペースで仕事を続けていくことができるのです。
障害者手帳が必要?応募条件や活用のポイント
障害者雇用枠で働くには、多くの場合「障害者手帳」の所持が求められます。これは、企業が障害者雇用促進法に基づく法定雇用率を満たすための要件であるとともに、配慮のある雇用条件で採用される根拠にもなります。ただし、すべての企業が手帳所持を必須としているわけではなく、一部には「申請中」や「取得予定」でも相談可能な求人も存在します。マイナビパートナーズやdodaチャレンジなどの専門エージェントでは、手帳の有無や種類に応じた求人提案を行っているため、自分の状況に合わせて利用するのがおすすめです。また、就労移行支援を利用しながら、申請手続きや手帳取得後の就職活動について相談できる場合もあります。まずは自分の障害区分と、どの雇用形態が合っているかを明確にしながら準備を進めることが重要です。
障害者手帳を使うとどうなる?応募前に知っておくこと
障害者手帳を活用して就職活動を行うことで、求人の選択肢が広がると同時に、企業側からの配慮や制度的な支援を受けやすくなります。たとえば、通院や体調管理に配慮された勤務スケジュール、静かな環境での作業、定期的な面談によるメンタルフォローなど、手帳を提示することで自分のニーズを正しく伝えられる土台が整います。また、企業は障害者雇用として雇った人材に対し、国からの助成金を受けることもあり、そのぶん支援体制も手厚くなる傾向があります。ただし、手帳を提示することで「業務の幅が限定されるのでは」と不安に思う方もいるかもしれません。ですが実際には、スキルや経験に応じた正社員登用やキャリア形成を進める事例も多く、キズキビジネスカレッジやココルポートなどの支援機関では、こうした疑問に対して個別に相談に応じています。応募の際には、自分に合った配慮内容を明確に伝えることが、より良いマッチングにつながります。
| 内容 | 手帳なしの場合 | 手帳ありで応募する場合 |
| 求人の選択肢 | 一般求人が中心 | 障害者枠の求人に応募可能 |
| 企業側の理解 | 一般対応。配慮に差がある | 初めから配慮前提のやり取り |
| 面接時の説明 | 配慮をお願いしづらい | 自分の特性を伝える機会がある |
| 書類の通過率 | 条件に合わないと厳しい | 手帳の提示で一定の理解を得やすい |
| 活用のポイント | 無理せず受ける範囲で挑戦 | “配慮されて当たり前”という安心感 |
業務内容・勤務時間・通院配慮など、無理のない設計がされている
障害者雇用の職場では、「働きたい気持ち」に寄り添いながら、無理のない形での就業設計がされています。具体的には、業務内容をあらかじめ明確にし、本人の得意・不得意を考慮した役割分担が行われることが一般的です。例えばパソコン作業が得意であれば、データ入力やメール対応など、比較的静かな環境でできる業務が割り当てられることがあります。また、勤務時間についてもフルタイムにこだわらず、週20時間や週3日勤務など、体力や体調に合わせた柔軟な調整が可能です。
さらに、定期的な通院や服薬が必要な方に対しては、勤務スケジュールの調整や急な体調不良時の対応策もあらかじめ想定されます。例えばココルポートでは、生活リズムや健康管理に重点を置いた支援を行っており、スタッフと相談しながらスケジュール調整をすることができます。このように、障害者雇用では安心して長く働けるように、働き方自体が最初から「配慮された設計」になっているのです。自分の状態を無理に押し殺すのではなく、ありのままの自分で働ける場を選ぶことができる点が大きな魅力です。
障害者手帳が必要?応募条件や活用のポイント
障害者雇用枠の求人に応募するには、原則として「障害者手帳」を持っていることが条件となります。手帳の種類には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があり、それぞれに応じた求人情報が提供されています。企業側はこの手帳によって「法定雇用率」の達成を目指すことができ、採用側・応募側の双方にとって制度的なメリットがあります。
しかし、手帳を取得したからといって自動的に就職が決まるわけではありません。求人の内容や企業の理解度、自身の準備状況に応じて、手帳をどう活用するかが重要になります。例えば、就労移行支援事業所「atGPジョブトレ」では、手帳を活用した就職活動の進め方や面接時の説明の仕方など、具体的なノウハウを提供しています。応募条件としての手帳はスタート地点にすぎず、実際の現場では自分に合った業務内容や職場環境を選び取るスキルも大切になります。適切な支援を受けることで、そのスキルは無理なく身につけられるでしょう。
障害者手帳を使うとどうなる?応募前に知っておくこと
障害者手帳を使って就職活動を行うと、いくつかの大きな利点があります。まず、企業が「障害者雇用枠」で募集している求人に応募できるようになり、一般枠とは異なる面接対応や職務配慮を受けることが可能です。たとえば、応募書類に記載することで、面接官があらかじめ配慮の必要性を理解した上で話を聞いてくれるケースが多くなります。また、採用後も「体調に応じた業務調整」や「障害特性をふまえた指導体制」など、職場での支援体制が整いやすくなります。
ただし、手帳を持っていることを必ずしもすぐに開示する必要はありません。企業によっては、応募時点では開示を求めず、内定後に確認するケースもあります。自分がどのタイミングで手帳の情報を伝えるかについても、事前に整理しておくことが大切です。また、就労移行支援事業所では、こうした場面に備えて模擬面接やエントリーシートの添削支援も行われています。たとえば「ミラトレ」では、実際の職場に近い環境で就労訓練ができるため、応募前の不安を軽減し、自信を持って面接に臨むことができるようになります。応募前に知識を深め、サポートを活用することで、安心して一歩を踏み出すことができるでしょう。
| ステップ | 内容 | 利用者の声 | 支援の効果 |
| 1.面談・登録 | 不安や希望をヒアリング | 「話すだけで気持ちが整理された」 | 自分の課題・強みが言語化できる |
| 2.通所開始 | 生活リズムやビジネスマナーの訓練 | 「毎日通う習慣がついた」 | 継続する力と自信がつく |
| 3.職場体験 | 実際の仕事を“試す”機会 | 「働けそうなイメージが湧いた」 | 働く前の“不安”が“実感”に変わる |
| 4.就職サポート | 面接練習・求人紹介・同行支援など | 「一人じゃ無理だったと思う」 | 実際の就職率が高い理由はここ |
等級や申請状況によって求人の選択肢が変わる場合も
障害者雇用における求人の選択肢は、障害者手帳の等級や申請状況によって変化する場合があります。たとえば、身体障害や精神障害の等級が軽度の場合は、フルタイムでの就労が可能な職場も選べる一方で、重度の場合は短時間勤務やサポートの手厚い職場が中心になる傾向があります。また、まだ手帳の申請中という段階では、「手帳が交付されてから応募可能」とする求人も多く存在します。企業にとっては法定雇用率のカウント対象となるかどうかが重要なため、応募条件に「手帳の交付を受けている方」と明記されていることが多いのです。このように、手帳の有無や等級は、応募できる求人の幅に直接関わってきます。就職活動を始める前に、自身の障害種別や等級、そしてどのような配慮が必要かを整理しておくと、マッチ度の高い職場を見つけやすくなります。「atGP」や「マイナビパートナーズ」などの専門支援サービスでは、こうした個別の条件に合った求人を紹介してくれるため、安心して相談できる環境が整っています。
障害者雇用の求人ってどこで探せばいい?安心できる方法とは
障害者雇用の求人を探すとき、もっとも安心して進められる方法のひとつが「障害者専門の転職支援サービス」や「就労移行支援事業所」を活用することです。一般の求人サイトにも障害者雇用枠はありますが、自分に合った職場を見つけるためには、障害の特性を理解している支援スタッフのサポートが非常に役立ちます。就労移行支援を利用すれば、職場探しから面接対策、応募書類の添削、入社後の定着支援までを一貫して受けられるため、一人で悩むことがぐっと減ります。たとえば「ココルポート」や「LITALICOワークス」では600種類以上の訓練プログラムや個別面談を通して、自己理解を深めながら無理なく就活を進めることができます。また、「ミラトレ」では模擬職場環境での訓練やコミュニケーショントレーニングを通して、自信をつけながら現場に近い経験を積むことができます。こうした専門機関は、求人探しに不安を感じる方にとって、非常に心強い存在となっています。
就労移行支援を利用して、プロと一緒に探す
就労移行支援は、障害のある方がスムーズに社会参加できるよう支援する福祉サービスであり、求人探しにおいても強い味方になります。支援員は福祉と就労支援の知識を持ち合わせており、利用者の障害特性や生活状況に応じて、就労に向けたプランを一緒に立ててくれます。例えば「atGPジョブトレ」では、発達障害・うつ・統合失調症など障害別にコースが用意されており、それぞれに特化したプログラムで就職準備が進められます。こうした支援は、一般的な職業訓練とは異なり、メンタル面のサポートや日常生活の整え方にも力を入れている点が特徴です。また、定期的に面談を行いながら進捗を確認することで、焦らず着実に目標に近づける点も安心材料となります。自分ひとりで求人を見つけるのが難しい、どこに応募すればよいかわからないといった不安を持つ方には、就労移行支援の活用が非常におすすめです。
就労移行支援を使った就活の流れと得られたこと
就労移行支援を使った就活の流れは、大きく「自己理解」「スキル習得」「職場体験」「求人応募」「職場定着」という段階に分かれます。最初に行われるのが、障害特性や生活リズム、体調の傾向などを明らかにするための自己分析です。たとえば「ココルポート」では生活チェックシートを使って日々の生活を振り返り、課題を整理する支援が行われています。そのうえで、SST(ソーシャルスキルトレーニング)やPCスキルなど、働くために必要なスキルを身につけていきます。次に職場体験や企業見学を通して、自分に合った職場かどうかを実際に体験することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。最後は、支援員のサポートのもとで求人に応募し、面接準備から職場への定着支援まで一貫してフォローされます。このプロセスを通じて、多くの利用者が「自分らしく働くための視点」と「社会とのつながり」を得られたと実感しています。初めての就職でも、一人ではなく専門家と一緒に進めることで、不安を軽減しながら着実にステップを踏むことができます。
“見つける”だけじゃなく“続けられる”職場を一緒に考えてくれる
障害者雇用において大切なのは、ただ就職することだけではなく、「いかに長く安定して働き続けられるか」という視点です。その点で、就労移行支援や専門エージェントの支援は非常に心強い存在です。たとえば「キズキビジネスカレッジ」では、発達障害やうつなどを抱える人たちが「もう一度働きたい」という気持ちに寄り添い、自己理解と適職選びをじっくりとサポートする体制が整えられています。また、「ココルポート」では、6か月定着率90%以上という実績があり、これは“続けられる職場探し”に注力している証でもあります。支援員は就職後も定期的にフォローアップを行い、職場での悩みや体調の変化に応じて対応策を考えてくれるため、一人で抱え込まずに済みます。このような支援を通じて、利用者は「職場とどう付き合うか」「自分のペースで働くとはどういうことか」を学び、より自立した就労生活を築くことができます。短期的な就職ではなく、長期的な「定着と成長」を見据えた支援を受けられることが、障害者専門の支援機関を利用する大きなメリットと言えるでしょう。
転職エージェントで非公開求人にアクセスする
障害者雇用に特化した転職エージェントを利用することで、一般の求人サイトには掲載されていない「非公開求人」にアクセスできるのも大きなメリットです。非公開求人とは、企業が特定の人材に絞って紹介を依頼している案件であり、条件が良かったり、職場環境が整っていたりするケースが多いのが特徴です。例えば「dodaチャレンジ」や「マイナビパートナーズ紹介」では、多くの非公開求人を保有しており、エージェントが一人ひとりの状況や希望をヒアリングした上で、相性のよい求人を提案してくれます。こうしたサービスでは、応募前に職場の雰囲気や受け入れ体制についての情報も共有してくれるため、入社後のギャップが少なくて済みます。さらに、面接対策や企業との調整も代行してくれるため、応募に伴う不安や負担を減らすことができます。求人の選択肢を広げたい、自分に合った職場をピンポイントで探したいという方にとって、転職エージェントの活用は非常に効果的な手段となります。就労移行支援と併用することで、就職前後のサポート体制をより手厚くすることも可能です。
障害者特化型エージェントのサービス比較
| サービス名 | 特徴 | 向いている人 | 利用者の声 |
| atGP | 配慮条件を丁寧にヒアリングし、求人を紹介 | 手厚いフォローを希望する人 | 「面接同行が安心できた」 |
| dodaチャレンジ | 精神・発達障害など幅広い対応実績あり | 大手企業を目指したい人 | 「求人の質が高かった」 |
| ランスタッド障害者支援 | 外資系・高年収求人あり | スキルを活かしたい人 | 「キャリア相談が役立った」 |
→ランスタッド アフィリリンクを貼る
atGPやdodaチャレンジなど、障害者特化型のサービスが多数
→dodaチャレンジ アフィリリンクを貼る
関連ページはこちら:「dodaチャレンジ 口コミ」へ内部リンク
→atGP アフィリリンクを貼る
ハローワークの専門窓口を活用する方法
障害者雇用の求人を探す際に、公的な支援機関である「ハローワーク」を利用するのも有力な選択肢のひとつです。特にハローワークには、障害者の就職支援に特化した「専門援助窓口(専門援助部門)」が設置されており、専門の職員(ジョブコーチや障害者支援担当)が個別に相談に乗ってくれます。この窓口では、障害特性に配慮した求人情報の提供だけでなく、職場実習のあっせん、履歴書の書き方や面接練習の支援、さらには企業との間に立って職場定着までサポートするケースもあります。自治体によっては、障害者向けの合同企業説明会や職業訓練などのプログラムを開催しているところもあり、地元での就職を考えている方にとっては非常に心強い存在です。さらに、ハローワークの利用は無料であり、情報の信頼性も高いため、初めての就活や転職を考える方にとって、最初の一歩として適しています。民間のエージェントや就労移行支援との併用も可能なため、自分の状況に応じて組み合わせると、より効率よく就職活動を進めることができます。
ハローワークの専門窓口を活用する際のポイント
ハローワークの障害者専門窓口を活用する際には、いくつか意識しておくとよいポイントがあります。まず重要なのは、自分の障害の内容や職場での配慮事項を具体的に伝えられるように準備しておくことです。障害名だけでなく、「長時間の集中が難しい」「通院で週に1日は早退が必要」「対人関係が不安なので静かな環境が望ましい」など、自分にとっての働きやすさを言語化できると、職員との情報共有がスムーズになります。また、ハローワークでは就職準備段階から就職後の職場定着までを継続的に支援してもらえるため、なるべく定期的に相談を重ね、状況の変化を都度伝えることも大切です。さらに、求人票だけでは読み取りにくい「実際の職場の雰囲気」や「障害への理解の度合い」については、担当者が企業と直接やり取りをしている場合が多く、参考になる情報を提供してくれます。自治体によっては、サポート体制や窓口の混雑状況が異なるため、事前に予約を取るとより丁寧な対応が受けられることもあります。ハローワークの強みは、公的機関ならではのネットワークと、地域に密着した支援体制にあります。こうした特徴を上手に活かしながら、自分に合った就職先を一緒に探していくことが可能です。
| 利用ステップ | 内容 | 知っておくべきこと | よくある疑問への答え |
| 窓口訪問 | 障害者専用窓口で受付 | 地域によって対応に差あり | 「予約なしでも行ける?」→OKだが事前電話が◎ |
| 面談 | 希望条件や障害の状況をヒアリング | 就労支援員がつく場合も | 「通院や配慮は話していい?」→話すことで合う求人に出会える |
| 求人検索 | 専用端末で検索可 | “非公開求人”がある場合も | 「ネットに出てない求人って?」→窓口だけの案件も多い |
| 職場見学・紹介 | 必要に応じて実施 | ハロワが橋渡しをしてくれる | 「職場見学はお願いできる?」→可能。積極的に相談を |
地域に根ざした求人や助成制度についても相談できる
ハローワークの障害者専門窓口を利用するもうひとつの大きなメリットは、その地域に特化した求人情報や支援制度についても詳しく相談できる点です。大都市圏だけでなく、地方都市や中小企業での障害者雇用も数多く取り扱っており、地域密着型の就職支援が可能です。たとえば「地元で通勤しやすい場所で働きたい」「地域の企業との繋がりを持ちたい」といった希望がある方にとっては、ハローワークの担当者から具体的な求人の紹介が受けられるのは非常に心強い要素となります。また、自治体によっては独自の就労支援策や助成制度がある場合もあり、それらの最新情報を得られる点も見逃せません。たとえば、障害者の雇用に対して交通費や訓練支援費などの助成金制度を活用できるケースがあり、それらを利用することで通勤や生活の不安を軽減することができます。こうした地域ごとの制度や取り組みはインターネット上では見つけにくいことが多いため、直接窓口で確認することが有効です。地域に根ざした情報を得ることで、就職後も無理のない生活スタイルを構築しやすくなります。
求人票ではわからない“職場の雰囲気”をどう見極める?
求人票に書かれている内容だけでは、実際の職場の雰囲気や働きやすさまではわからないことが多いです。たとえば「配慮あり」と書かれていても、具体的にどのような配慮がされているのか、実際にそれが日常業務の中で機能しているのかは、実際に見てみないと判断できません。そのため、就職活動を進めるうえでは「職場の空気感」や「社員同士の関係性」、「障害者がどのような業務を担当しているか」などを見極めることが重要です。特に精神障害や発達障害のある方にとっては、人間関係やコミュニケーションの負担がストレスになることも多いため、安心して働ける環境かどうかは大きなポイントとなります。こうした職場の実態は、就労移行支援事業所や転職エージェントを通じて得られる場合もありますし、実際に「職場見学」や「企業実習」に参加することで、自分自身で確認する機会を持つこともできます。働く前に職場の雰囲気を把握しておくことで、就職後のミスマッチを防ぎ、長く安定して働くことが可能になります。
職場見学でチェックしたいポイント
職場見学は、求人票では読み取れない「現場のリアル」を知る貴重な機会です。実際に職場を訪問することで、働いている人の表情や仕事の進め方、休憩スペースの様子、社内の音の大きさや照明の明るさなど、五感を通じて感じられる情報があります。たとえば、社員同士の声かけが丁寧だったり、障害者と健常者が自然に協力し合っている場面を目にすれば、「この職場なら安心して働けそうだ」と感じる材料になります。また、面談で企業側に「どのような配慮をしていますか?」「過去にどのような障害者の方が働いていましたか?」といった質問をすることで、実際の支援体制や受け入れ姿勢も確認できます。就労移行支援事業所を通して見学を行う場合は、スタッフが同行してくれることも多く、安心して確認ができる環境が整っています。自分にとっての「働きやすさ」が何かを意識しながら、見学を通じて判断する視点を持つことが大切です。
職場見学でチェックしておきたい観察ポイント一覧
職場見学では、以下のような点を意識して観察すると、より実態に近い判断ができます。まずは「社員の表情や会話の雰囲気」を見て、ストレスの少ない職場かどうかをチェックします。つぎに「障害者の方がどんな業務をしているか」「配慮がどのように実施されているか」などを聞き取り、具体的な支援内容を把握しましょう。また、照明の明るさや音の大きさ、作業空間のレイアウトなど、感覚過敏がある方にとっては職場環境も重要な要素です。さらに、上司や同僚の距離感、質問しやすい雰囲気かどうかも確認したいポイントです。トイレや休憩室の使いやすさ、昼食スペースの雰囲気なども、実際の就労に関わってくるため見逃せません。もし可能であれば、社員の方と数分でも直接話をする機会を持つと、その職場で働く人の価値観や人間関係の質が見えてきます。職場見学は「見た目」だけでなく、「感じ取る」ことが大切です。自分に合った環境かどうかをしっかり見極めることで、安心して働ける職場選びにつながります。
| 観察する要素 | チェックポイント | 理想的な例 | 避けたい例 |
| 職場の雰囲気 | 挨拶・表情・空気感 | 穏やかで挨拶が交わされている | ピリピリして無言の空気 |
| 環境の音や光 | 雑音の有無・照明の種類 | 静か/自然光・間接照明あり | 大音量の電話・蛍光灯まぶしい |
| 作業スペース | 自分の空間があるか | デスクが整っていて距離感も適度 | 密集していて落ち着かない |
| 上司・同僚の様子 | 接し方や声かけのトーン | 丁寧でゆるやかなコミュニケーション | 命令口調・圧が強い |
作業環境・人の対応・音や照明など、五感で感じる情報を大事に
職場見学では、目に見える設備や社員の言葉だけでなく、自分の五感を使って感じる情報がとても大切になります。たとえば、作業スペースの広さや清潔さはもちろん、空気の流れや温度、においなど、実際に働く際の「快適さ」に直結するポイントを意識してみましょう。また、職場内で交わされている挨拶や雑談、指示の出し方など、人の対応にも注目してください。表面的に親切に見えても、実際のやり取りに温かみがあるか、障害のある方への声かけが自然に行われているかなどを感じ取ることが大切です。さらに、発達障害や精神障害のある方にとっては「音」や「照明」が大きなストレスになる場合もあります。機械音や話し声が反響していないか、蛍光灯の光が強すぎないかなど、自分の感覚と照らし合わせながら見ておくことが必要です。職場の見た目だけではなく、実際にその場に身を置いて感じる「居心地の良さ」は、長く働く上での大きな指標になります。こうした五感によるチェックは、自分に合った職場を選ぶための大切な判断材料となります。
面接時に確認すべき「合理的配慮」の具体例
障害者雇用の面接では、自分の特性を企業に伝えることと同時に、「どのような配慮が受けられるのか」を確認することが非常に重要です。合理的配慮とは、障害のある方が他の社員と平等に働くために必要な職場環境や勤務条件の調整を意味します。面接時には、抽象的な説明にとどまらず、具体的な事例を確認するようにしましょう。たとえば「通院のための早退や遅刻に対応してもらえるか」「突発的な体調不良時の連絡方法や休暇の取り方」「業務内容の範囲をあらかじめ明確にしてもらえるか」「対人ストレスを軽減するための一人作業の導入や配席の調整」など、実際に働く中で困るかもしれない点について率直に質問することが大切です。企業によっては、マニュアル化されている配慮もありますが、個別の対応が可能かどうかを事前に確認しておくと、就職後のギャップを防ぐことができます。また、「以前に障害のある方を採用した経験があるか」や、「入社後に定期面談の機会があるか」といった点も、働きやすさに直結する情報です。合理的配慮をお願いすることは、特別な要求ではなく、安心して働くための当然の権利です。遠慮せず、自分にとって必要なサポートを明確に伝え、企業側の対応方針をしっかり確認しておくことが、安定した職場選びの鍵となります。
| 必要な配慮の例 | 面接での聞き方 | 意図 | 確認すべきポイント |
| 通院への配慮 | 「定期的な通院があるのですが、柔軟に対応いただけるでしょうか?」 | 勤務調整が可能かどうか | 有休/中抜け対応など |
| 音・光などの環境面 | 「集中力に影響が出やすいため、席の場所などご配慮いただけることはありますか?」 | 作業環境の調整可否 | 静かなスペースが確保できるか |
| 休憩の取り方 | 「体調により、タイミングを見て休憩を取りたいのですが可能ですか?」 | 自律的な調整が許されるか | 一律ルールでないか確認 |
自分に必要な配慮が“想定されているか”がカギになる
障害者雇用の面接では、「自分に必要な配慮が、企業側にあらかじめ想定されているかどうか」が、入社後の働きやすさを大きく左右します。たとえば、うつ症状や発達障害を持つ方が、静かな環境や業務指示の方法に配慮を求める場合、それが初めての配慮事項となる企業よりも、すでに同様の対応実績がある企業のほうが安心して働ける傾向があります。実際、「atGPジョブトレ」や「ミラトレ」のような支援サービスでは、障害特性に応じた配慮内容をあらかじめ明文化した企業と連携しているため、利用者は入社後のギャップを感じにくいといった実績もあります。面接時に企業側が「どのようなサポートが必要ですか」と丁寧に尋ねてくれる場合や、「こういった配慮実績があります」と話してくれる場合には、障害への理解度が高く、継続して働ける職場である可能性が高いです。一方で、配慮に関しての質問がない場合や、こちらの説明に戸惑う様子が見られる場合は、慎重な判断が求められます。自分がどのような環境で力を発揮できるかを言語化し、それを企業とすり合わせることが、長く安心して働ける職場探しのカギとなります。
求人探しのときに大切にしたい“自分軸”のつくり方
求人を探すとき、多くの人がつい「条件のよさ」や「通いやすさ」など外的な要因に目を向けがちですが、障害者雇用で後悔のない転職をするには、自分の内面と向き合い「自分軸」を持つことがとても重要です。自分軸とは、何のために働くのか、どんな環境で自分は力を発揮できるのかといった「価値観」や「生き方」に基づいた選択の基準です。たとえば、「人と関わりすぎると疲れてしまうので、黙々と作業できる仕事が向いている」「医療費を安定して払うために、長く続けられる職場がいい」といった考えが自分軸になります。この軸を明確にしておくことで、求人選びの段階でもブレずに判断ができ、周囲の情報に流されることが少なくなります。また、自分軸があると、面接時の自己紹介や志望動機にも一貫性が生まれ、企業側にも強い印象を与えることができます。就労移行支援などを活用すると、支援員と対話を重ねながら自分の価値観を言語化するサポートを受けられるため、ひとりでは気づけない視点にも出会えるでしょう。
働きたい理由を明確にする
就職活動を始めるうえで最初に取り組みたいのが、「なぜ働きたいのか」という自分自身の理由を明確にすることです。これは、自分のモチベーションを支えるだけでなく、面接時に説得力のある話ができる基盤にもなります。特に障害者雇用では、就職の理由が「収入の安定」だけでなく、「自立した生活を送りたい」「社会と関わりたい」「日々のリズムを整えたい」といった精神的な動機にも関わってきます。たとえば、「親元を離れて一人暮らしを目指したい」「子どもと暮らすために経済的な基盤を作りたい」といった現実的な動機は、そのまま就職活動の原動力になります。理由がはっきりすると、求人を見たときにも「これは自分の目標につながるかどうか」を判断しやすくなり、職場選びに迷いが減ります。自分の働きたい理由を紙に書き出してみたり、支援機関でキャリアカウンセリングを受けたりすることで、頭の中が整理されていきます。明確な「働く理由」がある人ほど、ブレない軸で求人を選び、結果としてミスマッチの少ない職場にたどり着きやすくなるのです。
働きたい理由を明確にするための内省ステップ
働きたい理由を明確にするには、まず自分の「現状」と「これからどうなりたいか」を見つめ直す内省(ないせい)のプロセスが必要です。第1ステップとして、自分の日常生活の中で「困っていること」「改善したいこと」を書き出してみましょう。たとえば、「昼夜逆転を直したい」「人と話す機会を増やしたい」などが挙げられます。第2ステップでは、「働くことによって、その困りごとがどう変わるか」を考えてみてください。「働けば生活リズムが整う」「収入が得られれば安心して生活できる」といったつながりが見えてきます。第3ステップでは、自分にとって働くことがどういう意味を持つのかを言語化します。「自立の一歩」「人との関係性を築くきっかけ」「自分らしさの表現」など、自分の価値観に近づく言葉を探していきましょう。こうしたステップを踏むことで、自分が「何のために働くのか」が明確になり、求人選びや面接でも自然に言葉が出てくるようになります。就労支援機関では、このような内省を支援するワークシートや面談の機会があり、一人で整理が難しい場合も安心して進めることができます。
| ステップ | 質問例 | 自分の答え | 気づいたこと |
| ステップ1 | 「今までどんな仕事が楽しかった?」 | 人と話を聞く仕事が楽しかった | 自分は“聞き役”にやりがいを感じる |
| ステップ2 | 「辞めたいと思ったのはどんな時?」 | 評価されないとき、無理を強いられたとき | “感謝される”職場を求めている |
| ステップ3 | 「働くことで何を得たい?」 | 社会とのつながり/生活リズム/自己肯定感 | お金だけじゃない“居場所”がほしい |
お金のためだけじゃない、「居場所としての職場」があるか
障害者雇用での職場探しにおいて、「収入」だけでなく「居場所」としての安心感や心の安定を求める方は少なくありません。特に精神的な不安や孤立感を抱えやすい方にとって、ただの労働環境ではなく、人間関係やサポート体制が整った「居心地の良い場所」であることがとても大切です。たとえばミラトレでは、支援員が一人ひとりの悩みを丁寧に聞き取り、個別支援計画を立てた上で、安心して通える雰囲気づくりに力を入れています。また、ココルポートでは就労後も定着支援が充実しており、就職先でも孤立せずに継続できるよう配慮されています。居場所としての職場があることで、自分らしさを失わず、長期的に安定して働くことが可能になります。就職活動では給与や勤務条件だけでなく、「ここなら安心して通えるか」という視点も忘れずに持ちたいところです。
希望条件を細かく書き出して優先順位をつける
自分に合った職場を見つけるためには、まずは「何を大切にしたいか」を明確にすることが大切です。勤務時間、通勤距離、仕事内容、職場の雰囲気、配慮内容、給与条件など、人によって重視するポイントは異なります。これらの希望条件を具体的に書き出し、それぞれに優先順位をつけることで、自分にとって本当に必要な条件が見えてきます。例えば、「フルタイムよりも短時間勤務」「一人作業よりもチームでの仕事」「通院を続けやすい柔軟な勤務体制」など、細かく考えることでミスマッチを防ぎやすくなります。就労移行支援を行っている事業所では、この優先順位づけをスタッフと一緒に行うケースも多く、特に初めての転職活動ではこの整理が有効です。障害の特性や体調の波がある方にとっては、こうした自己理解と職場選びのマッチングこそが、就職後の安定につながります。
希望条件を整理するための優先順位付けシート
希望条件を整理する際におすすめなのが「優先順位付けシート」です。これは、希望する条件を複数リストアップし、それぞれに「絶対に譲れない(最優先)」「できれば満たしたい(中優先)」「あれば嬉しい(低優先)」などのランクを付けていくシートです。たとえば、通勤時間、職場の人数、仕事内容の内容、在宅勤務の可否、給与水準、職場の雰囲気など、できるだけ具体的に記載することがポイントです。こうした整理を行うことで、求人情報を見たときに迷わず判断でき、自分に合った企業選びがしやすくなります。就労移行支援事業所の中には、こうしたシートを活用した個別支援プログラムを提供しているところもあります。ココルポートでは自己分析プログラムの一環として、自分の強みや苦手を把握し、職場にどんな配慮を求めるべきか明確にするサポートが行われています。一人での整理が難しい場合は、専門の支援員に相談しながら作成していくとよいでしょう。
| 条件 | 自分の希望 | 優先度(高・中・低) | 理由 |
| 勤務時間 | 週3〜4、1日5時間以内 | 高 | 体調に波があるため |
| 通院対応 | 週1の午前中に通院 | 高 | 治療継続が就業の前提 |
| 在宅勤務 | 可能なら週の半分在宅 | 中 | 通勤の負荷を減らしたい |
| 職場の人間関係 | 穏やかな雰囲気 | 高 | 過去の職場でのトラウマがある |
| 給与水準 | 月10万円以上 | 中 | 生活に必要な最低ライン |
「在宅希望」「通院配慮」「静かな環境」など正直に洗い出す
障害者雇用を目指す上で、自分の希望や配慮が必要な点をあらかじめ洗い出しておくことはとても大切です。「在宅勤務を希望したい」「通院のために休みを取りたい」「静かな環境で働きたい」など、生活リズムや体調に影響する項目ほど、正直に言葉にして整理しておく必要があります。支援事業所の現場では、この自己整理を支援員と一緒に行いながら、求人選びや職場との調整に役立てています。たとえばmanabyでは、在宅訓練やeラーニングを活用しながら、自分に合った働き方を模索する支援を行っており、発達障害や精神障害の方も安心して自分のペースで学び、働き方を見つけることができています。こうしたニーズは、曖昧にしたまま就職活動を進めると、ミスマッチや早期退職につながりかねません。自分の「こうありたい」を素直にリストアップすることで、支援者や企業との橋渡しがスムーズになります。
不安や希望を“言葉にして相談する”習慣を持つ
「自分に合った職場を見つけたい」と思っていても、不安や希望をうまく伝えられないという方は少なくありません。特に障害のある方の場合、「どこまで話していいのか」「理解してもらえるのか」といった不安がつきまといがちです。しかし、職場とのミスマッチを防ぎ、継続して働くためには、不安や希望を具体的な言葉にして相談する習慣が必要です。ココルポートやキズキビジネスカレッジなどの就労移行支援事業所では、こうした「相談する力」を育てるための面談練習や、グループワークが多く取り入れられています。自分がどのようなサポートを望んでいるのかを言葉にする訓練は、就職面接だけでなく、入社後の人間関係や仕事の進め方にも役立ちます。最初はうまく言えなくても、繰り返し練習することで自然と表現力が身につき、自信を持って話せるようになります。
不安や希望を“言葉にして相談”できるようになる訓練シート
不安や希望を整理し、第三者に相談できるようにするための「訓練シート」は、就労支援の現場で多く活用されています。シートには「今、何が不安なのか」「どんな働き方を希望しているのか」「過去に困った経験は何か」などの質問項目が並び、自分の思いや状況を可視化する手助けをしてくれます。たとえば、SST(ソーシャルスキルトレーニング)を取り入れているココルポートでは、こうしたシートを使って模擬面談を行いながら、相手に伝える力を養っています。訓練シートの活用によって、「自分にはこんな特性があり、こんな配慮があると働きやすい」という伝え方が自然と身につきます。また、支援員との面談で使うことで、具体的な就職先選びにもつなげられます。あらかじめ書き出すことで頭の中が整理され、面接や職場見学の際にも堂々と自分の気持ちを伝えることができるようになります。相談が苦手な方ほど、こうしたツールを活用することで一歩前に進むことができます。
| 状況 | 書き出した不安・希望 | 言葉にした例 | 相手に伝えた結果 | 感じた変化 |
| 通院について | 「通院があるのに迷惑かも…」 | 「週1で通院があり、その日は午前勤務希望です」 | 「調整できますよ」と言ってもらえた | 言ってよかったと安心 |
| 業務負荷 | 「いきなりフルタイムは無理かも」 | 「最初は短時間勤務から始めたいです」 | ペースを考慮したプランを提示された | 自分の希望が通じたことで前向きに |
| 対人ストレス | 「会話が続かないのが不安」 | 「会議や雑談は控えめだとありがたいです」 | 配慮できるよう調整すると回答あり | 無理せず働ける職場かもと感じた |
それが“配慮のある職場”と出会う第一歩になる
自分の不安や希望を正直に洗い出し、それを言葉にして相談できるようになることは、「配慮のある職場」と出会うための大切な第一歩です。求人票の条件だけではわからない職場の雰囲気や、どこまで配慮してもらえるかといった点は、応募者側が自分の状況を具体的に伝えることで初めて、企業側も対応を考えられるようになります。就労移行支援事業所では、そうした「自己開示」と「希望条件の整理」に重点を置いた支援を行っており、たとえばミラトレやmanabyでは、個別性を尊重した訓練と面談を通じて、企業とのミスマッチを防ぐ工夫がなされています。配慮を受けることは特別なことではなく、「働き続ける」ための当然の準備です。自分に必要なサポートをきちんと理解し、それを伝える準備が整えば、きっとあなたに合った職場と出会えるはずです。
【まとめ】障害者雇用 求人 探し方|自分に合った職場は、きっと見つかる
障害者雇用での就職活動は、一般的な求人探しとは異なり、特性への理解や配慮を前提とした職場との出会いが重要です。そのためにはまず、自分自身の特性や希望条件を明確にし、優先順位をつけていくことが欠かせません。「在宅勤務」「通院配慮」「静かな環境」など、自分にとって無理のない働き方を知ることが、求人選びの軸になります。そしてそれを言葉にして伝えられるようになることで、支援員や企業との信頼関係も築きやすくなり、結果として定着率の高い職場に就職できる可能性が広がります。atGPやココルポート、キズキビジネスカレッジなど、さまざまな就労移行支援機関では、こうしたプロセスを一人ひとりに寄り添ってサポートしています。お金のためだけではなく、「居場所」として安心できる職場を見つけること。それは簡単な道のりではないかもしれませんが、正しい手順を踏めば、必ずたどり着ける道です。焦らず、着実に、自分に合った働き方を探していきましょう。
関連ページはこちら
配慮されている求人ってどんなもの?
実際の「合理的配慮」がある求人事例を紹介し、どんな働き方が可能か具体的に解説しています。
→関連ページはこちら【実例あり】合理的配慮がある求人とは?働きやすさを重視した求人の選び方ガイド
障害者手帳を転職活動に活かすには?
転職時の使い方や、企業への伝え方のコツを紹介しています。
→関連ページはこちら【完全ガイド】障害者手帳を転職で活かす方法|働き方・制度・交渉のコツまで
うつ病からの転職成功体験談
「もう働けないかも」と思った人が見つけた働き方と、安心できる職場との出会いを紹介しています。
→関連ページはこちら【体験談】うつ病で退職した私が、転職で見つけた心がラクな職場
就労移行支援ってどう使うの?
初めての利用でも安心できる、手続きから通所、就職までの流れをわかりやすくまとめています。
→関連ページはこちら「就労移行支援 利用 方法」へ内部リンク
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
生活とお金に関するおすすめ情報まとめ(ドメイントップページ)を見る
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
厚生労働省「障害者の雇用について」もあわせて参考になります

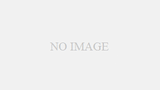
コメント