「このまま働き続けていいの?」と感じているあなたに、心療内科から始まった私の転職の話
朝起きるたびに、「また今日も仕事か」とため息をつく日々が続いていませんか。仕事のことを考えるだけで気が重くなり、職場の人間関係や業務量に疲れ果て、「もう限界かもしれない」と感じている方も多いのではないでしょうか。私もかつてはその一人でした。心療内科に通うようになったことをきっかけに、自分の人生や働き方を見直し、転職という選択肢に目を向けるようになりました。この記事では、私の経験をもとに、心の不調から始まった転職活動のリアルと、その先で出会った就労移行支援の取り組みについて紹介します。もし今、働くことに苦しさを感じているなら、あなたにとっての新たな一歩を考えるきっかけになるかもしれません。
心療内科を受診したのは、限界を迎える直前だった
仕事が辛いと感じる日々が続いていたある朝、体が動かなくなりました。頭では「会社に行かないと」と思っても、体がベッドから離れないのです。前の日の夜も、眠れずにただ天井を見つめていました。そのとき初めて、「自分はもう限界かもしれない」と自覚しました。心療内科を受診したのは、まさにその数日後のことです。医師から「適応障害の可能性がある」と伝えられ、初めて自分の状態を客観的に知ることができました。症状に名前がついたことにより、なぜあの時つらかったのか、なぜ眠れなかったのかを理解することができたのです。そして、その出来事が、私の働き方を見直すきっかけとなりました。
朝が来るのが怖くて、眠れない日が続いた
眠ろうとしても、頭の中では仕事のことばかりがぐるぐると回り、気づけば朝日が差し込んでいる。そんな夜が何日も続きました。メールの未返信や、上司からのプレッシャー、人間関係の気まずさ、そして自分のミスへの後悔。小さなストレスが積み重なって、やがて心と体のバランスが崩れていったのです。目が覚めても全身が重く、顔を洗う気力も湧かず、会社に向かう足取りは鉛のように重かったのを今でも覚えています。周囲には「体調が悪いだけ」と取り繕っていましたが、内心では「いつまでこの状態が続くのか」という不安でいっぱいでした。このままではいけない、でもどうすればいいかわからない。そんなときに相談したのが、心療内科でした。
朝が来るのが怖いと感じ始めた心と体の変化
「朝が怖い」と感じるようになったのは、ある日突然ではなく、少しずつでした。最初はなんとなく寝つきが悪い日が増え、次第に「明日も仕事か」と思うだけで心拍数が上がるようになりました。それに伴って胃の不調や頭痛が出てくるようになり、休日も心から休めない状態になっていきました。心療内科では「休養と環境調整が必要」と言われましたが、すぐに仕事を辞める決断はできませんでした。しかし、その後、就労移行支援やカウンセリングの情報に出会い、「働き続けるために環境を変える」という選択肢を知りました。例えば、ミラトレやキズキビジネスカレッジのような就労支援事業所では、心や体の不調を抱える人が安心してキャリアの再出発を図れる支援が用意されており、私のような経験をした方にとって、心強い選択肢となるでしょう。自分の状態を受け止める勇気と、支援を求める行動が、未来を変える第一歩になったのです。
| 時期 | 体のサイン | 心の状態 | 朝の自分の行動 | 今の自分からの視点 |
| 1週間前 | 早朝覚醒・頭痛 | 仕事の夢を見る | スヌーズを何度も押す | 既にSOSは出ていた |
| 3日前 | 動悸・胃の不快感 | 出社が怖い | ベッドから動けない | 体が限界を知らせてくれていた |
| 当日 | 呼吸が浅くなる | 涙が止まらない | 会社に「休みます」とだけ伝えた | 休むことが必要な日だった |
体は元気なのに、心だけが動けなかった
朝起きて、体を動かす力はあるのに、なぜか会社に向かうことだけができない。そんな不思議な感覚に苦しむ日々が続きました。熱があるわけでもなく、骨折しているわけでもない。けれど、心のどこかに重い鉛のようなものがのしかかっていて、職場に足を踏み入れることができないのです。電車のホームに立った瞬間、急に涙が出てきたり、会社の最寄り駅で動けなくなったり、そんなことも何度もありました。「サボっているだけなのでは」「みんなも我慢して働いているのに」と自分を責め、体が元気だからこそ「ちゃんと行かなきゃ」という焦りが強まりました。ですが、後に医師から「心のエネルギーが枯渇している状態」だと説明され、自分の苦しみにはちゃんとした理由があるのだと知ることができました。外見ではわからない心の限界があるという事実を受け入れるまで、時間がかかりました。
「ただの甘えかも」と思いながら、初めて病院の扉を開いた
「病院に行くほどじゃない」「誰かに相談するなんて恥ずかしい」と思いながらも、もう一人ではどうにもできないところまで来てしまった自分に気づいたとき、やっと心療内科の門をくぐりました。病院の受付で名前を呼ばれるだけでも心拍数が上がり、「ここにいること自体が間違いではないか」と不安になったことを覚えています。それでも、医師と向き合い、話をする中で少しずつ心がほどけていきました。「それは甘えではなく、心が限界を迎えている証拠です」と言われたとき、張りつめていた気持ちが少しだけ和らぎました。自分では「まだ大丈夫」と思っていたけれど、実際には心が悲鳴を上げていたのだと、そのとき初めて理解できたのです。
「甘えかも」と思いながら受診したときの思考と変化
病院に行く前の私は、どこかで「この程度で受診するなんて、自分は弱い人間だ」と感じていました。周囲の人が普通に働いている中で、自分だけが立ち止まってしまっていることへの罪悪感や、社会に置いていかれる不安が常に頭の中にありました。けれど、診察を受けてみると、医師は私の話に耳を傾けながら、「がんばってきたんですね」「無理をしすぎたのかもしれません」と静かに話してくれました。その一言が、自分を責め続けていた心をゆっくり解きほぐしてくれました。「甘えではなく、回復のための選択だった」と、後から思えるようになりました。また、就労移行支援などの制度があることを知り、「働きたいけど今は休みが必要」という状態を受け入れてくれる環境があることにも救われました。ミラトレやココルポートなどの事業所では、心の状態を見ながら無理なく社会復帰を目指す支援が用意されています。自分の苦しみを認め、助けを求めることは、弱さではなく、大きな第一歩なのだと実感しました。
| 気持ち | 病院へ行く前 | 診察中 | 診察後 | 気づいたこと |
| 不安 | 「本当に病院に行っていいのか」 | 緊張で言葉が出ない | 医師の言葉に涙が出た | 誰かに受け止めてもらうだけで救われる |
| 自責 | 「怠けてるだけじゃ…」 | 状況をうまく説明できない | 「休んでいいんですよ」に驚いた | 自分の感じていたことに“名前”がついた |
| 期待 | 「何か変わればいいけど…」 | 症状についての説明に納得 | 次の予約を入れる気持ちが湧いた | “甘え”ではなく“症状”だったと確信 |
医師の一言で、自分を責める気持ちが少しだけ軽くなった
診察室で医師に今の状況を伝えるのは、想像以上に勇気がいりました。「眠れない」「会社に行くのがつらい」「何をしていても心がざわつく」。話しながら涙が出てきてしまい、自分でも驚きました。そんな私の様子を見た医師は、「それは、よくあることですよ」と穏やかに言ってくれました。そして、「あなたは十分がんばっています」と続けてくれたのです。その一言で、胸につかえていたものが少しずつ溶けていくような気がしました。周囲には理解されにくい心のつらさを、否定せずに受け入れてくれる人がいる。たったそれだけで、救われた思いがしました。それまでは「自分が弱いからだ」「もっと努力すべきだった」と自分を責めるばかりでしたが、少しずつ「今の私は、ただ疲れているだけかもしれない」と思えるようになりました。心の状態を誰かに話すことで、初めて自分自身にも優しくなれるのだと知ったのです。
心療内科で相談したことで、自分の状態を客観視できるようになった
心療内科を受診する前は、「自分は何がつらいのか」さえうまく言葉にできない状態でした。仕事に行けない日が増え、焦りと罪悪感だけが募っていく。そんな中で、医師との面談を重ねることで、自分の状態を一つひとつ丁寧に振り返る機会を得られました。どんなときに気持ちが沈むのか、体にどんなサインが出るのか、それを紙に書き出したり言葉にしたりすることで、ぼんやりとしていた「不調」が具体的に見えてくるようになったのです。これまで「とにかく我慢することが美徳」だと思っていた自分が、初めて自分の心と向き合い、「これ以上は無理をしない」という判断ができるようになったのは、大きな転機でした。就労移行支援のようなサービスも、こうした気づきを経てからこそ意味を持つものだと感じます。manabyのように在宅型で学べる環境や、個別支援が整っている事業所では、「心が整ってから働きたい」という気持ちに応える選択肢が広がっています。
“今の仕事がすべてじゃない”という気づき
心療内科に通い始めてからしばらくすると、「今の会社で働けない自分には価値がない」という思い込みが、少しずつ薄れていきました。診察の中で、「働き方にもいろいろな形があります」と医師に言われた言葉が心に残っています。それまでは「一つの会社で、フルタイムで働き続けること」だけが正解だと思い込んでいたのです。しかし、実際には在宅勤務や短時間勤務、障害者雇用や福祉的就労といった多様な選択肢があることを知り、「無理をしない働き方」を自分で選んでもいいのだと気づきました。例えば、LITALICOワークスやatGPジョブトレなどでは、自分の特性に合った仕事を見つけ、安心して働き続けられるようサポートしてくれます。社会に出ることは「普通」に戻ることではなく、「自分に合った形で生きること」。この気づきがあったからこそ、私は再び仕事に前向きな気持ちを持てるようになりました。今の仕事がすべてではない、という視点が、心の余白を広げてくれたのです。
“今の仕事がすべてじゃない”と気づけた瞬間の整理表
| きっかけ | それまでの思い込み | 気づいたこと | 心の変化 | 次に取った行動 |
| 医師のアドバイス | 「今の会社で頑張らなきゃ」 | 働き方に“選択肢”がある | 罪悪感よりも希望が湧いた | 支援サービスを調べ始めた |
| 友人の体験談 | 「辞めたら終わり」 | 他にも似た経験をしてる人がいた | 自分だけじゃないと安心 | 転職の体験談を読むように |
| SNSで見た発信 | 「再就職なんて難しい」 | 配慮のある企業も存在する | 視野が広がった | 障害者雇用について学び始めた |
「働き方を変えてもいい」と思えた瞬間が転機になった
それまでの私は、「正社員で、週5日フルタイムで働く」ことだけが“ちゃんと働いている”証だと思っていました。だから、今の職場に行けなくなった自分を「社会から落ちこぼれた」と感じていました。しかし、心療内科での相談や休養の時間を経て、自分の限界と向き合ったとき、「この働き方を一生続けなければならないのか?」という疑問が自然と湧いてきたのです。周囲に迷惑をかけないように無理をしていた日々を振り返ると、「がんばり方を間違えていたかもしれない」と気づきました。そのとき、「働き方を変えてもいい」と心から思えたのです。この気づきが転機となり、就労移行支援という存在に出会いました。ミラトレやココルポートなどのように、働く前にしっかり準備できる場所があるという事実は、自分にとって大きな安心材料になりました。無理をしない働き方を選ぶことは、逃げではなく、自分を守るための選択肢だと実感できた瞬間でした。
転職を焦らず「準備する」という考え方に変わった
心と体のバランスを崩してから、「今すぐに仕事を見つけなければ」という焦りがいつも頭の中にありました。ですが、焦って転職活動をしても思うように動けず、面接に行くのも怖くて結局手が止まってしまう。その繰り返しでさらに自己嫌悪が強まりました。そんな中、就労移行支援に出会い、「働くために、まずは自分を整える」という考え方を教えてもらいました。生活リズムを整え、ビジネスマナーや対人スキルを身につけ、障害特性に合った仕事を選ぶ。その一つひとつの準備が、「自分はちゃんと前に進んでいる」と思える感覚を与えてくれました。特にココルポートのような支援機関では、自己分析やSST(ソーシャルスキルトレーニング)を通じて、再び社会とつながるためのステップを段階的に学ぶことができます。焦るより、準備を重ねることで、結果的に自分に合った職場を見つけられる。その事実を知ったことで、転職に対する不安が徐々に減っていきました。
「転職は準備が大事」と思えた行動と思考の変化
以前の私は、「今の職場を辞めたらすぐに転職先を見つけないと」と、焦るあまりに自己分析や企業研究をおろそかにしていました。その結果、条件だけで選んだ職場で再び体調を崩し、転職を繰り返すことになったのです。けれど、心療内科で休職を勧められ、就労移行支援に通うようになってから、「自分にとって無理のない仕事とは何か」を見つめ直す時間が持てました。manabyのように在宅で学べる事業所では、個々のペースに合わせてスキルを身につけられるので、心と体の準備がしっかりできます。また、atGPジョブトレのように障害別のコースに分かれている支援機関では、自分の課題に合った訓練を受けることができ、再就職への自信につながります。こうした支援の中で、「今は転職のための準備期間なんだ」と思えるようになったことは、自分にとって大きな変化でした。準備を重ねた上での転職は、結果だけでなく、そこに至る過程にも納得ができるものになると実感しました。
| 状態 | 焦っていた頃 | 準備期間中 | 準備を通じて得たこと | 今の自分の考え |
| 心の余裕 | 不安でいっぱい | 「今は整える時間」と思えるように | 焦らなくても道はあると実感 | “急がず確実に”の大切さを実感 |
| 情報収集 | とにかく求人検索だけ | 支援制度や職場環境もリサーチ | 自分に合う条件が見えてきた | 条件だけで選ばない視点が持てた |
| 自己理解 | 「なんとなく合わない」 | 強み・苦手を言語化した | 伝える力がついた | 面接で自信を持って話せた |
カウンセリングを通じて、キャリアの見直しができた
心療内科に通い始めてから受けたカウンセリングでは、自分の思考パターンや過去の経験を少しずつ掘り下げながら、どこで無理をしていたのかを一緒に整理していきました。最初は「ただ話すだけで変わるのか」と半信半疑でしたが、何度か通ううちに、心の中で整理できていなかったことが言葉になっていくのを感じました。例えば、自分のキャリアに対する理想像がいつの間にか「周囲と比べた結果」でできあがっていたことや、「役に立ちたい」という気持ちが過剰な自己犠牲につながっていたことにも気づきました。そうした内面の気づきを通して、「キャリアとは自分らしく働くための道であって、他人の正解をなぞるものではない」という新たな視点が生まれました。カウンセリングは、ただ心を整えるだけでなく、人生全体を見直すための大切なプロセスだったのです。
自分に合った働き方を探すために動き出したこと
これまでの働き方が自分に合っていなかったと気づいても、すぐに「じゃあどうすればいいのか」は見えてきませんでした。ただ漠然とした不安と向き合いながらも、「次は無理をしない働き方を選びたい」という思いは強くなっていきました。そんなとき、就労支援サービスの存在を知り、勇気を出して一歩踏み出すことにしました。たとえば、LITALICOワークスやatGPジョブトレでは、個別相談を通して自分の適性や体調に合った働き方を見つけるサポートをしてくれます。また、支援スタッフとのやり取りの中で、仕事に対する考え方を見つめ直す機会も多くありました。「働く=フルタイム・正社員」という固定観念から離れて、「自分が長く続けられる働き方とは?」という視点で職場を探すようになったのです。この動き出しが、再出発への確かな第一歩となりました。
就労支援サービスに相談して「無理しない働き方」を模索
最初に就労支援サービスに連絡するまでは、「自分の悩みなんて相談してもいいのか」と迷っていました。けれど、実際に話をしてみると、支援員は否定せず、親身に耳を傾けてくれました。そして、「無理をしない働き方も、立派な選択ですよ」と言ってくれたのです。その言葉に救われたと同時に、「自分だけが特別に弱いわけではない」という安心感も得られました。就労移行支援では、パソコンスキルやビジネスマナーを学ぶだけでなく、社会とのつながりを取り戻す練習の場にもなっています。manabyのような在宅訓練ができるサービスでは、自分のペースで無理なく学ぶことができ、精神的な安定を保ちながら前に進めることが特徴です。支援を受けることで、ただ仕事に就くためだけでなく、「自分に合った働き方」を一緒に模索していくという意識が芽生えました。
就労支援サービスに相談して変わった“働き方”への向き合い方
就労支援サービスに相談する前の私は、「働くこと=耐えること」という感覚が強く、自分に合っていなくても我慢して続けるのが当たり前だと思っていました。しかし、サービス利用を通じて「働くことは、心身ともに安定した状態でこそ意味がある」と実感するようになりました。支援員との面談や、実際の職業訓練を経験する中で、「疲れすぎない働き方」や「自分の強みを活かす仕事の探し方」を知ることができたのです。特に、ミラトレのような就労支援では、コミュニケーションやビジネススキルだけでなく、模擬職場体験などを通じてリアルな働き方を体験できたことが、自信につながりました。働くことは「耐えること」ではなく、「自分らしく生きるための手段」として捉えられるようになった今、もう一度社会に踏み出す覚悟と希望を持つことができました。支援を通じたこの変化は、人生の大きな転機となりました。
| 相談前の状態 | 相談で話したこと | 担当者の対応 | 相談後の気づき | 変わった行動 |
| 何から始めていいか分からなかった | 自分の苦手・理想の働き方 | 否定せず、具体的な選択肢を提示 | 「一人で考えすぎていた」と実感 | 勤務形態や条件を絞って検索できた |
| 転職が怖い・不安しかない | 働きたいけど自信がない | 焦らず準備しようと言ってもらえた | 焦りがスーッと引いた | 小さな目標からスタートした |
| サービスの存在すら知らなかった | どこに相談すればいいか | 他の支援制度や窓口も紹介された | 情報が整理されて頭が軽くなった | 支援機関に定期的に通うように |
在宅勤務や短時間勤務、配慮ある職場の存在を知った
以前の私は、働くとは「会社に毎日通ってフルタイムで働くこと」だと思い込んでいました。しかし、就労支援を通じて多様な働き方の存在を知り、その考えは大きく変わりました。とくに、在宅勤務や短時間勤務、フレックス制度など、心身の状態やライフスタイルに合わせて働ける職場が実際にあると知ったことは、大きな希望につながりました。また、企業によっては障害者雇用に積極的で、精神疾患や発達障害のある社員に対して、勤務時間の調整やコミュニケーション方法への配慮を行っているところもあります。LITALICOワークスやatGPなどの支援機関では、そうした配慮のある求人を紹介してくれるだけでなく、職場定着までをサポートしてくれる体制が整っています。自分の状態を受け入れ、それに合った働き方を選べることで、「また働けるかもしれない」と感じるようになりました。
発達特性やメンタルの不調に理解ある企業を選ぶコツ
企業を選ぶ際、「ネームバリュー」や「給与」だけを基準にしてしまうと、自分の特性と合わない環境に身を置くことになりかねません。発達特性やメンタル不調を抱える人にとっては、環境そのものが自分の働き方や体調に大きく影響します。そのため、まずは「どんな配慮があれば安心して働けるか」を明確にすることが大切です。例えば、口頭よりもテキストでの指示が安心できる、業務の見通しが立っている方がストレスが少ない、などです。そして、それに対応できる企業かどうかを見極めるポイントとして、求人票に記載されている「障害への配慮」や「就業時間の柔軟性」「通院への理解」などをチェックするのが効果的です。dodaチャレンジやマイナビパートナーズ紹介などでは、実際に企業にヒアリングを行い、配慮内容を確認した上で求人紹介をしているため、自分一人で調べるよりも安心して選ぶことができます。
“配慮がある企業”を見極めるための就活チェックポイント
配慮ある企業を見極めるには、求人情報の「障害への理解」という文言だけでは不十分です。具体的にどのような配慮が行われているのか、事前に確認することが重要です。まず注目すべきは「通院や体調に応じた勤務調整の可否」「業務内容の明確な分担」「定期的な面談やフォロー体制の有無」です。これらは職場で無理なく働き続けるために欠かせない条件です。また、企業見学や実習が可能な求人であれば、実際の職場の雰囲気や社員との関わり方を体験できるため、入社後のミスマッチを防げます。さらに、atGPジョブトレやmanabyなどの支援機関を利用することで、企業と事前に面談を設けてもらったり、自分に合った質問を代行してくれたりと、安心して企業選びができる仕組みも整っています。“配慮がある職場”は、自分の希望や特性を正直に伝えた上で、対話の中で見つけていくもの。だからこそ、焦らず丁寧に向き合うことが、自分らしく働ける場所に出会うための近道になるのです。
| 見るべきポイント | ダメだった企業の例 | 良かった企業の例 | チェック方法 | 判断の目安 |
| 面接時の対応 | 病歴に反応が薄く、曖昧な返答 | 「どんな配慮が必要ですか?」と聞いてくれた | 面接でこちらの話を遮らないか | 聞く姿勢と柔軟性があるか |
| 求人内容の透明性 | 「配慮あり」と書いてあるだけ | 通院配慮、残業なしなど具体的に明記 | 求人票と実際の話に差がないか | 事前情報とズレがないか |
| 社内制度 | 特になし/形だけの制度 | 面談制度・産業医との連携あり | 福利厚生や制度の有無を確認 | 制度が“実際に使われている”か |
障害者雇用や支援付き就職サービスが鍵だった
働き方を見直すなかで出会った「障害者雇用」や「支援付き就職サービス」は、私にとって新しい世界でした。以前は「障害者枠での就職」と聞くと、何か制限のある働き方というイメージを持っていましたが、実際にはその逆で、「無理をしない働き方」を支えてくれる制度だったのです。例えば、atGPやマイナビパートナーズ紹介のような転職サービスでは、自分の特性をきちんと伝えたうえでマッチする職場を探すサポートがあります。支援員やキャリアアドバイザーが丁寧にヒアリングしてくれることで、これまでの職場で「うまくいかなかった理由」も明確になり、自分に合った職場選びがしやすくなりました。また、企業側も障害に配慮した勤務体制を整えている場合が多く、「働きやすさ」や「理解ある環境」に出会える確率が格段に上がるのです。この制度の存在を知ったことが、再出発への大きな支えになりました。
心療内科×転職を考える人が知っておきたい3つの支援策
仕事のストレスやメンタルの不調から心療内科を受診し、「このまま今の仕事を続けていいのだろうか」と悩む人は少なくありません。そんなとき、必要なのは無理に働き続けることではなく、「休むこと」と「備えること」、そして「支援を受けること」です。現代には、心の不調を抱える人が再び社会で活躍するためのサポートが多数用意されています。特に「就労移行支援」「障害者雇用」「支援付き転職エージェント」の三本柱は、回復と再出発を両立させる上で非常に有効な制度です。これらの制度を知り、活用することで、「働けない自分」から「自分らしく働ける環境を選ぶ自分」へと意識が変わっていくでしょう。ここからは、それぞれの支援策がどのように役立つのかを、具体的に紹介していきます。
① 就労移行支援でのステップ復帰
就労移行支援とは、障害やメンタルの不調などにより一般企業への就職が困難な人が、社会復帰に向けてステップを踏みながら準備できる制度です。支援事業所では、生活リズムの安定から始まり、ビジネスマナー、職業訓練、就職活動支援まで、トータルでサポートが受けられます。医師から休職や転職をすすめられた際、「でもこの先どうすればいいのか分からない」と悩む人にとって、まさに“橋渡し”となる支援です。特に、LITALICOワークスやミラトレ、manaby、ココルポートなどの支援機関は、それぞれに特徴があり、利用者のペースや特性に合わせたサポート体制が整っています。
就労移行支援で得られたステップ復帰の安心感
私が就労移行支援を利用して感じたのは、「今のままでも受け入れてもらえる場所がある」という安心感でした。まずは生活リズムを整えることから始まり、少しずつ日中に活動できる時間を増やしていく。焦ることなく、自分のペースで進める環境があることが、精神的な安定につながりました。たとえば、manabyでは在宅訓練ができるため、外出が負担になる時期でも無理せず学びを進められましたし、LITALICOワークスでは実践的な就職活動の支援を通じて、自己理解や自己表現の仕方を深めることができました。また、訓練中に支援員が日々の変化を共有してくれることで、「今日はこれができた」といった小さな成功体験が積み重なり、自信を取り戻すことができました。就労移行支援は、ただの職業訓練ではなく、「心のリハビリ」としての意味も大きいと実感しました。再び社会とつながる準備として、これほど心強いサポートは他にないと感じています。
| ステップ | 内容 | 当初の気持ち | 実際の印象 | 続けて得られたもの |
| 利用説明〜登録 | 支援内容や通所ペースを確認 | 不安と緊張でいっぱい | 丁寧に説明されて安心できた | 信頼できる場を得た |
| 生活リズム訓練 | 朝起きて支援先へ通う | 起きられるか不安 | 徐々にリズムが整ってきた | 自己管理に自信がついた |
| 軽作業・グループワーク | 対人活動や作業練習 | うまくやれるか心配 | 成功体験が少しずつ積み重なった | 「また働きたい」と思えるように |
| 求職サポート | 面接練習・求人紹介 | まだ早いかもと思っていた | 無理に急かされず安心 | 自分のタイミングで進められた |
② 発達障害に特化した支援サービスの活用
発達障害を抱えて働くことに不安を感じている方にとって、「自分の特性を理解してもらえる環境」は非常に重要です。しかし実際には、職場でのコミュニケーションに戸惑ったり、集中力の波や段取りの苦手さからミスを繰り返し、自信をなくしてしまう方も少なくありません。そんな中で、発達障害に特化した就労支援サービスは、自分の特性を活かしながら働くための“伴走者”となってくれます。
たとえば「atGPジョブトレ」では、発達障害に特化した専門コースが用意されており、グループワークや個別支援を通じて、自己理解や対人関係スキルを高めるプログラムが実施されています。また、職場での想定シーンを取り入れたロールプレイや、作業への取り組み方の工夫を学べる訓練もあるため、実践的なスキルが身につきやすい点が特徴です。こうした支援の中で「できないこと」よりも「できること」に意識が向くようになり、自己肯定感を取り戻していく利用者が多く見られます。
LITALICOワークスでも発達障害のある方に向けた個別支援が充実しており、相談の段階から丁寧なヒアリングを通じて、就職活動の不安を一緒に整理していきます。また、特性に合わせた求人提案や職場定着支援まで行う体制が整っているため、働きはじめた後も継続して安心できる点も魅力です。
発達障害のある方にとって、「自分の苦手は工夫で補える」「強みを活かして働ける」という実感を得ることは、自立に向けた大きな一歩になります。そうした支援の場があることで、今までの働きづらさを振り返り、「自分に合った働き方を選べばいい」と前向きに考えられるようになるのです。無理をし続けるのではなく、「支援を受けながら働く」という選択肢を持つことが、これからの自分らしい働き方につながっていきます。
発達障害に特化した支援サービスの強み比較
| 支援内容 | 発達特性に対する配慮 | 特に役立ったこと | 他サービスとの違い | 活用のヒント |
| スケジュール視覚化 | 視覚的な指示で予定を把握しやすい | 「次に何をするか」が分かりやすい | 口頭だけの指示に頼らない | カレンダー+マグネットなどが活用される |
| コミュニケーション練習 | ロールプレイ中心 | 相手の気持ちを知るきっかけに | 講義より実践多め | 面接練習が苦手な人に◎ |
| 感覚過敏対策 | 音・光の配慮がある空間づくり | 集中できる環境がありがたい | 一般的な支援より個別性高い | 施設見学で「静かさ」を確認するとよい |
③ 理解ある転職エージェントとのマッチング
心の不調や発達障害、精神的なストレスを抱えた状態での転職活動は、孤独や不安を伴いやすく、うまく進まないことでさらに自信を失ってしまうこともあります。そんなときに力となってくれるのが、「障害への理解がある転職エージェント」の存在です。単なる求人紹介にとどまらず、一人ひとりの状況や特性を丁寧にくみ取りながら、無理なく働ける環境を一緒に探してくれる支援者がいるだけで、転職活動の負担は大きく変わります。
たとえば「マイナビパートナーズ紹介」では、精神障害や発達障害、身体障害を抱える方に向けた非公開求人を数多く扱っており、障害への理解がある企業を厳選して紹介してくれます。登録後にはキャリアアドバイザーとの面談が行われ、過去の職場での経験や現在の体調、希望する働き方について丁寧にヒアリングがなされます。そのうえで、時短勤務やテレワーク、通院配慮のある求人など、個別に配慮されたポジションを提案してくれるため、安心して応募に進めるのです。
また「atGPエージェント」も、精神・発達障害を持つ方に特化したエージェントサービスで、履歴書や職務経歴書の添削から面接対策、就職後の職場定着支援まで一貫したサポートを提供しています。特に、障害者雇用に積極的な企業とのマッチングに強く、過去の利用者の中には「はじめて自分の特性をオープンにして働けた」と話す人もいます。
こうしたエージェントとの出会いは、単なる転職先探しではなく、「自分の働き方を再定義する時間」となり得ます。理解のある担当者と出会うことで、「働けるかどうか」ではなく「どこで、どのように働くか」を前向きに考えられるようになるのです。自分だけでは見つけられなかった選択肢や、視野の広がりは、エージェントという第三者だからこそ得られる大きなメリットだといえるでしょう。
理解あるエージェントとの出会いで変わった就職活動
以前の私は、求人サイトを眺めながらも「自分が応募できそうな仕事がない」と感じ、転職活動そのものをあきらめかけていました。そんなとき、思い切って登録した障害者雇用に特化した転職エージェントとの出会いが、大きな転機となりました。担当者は私の話をじっくりと聞いてくれ、「無理にフルタイムで働く必要はありませんよ」「配慮のある職場を一緒に探しましょう」と言ってくれました。その言葉だけで、肩の力がふっと抜けたのを今でも覚えています。
エージェントの提案してくれる求人は、勤務時間や業務内容に配慮があり、職場の理解も進んでいる企業ばかりでした。また、面接前には模擬面接を通じて自分の強みや課題を整理できたことで、久しぶりの就職活動も安心して臨むことができました。その結果、自分のペースを大切にしながら働ける職場に出会うことができ、「もう一度社会で役割を持つことができた」と実感するようになりました。
就職活動が怖い、動き出せないと感じている方にこそ、理解のあるエージェントとのマッチングは大きな助けになるでしょう。自分の特性や希望を受け入れてくれる伴走者がいるだけで、「一人じゃない」と思える安心感が生まれ、前に進む力になるのです。
| 相談前のイメージ | 実際の面談内容 | 驚いたこと | 一緒にできたこと | 気持ちの変化 |
| ゴリ押しされるのでは? | まずは“今の不安”を丁寧に聞いてくれた | いきなり求人を押し付けられなかった | キャリア整理・企業選び | 「無理しなくていい」と思えた |
| 条件を伝えるのが難しそう | “働ける時間・働けない条件”も聞かれた | 弱みではなく“前提”として受け止めてくれた | 希望条件の言語化 | 自分の意見を言う練習になった |
| 希望が通らないかも… | 企業側にも事前に情報共有してくれた | マッチングの前に“環境の相性”を重視してた | 見学同行・交渉代行もあり | 面接が“怖いもの”ではなくなった |
働きずらさを感じている人におすすめの転職サービス
dodaチャレンジ|ストレスを減らせる環境を一緒に考えてくれる
→dodaチャレンジ アフィリリンクを貼る
関連ページはこちら:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
LITALICOワークス|働く前に心の準備ができる就労支援
→LITALICOワークス アフィリリンクを貼る
ランスタッド|大手だから安心して相談できる環境がある
→ランスタッド アフィリリンクを貼る
atGP|理解ある職場紹介で再出発を後押ししてくれる
→atGP アフィリリンクを貼る
ミラトレ|小さな練習から始められる就労移行支援サービス
→ミラトレ アフィリリンクを貼る
【まとめ】心療内科 転職 相談|心の声を無視せず、働き方を見直してよかった
「このまま働き続けていいのだろうか」と悩みながら過ごしていた日々。朝が来るのが怖く、眠れない夜が続いたこと、そして心と体のバランスが崩れた自分に気づいたこと。それらすべてが、転職を考えるきっかけとなりました。心療内科での受診は「甘えではないか」と迷いもありましたが、医師の言葉やカウンセリングによって、自分の状態を受け入れ、客観的に見ることができるようになりました。そして、「今の仕事だけがすべてではない」「働き方は変えていい」という気づきが、人生を見直す大きな転機となったのです。
その後、就労移行支援や障害者雇用、支援付き転職エージェントといった制度を知り、無理なく、自分のペースで働くための準備を始めました。manabyやミラトレ、LITALICOワークス、atGPジョブトレなど、多くの支援機関があることを知り、「自分に合った場所がきっとある」と思えるようになったのは、心に大きな安心感をもたらしました。また、理解ある転職エージェントとの出会いにより、「一人で頑張らなくていい」と思えるようになったことも、再出発の大きな支えとなりました。
働き方を見直すことは、決して逃げではありません。むしろ、自分の人生に責任を持つための前向きな選択です。心の声を無視せず、立ち止まり、自分のペースで新たな道を探す。その経験があったからこそ、今の私は、以前よりも自分らしく働けています。同じように悩んでいる方にも、「無理をしなくていい」「頼っていい」「変えていい」というメッセージが届くことを願っています。
関連ページはこちら
発達障害のある人向け就職支援の選び方
自分に合った仕事と職場を探すために知っておきたい支援サービスの内容を紹介しています。
→関連ページはこちら「発達障害 就職 支援 サービス」へ内部リンク
在宅勤務への転職を考えている人へ
心身の負担を軽減できる働き方を目指した在宅転職の体験談を紹介しています。
→関連ページはこちら「在宅勤務 転職 体験談」へ内部リンク
障害者雇用の求人を探すときのポイント
職場環境や配慮の内容など、求人選びで気をつけたい点をまとめています。
→関連ページはこちら「障害者雇用 求人 探し方」へ内部リンク
就労移行支援の使い方と利用の流れ
無理のないステップでの社会復帰を支援してくれる就労移行支援の活用方法を紹介しています。
→関連ページはこちら「就労移行支援 利用 方法」へ内部リンク
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
生活とお金に関するおすすめ情報まとめ(ドメイントップページ)を見る
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
厚生労働省「こころの健康」ページも参考になります

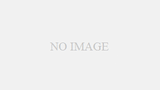
コメント